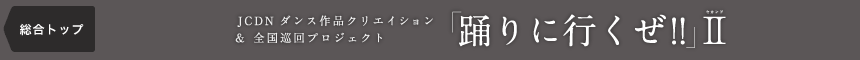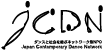森田淑子インタビュー [Aダンスプロダクション]
森田淑子「ヤマナイ、ミミナリ」について語る

「ヤマナイ、ミミナリ」仙台公演より photo:越後谷出
(収録:2014年2月9日仙台/テープお越し:渋谷陽菜 聞き手・編集:水野立子)
森田さんは、1年前の「踊2」vol.3のAプログラムに応募して選出されていたが、作品制作をスタートさせていた9月に大きな事故にあい参加することができなくなってしまった。いったんは言葉を失ったところから、歩けるようになるまでリハビリを経て復帰し、今年のvol.4に応募して再選出されたという経緯があります。作品構想から2年、巡回公演初演となった札幌、1か月後の仙台公演を終えた直後に、初めての本格的な作品制作についての取り組みを伺いました。インタビューの話題に出てくる、<家族のこと、事故のこと>についての補足情報として公演当日パンフレットに掲載しているテキストを下記に転用します。
※当日パンフレットより
「ヤマナイ、ミミナリ」森田淑子
ここ何年もずっと、自分のからだの中に小さな違和感があった。何かがじわじわと喉の奥に込み上げる。息苦しさで、叫びだしそうになる。ずっとそうだ、理由はわからない。
しかし、いつまでも耳鳴りがやまない。
このテキストは、2012年8月に踊りに行くぜⅡVol.3のチラシ用に書いたものです。
「ヤマナイ、ミミナリ」という作品を創ろうと思ったきっかけは2つあります。
1つ目は、私の家族が違う国で生まれ、異なる文化、異なる言葉のもとで育ち、家族同士、言葉で理解し合えずに、家族のもとを離れたことです。
きっかけの2つ目は、1年前、事故に遭い、脳に損傷を受けて歩けなくなり、失語症によって言葉を失ったことです。
その2つをきっかけに、言葉とは本当はどういうものかを考えるようになり
「ことばのむこう」をベースに作品を創り始めました。
なぜ、再び生きる時間を与えてもらったのか。その答えに向かい合い、踊ります。
>>事故にあったことで作品制作が1年後に伸びたこと。私小説という制作方法。
ー今回の作品の構想はいつから始まったんですか?
1年前の「踊2」vol.3の説明会に参加したときですかね。だから、2012年の春ですね。
―その時からこの方向性は決まっていたの?
いや、その時は違うコンセプトの方向もありました。公募説明会に行ったときのメモには、「コインロッカー・ベイビーズ」って書いていましたね
―あの時ってタイトルがそうだったっけ?
いえ、タイトルは全然決まってないですね。ただ、村上龍の小説「コインロッカー・ベイビーズ」が自分にとって印象深い作品だったんです。それをどうやってダンス作品にしようか、というところまで思いついてなかったですけど。この小説とダンスで何かミックスして出来ないかと思ったのが始まりでした。
―vol.3の1次選考を通過して、プレゼンの2次選考のときもかなりこの「コインロッカー・ベイビーズ」が核となったものだったですね。
あーそうですね。今回の作品ではこれをモチーフに使おうってことはなくなりました。
―その変化の経過はどういうことがあったのだろう?その変わっていった経路。
うーん、徐々に変わっていったんですけど、水野さんに「小説にこだわらず、もっと自分のテーマを掘り下げていったほうがいいよ。」と言われたこともヒントになりました。
―それは何時頃の会話だっただろう?二年前選出された後のミーティングかな?
そうですね。「踊2」のフライヤー撮影の前に品川でお茶しながら話した時、私の家族の話になって、やっぱり小説の「コインロッカー・ベイビーズ」が印象深かった部分と、家族のことが繋がっているという話をしました。私の親が韓国人なので日本語がうまく使えないこと、私は日本で生まれ育ち、親は韓国の文化だから、その違いがあり意思疎通がうまくいかなかったこともあり。言葉については考えていました。で、水野さんにその私の実際の家族の話の方に興味が惹かれると言われて、そういうことが興味を惹く事になるんだというのは意外でしたね。一緒に作品をつくるメンバーにも同じことを話したんです。それまでは、家族の状況のことになんて興味ないだろうと思ったんですけど、「独特だね。そのことにふつうは興味惹くでしょう。」って言われて、「あーそうなのか。」と思って。
やっぱり「コインロッカー・ベイビーズ」の奥には自分の家族がいたって事は確かだなあと。で、それを作品に出来るかもしれないって思えたのは、水野さんの話があったからです。
―普通より変わっている家族関係だな、ということに興味を惹かれたわけじゃないですよ。森田さんが結局、小説「コインロッカー・ベイビーズ」の話からインスパイやされて何をやりたいのかって考えると、村上龍の小説ではなく、森田さん自身の存在だとか、生きる事とか伝わってきて、その事に興味を持ったっていう意味なんです。これはもう、村上龍じゃなくて、森田淑子のことを私小説として作品にしたほうがいいと思った。
はい。そうでしたね。水野さんから“私小説”という手法の話を聞きましたね。わたしはそのとき初めて聞いたんですが。文学の私小説のことも聞きました。
―どうも森田さんの作品へのこだわりが、そこにあるように感じて、じゃあそれを“私小説”という手法をとりいれてやった方が、はっきりするし、つくりやすいのではないかと。それで文学では田山花袋「蒲団」とか、舞台では川口隆夫さんの「パーフェクトライフ」とかがあるよ、という話しをしたんだった。その頃、川口さんの作品をみてとても私的な出来事であるはずなのに、それを作品として公にすることで、それが他人の心にすっと入り込むことができるというのを見た直後だったから、森田さんもなにかヒントになるかな、と思って。
そうでしたね。わたしはみたことはなかったので、実感はなかったけど、そうかな、と光が見えたような気がしました。1年後のダンス・イン・レジデンスの青森王余魚沢で、飯名尚人さんにも同じく川口さんの話を聞きました。
―そうでしたね。やっぱり同じ共通点がみえるんですね。いまの作品は、ダイレクトに家族のことはないよね。
マフラーの踊りは家族の踊りなんですけど。
―そっかそっか。やっぱり根底にあるから要素はでてくるんですね。

「ヤマナイ、ミミナリ」仙台公演より photo:越後谷出
進藤が踊っている“ぬいぐるみ”の踊りも家族の踊りなんですよ。踊りをつくってもらう時にいくつか項目を選んでもらい、家族とか写真とかいくつかピックアップしてつくるように最初に言ったんですね。進藤は家族の踊りをやりたいっていったので、それを8月からつくり始めました。今までカットした振りが多いのですが、最後までこのシーンは残っています。
―なるほど。テーマが家族のこと、ごくプライベートなことを私小説的に作品にしようってなっていったときに、事故があって一旦、保留になっていまの作品への変化の過程を是非お聞かせください。森田さんの中で心身ともにどんな体験が関係したのかな?
今回の新たにつくることになった作品のきっかけになったのは、やはり事故でした。自分自身も、家族が誰だったのかも、全てわからくなった経験を経て、だんだん思い出していって「あ、この人は家族。」ってわかるようになるまで時間がかかりました。「家族」っていう言葉もその時は分からなかったですけど。病院に来てくれた母も、なんとなくこの人は知っている、と後でわかったくらい、全てがぼんやりしていました。
―そういう分からなくなったことが、分かってくるという事は凄い事だったんだろうね、きっと。
>>歩けるようになったことは、作品に入れています。
スプーンって言葉がほんとに面白くて。スプーンがなかなか覚えられなくて、ずーっと時間かかったんですよ。
―それって得な体験だね。赤ちゃんが、言葉を覚えてくる過程って覚えていないじゃない。だけど、それを認識できるわけだからすごいね。ヘレン・ケラーの話みたいだね。コップをさわらせて、コップだと教えても、言葉と物の関係がヘレン・ケラーにはわかんなかったけど、形のない水の流れからようやく認識できたのは、冷たいとか、感触とか感覚でわかったのかなと思うんですよ。水を「water」 と分った時、雪が溶けるように全てが認識できていき感動したように、森田さんも同じような経験だったんですかね?
私もどうやってこれがスプーンで、これがお皿って、物に名前があるってことをわかっていったか、今になって分からないんですよ。多分ですけど、思い出した瞬間があって三分後には忘れてるんですよ。その繰り返しがあって。「あー!この言葉はスプーン。」って教えられた事は頭にあって。子供と同様、覚えていないんです。
今の作品に具体的に取りいれていることは、やはり“歩く”ことですね。自分が歩けるようになったことは鮮明に覚えてるんです。
―段階があると思うけど、自分の足で立てるまで二ヶ月くらい?
9月16日に事故にあい、11月頭までかかりました。
―二ヶ月弱か。歩けるようになるまでの鮮明に覚えている感覚は、身体の感覚みたいなもの?
そう!体重がかかって重いって感じるんですよ。かかるんですよ、重さが。何でこんなに重いんだろうって。で、歩くように指示されてバーにつかまって一歩足をおこしたら頭とか肩が揺れることに驚いて。
―子供が歩行する時の感覚と同じなのかな、どうなのかな。森田さんはそれをダンスにしようとしたわけですね。
はい、やはり強く残っていることなので今回の作品の中で入れています。
―「ヤマナイ、ミミナリ」というタイトルでもあるように、事故にあって身体が全然動かなくなったところから、歩けるようになったっていうそこの関係はどういうことなんですか?
世界から色がなくなって見えたと入院した時に思ったんです。それがだんだん、過去の記憶を思い出した時に、昔こんなことしてたとか、ダンスしてたとか、「踊2」に応募したとか、今自分の状況を分かってきて、「あ、病院ってとこで寝てるんだ」ってそれしか分かんなかったんですよね。
その後、今の自分と過去の自分を思い出してきた時に、歩けて本当に嬉しかった思いから、一気に落胆して心が不自由になった。その時、色が消えたと思ったんですよ。こんな身体で生きていくんなら生きていないほうが良かったって。
―逆転しちゃった。
そうです。過去を思い出して今の自分がわかってくると。だからこれがコップで、スプーンでって分かるようになったことが嬉しかったんですけど、本当に反対の思いも同時にありました。だから、ずーとっ葛藤が起こり作品にも葛藤のシーンを入れています。
>>モノクロの世界から、色がついてきたカラーの世界に。
「小林さんの美術の特徴は、独特な色使いだと私は思います。」

「ヤマナイ、ミミナリ」仙台公演より photo:越後谷出
―色カラーが作品の真ん中くらいからでてきますね。あれはその落胆から、希望が見えたみたいな、色がまた見えたみたいなことが実際におきたの?
自分の体験では段々と気づいたら逆転してたって感じですね。真っ黒な世界からポツポツポツとすりガラス越しに色が見えてきた、それが段々と見えてきたって感じですかね。
―なるほど。舞台美術でグレーからカラーに色があふれるオブジェが使われていますね。小林さんに美術をお願いすることにしたのは、この作品の美術にあう作家だということからですか?
いくつかの経緯があって小林さんに美術をお願いすることになったのですが、結果的にはそうです。小林さんの活動を知るきっかけになったのは、退院後、病院ボランティアに興味があり調べていたところ、小林さんのホームページにたどりついたことです。それから何度も小林さんの作品を拝見しました。その後、もう一度「踊2」に応募することになった時、小林さんの美術作品が浮かんだんです。事故に遭う前にお願いしていた美術作家さんも、様々なアイデアを持っていらして素晴らしい方だったのですが、今回の作品は以前つくりたいと思っていた作品とテイストが違っていました。小林さんの美術の特徴は、独特な色使いだと私は思います。今回の作品は、やりたいことに色を使うことが含まれていたので、小林さんにお願いすることになりました。
―今回、制作を開始して約半年になりますね。実際にこんなにガッツリとメンバーと作品と向き合うなんて初めてだよね?
はい、初めてです。
―巡回公演で、二箇所でしかも自分が知らない人に観て貰うという経験も初ですね。率直に凄くワクワクする事なのか、それとも怖いって思う事なのか、どっちなのか?
両方ありますよ!当然怖いですよね。でも、やったことないことはやってみないとわからないから。どこまで出来るか自分を試そうって気もありますし。
>>言葉で表せないこと、伝えられないことがある、本当のことがわかってしまう。それをダンスにしたい。

「ヤマナイ、ミミナリ」仙台公演より photo:越後谷出
―どうしても、ここだけは伝えたいんだ、っていうところ、どういう事がこの作品で一番届けたいことですか?
言葉で話しても、話さなくても、相手に必ず伝わってしまうことがある、ということ。多分、国籍とか、使っている言語とか全然関係なく、身体と身体に対してアプローチをしたら、どうしても伝わってしまう事、隠せない事がありますよね。上手く言葉で誤魔化しても「A」って言葉の裏にある「B」がどうしても透けて見えてきてしまう。そういう事だと思います。
―森田さんの場合は、このことを表現する場合、救われる事と、自分が傷つく事、どっちの側なのかな?
本当は相手からのつらい言葉を真に受けて、自分が傷つけられてしまったと思いがちだけど、それは思い込みで、一見つらいと思う言葉の裏には愛情だったり、そう言ってくれた意味があるんだって、後から気付いたんですね。
―言葉って発してしまったらもう取り消せない「言霊」って言うでしょう。無意識に発したことで傷つけたり失敗したって思う事がいっぱいあるのね。私は。
ありますねー私も多い。
―タイムマシンで戻りたくなりますね。その後悔の気持ちと、この人こんなこと言ってるけど、本当のその奥を私は見ることが出来るんだよね、っていう誇らしい気持ちと二つあると思うんです。
自分の経験で言うと両方あります。作品としては、それがわからない時期のことも含んでます。その後の、言葉のむこうにある言葉にならないことがある、ということを私が見えたことも伝えていける作品にしたいです。
ー実際には、面と向かって言いにくいことも、作品でそれを伝えることができるといいですね。みた人が救われるかもしれない。そういう事が伝わる作品になるといいなあ。
仙台に来て、ゲネ前の一回目の通し終わって、帰りにメンバーに話した事から自分は家族を作品のテーマの一部に作ってるのに、まだ家族のこと見てないんだって気付く事があって、「家族がこれを観てくれたらどう思うかな。」って考えてしまったことがあって、そういう事を考えると辛くなるので考えないようにしてたんですね。でも、家族がテーマにあるのにそれを考えないでどうするって仙台に来てやっと思えて、まぁ、実際は見てないですけど、多分、家族が観て喜んでくれる踊りをしたいって、初めて通しでその気持ちを思いながらいたことが出来て。
―ダンス、ダンス作品をみることで、やっぱり救われるっていうか、生きられるんだって思える力が舞台作品にはあると思う。まあ自分が後悔する失敗をしているから、わかることもあるしね(笑)
もーそりゃ、しちゃってます。恐ろしくなるくらい。
―なんかこう、届きそうな感じがするから、あとどうするかだね。メンバーとはそういうことって共有してるの?
してます。
―そういう意味では作家として幸せだよね。
―初めて作品をつくる場合、ありがちなのは、作家がやりたい事をメンバー間で共有できないことが多いと思う。演出家、振付家が、出演者や音楽家、美術家に自分の目指す世界をどう共有して力を出してもらう仕事ができるかどうか。森田チームは、そういう意味ではうまく進んでいるようにみえますね。ドラマツゥルクという立場をつくったことも功をなしたのかもしれないですね。後はじゃあダンス作品として、どうみえてくるのか?まさにテーマである言葉でいえない感覚をダンスでしか立ち上がらない世界をつくらないと、ですね。
昨日の仙台初演後、主催者やお客さまから色んな感想や意見を頂いて、色々触発されることが多かったんです。なんていうか、今すぐ変えてどうみえるかっていう思いに駆られて。明日の公演までに、ダンサーだけで話して色んな提案が一気に出てきて、仙台が終わったら試したいこと、アイデアが出てきています。
―楽しみです。森田さんの経験、事故を通してなくしてしまった感覚を壮絶に取り戻すまでの身体感覚と、人との関係にあるひづみになっていることがクロスしている。だからこそダンス作品でしか、表現できないものが現れるとくると思う。小説ではできない事を、その感覚をダンスにしていけるんじゃないか、と思いますね。話をきいていると必然を感じられて、すごく可能性があるなと思っています。後悔と希望と絶望とグチャグチャになって、ぐるぐる回るようなことだから、それをダンスでやれたら、「あーわかる!」っていう、そういう踊りはいいよね。振付や森田さん自身がこの作品で、ダンスをつくり踊るうえで、ポイントにしていること、目指していることをお聞かせください。
私と違った視点で作品を捉えているチームメンバーの意見を、自分の中で噛み砕き、まずは一度試してみることです。複数のメンバーがいることで、同じ考えを共有しながらも、少し違った視点で見ていると気づくときは、面白いなぁと思います。また、メンバーから言われて気づいたことなのですが、たまに自分の中だけで自己完結して、それをメンバーに伝えていないことがあるようなので、思ったことはすぐに伝えるように心がけています。目指していることはたくさんありますが、ひとつは自分の作品や振付を客観視した時に、やりたいことの通りに見えているか、稽古や劇場で臨機応変に判断し対応することです。
作家はこれができないといけないことは理解しているつもりですが、自分の作品を客観視するのは本当に難しいです。最後は、自分がやりたいと思っていることは、どうしてもやりたいことなのか、なぜやりたいのか、自分自身の考えを自分自身でよくわかっていることでしょうか。そういうことは、メンバーからの質問がヒントになることも多いです。
あとの東京、京都公演までにあらゆる引き出しを使って、もう一度演出、振付をしていきたいと思います。
―最終の2か所公演で自分が満足できる作品になっていればよいですね。ありがとうございました。