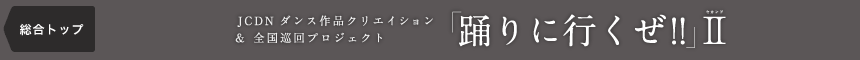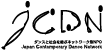今年のAプログラム3作品が出揃いました。
どうも。水野です。巡回公演も2か所を終え佳境に入ってきた感じで、なんというかソワソワしてきました。世の中では、インフルエンザが猛威をふるっているようで、踊2の出演者とスタッフがいかにその感染から逃れるかが命題です。出演者が隔離されたら上演できなくなりますから、大変だー!

(巡回公演舞台スタッフチーム!)
さて、今年のAプログラム、札幌公演では森田淑子作品「ヤマナイ、ミミナリ」、鳥取公演では黒沢美香作品「渚の風<聞こえる編>」と、余越保子作品「ZERO ONE」がそれぞれ初演を終え、全3作品が出そろいました。なんだか今年は、様子が違うねえ、という声もいただきます。そう、いままで応募対象として特に設定していなかったのですが、2年前あたりから経験のある作家から、「対象は新人じゃないとダメ?応募してもよいのか?」という問い合わせをいただくようになり、今回の応募要項から*初めて作品をつくる人、*経験のある人、と対象を明記したところ、幅の広い層からの応募となりました。
そういうわけで今年のAプロは、バラエティー豊かです。ジェネレーションもかなり違う(笑)初めてダンス作品をつくる森田淑子チームと、十分すぎる貫録の黒沢さんと、N.Yでは知らない人はいない注目度のある余越さんですが、日本ではほぼ無名、初日本制作。この3作品で残りの巡回地を各地のBプログラムと走ります。最終東京公演と京都公演はこのAプロ3作品のみの上演ですので、ご注目ください。
先週末の鳥取公演での余越、黒沢作品の初演の印象に残ったことをHOTなうちに書き留めておきます。
この二人の振付家が、今回の作品で選んだダンサーはまるで正反対です。黒沢さんは<ミカヅキ会議>ダンサー歴ほぼなし、大学教授。余越さんは、ダンサー歴10年以上のバリバリ現役双子ダンサー。ところがですよ、お二人の話を聞いていると、ダンスへのアプローチが実はとても近いことを発見。
以前、余越さんがニューヨークのKitchenのキュレーターをしていた頃、黒沢さんの作品を招聘したときの話を伺ったとき、両者のダンスへのスタンスというか、求めるものは共通性を持っていると感じていました。鳥取公演終演後のアフタートークでの客席からの質問「なぜ、ダンスで表現するのか、なぜ、ダンスなのか?」の答えを聞いて、さらにそれが明確になった気がします。「ただただ、ダンスでなければできないことをやっている。ダンスに仕える、捧げる、行方をお聞きする感じです。」「最初から作品がどこに向かうのかは、わからない。ダンスは今しかないんです。」伝え方は違えども、二人のダンスそのものをつくる振付を堀り起こすときの感覚が非常に似ているなあと。
作品をみるとこのことが、とても納得させられるんですね。2作品とも、目の瞬きを忘れるように「じっ」とみるダンスでしたよ。

(「渚の風<聞こえる編>」 photo:Shinji Nakashima)
話は変わって、今年のお正月、「井上陽水ドキュメント<氷の世界>40年」というTV番組をみたんですが、それがとてもおもしろかった。アルバム収録全曲を本人、制作プロデューサー、スタッフはもとより、作家、評論家が当時の秘話や時代背景とともに、なにゆえこれが爆発的に売れたのかを分析していくという内容。おもしろすぎて録画してたから3回くらい見ました。「氷の世界」のアルバムの内容は、まったくもって、明るいわけでも希望があるわけでもなく、むしろ救いがない。そして混沌としている。1973年当時、残念なことにわたしはまだ井上陽水を理解できるほど大人ではなく、若干年下の世代。オイルショックで経済不況がやってきて、家計も大変、というのはぼんやりと記憶にあり、そんな時代が1973年。陽水自らが語るアルバムのテーマは、「不条理」と。普通はメジャーにならないであろう<不条理>をテーマにした音楽を100万人の日本人が買いあさったという事実、これはやっぱりおもしろいし、すごい。何故そんなに力があったのだろうと考えると、マイナーメジャーが関係なくなるほど、行き場のない気持ちが蔓延していたのだろう、そして誰もが、その共有感覚をこのアルバムに見たのだろう。もしかすると、40年前の日本の社会と今は似ているのかもしれない、と思った。リッチな人も貧乏な人も、同じように先がみえないと思っていて、幸せを感じにくいと思っている。
40年前の井上陽水はいまほどビッグじゃなかったわけで、しかし、同時代の音楽になりえたわけだ。いま同時代の作家がつくるダンス作品こそ、わたしたちの心に響くものになり得るのではないか、そうあってほしいと思った。

さて、この「氷の世界」のTV番組の話がいったい何の関係あるのか、というと、鳥取公演の余越作品「ZERO ONE」を見たとき、これはまさに不条理だなあ、と感じたから。見た目が同じ外見の双子ダンサーの踊りを見ていると、客席にいる私と舞台のダンサーの区別がつかなくなってくる、そんなダンス。日常と非日常が同居する首くくり栲象さんの映像。聖職者のような、詐欺師のような摩訶不思議な唄。双子ダンスがお互いを操ったり、いじめたり、愛しんだりが頂点に達すると、まるで自分の体に空いた穴をみているような感覚になる。ダンスというとても抽象的なものをみているのだが、自分と他者の間にある存在を思考できる豊かさがあった。そこには、どうにも手がでない不条理世界があった。井上陽水のアルバムは、大ヒットになったけど、ダンス作品はヒットする間もなく消えていくから、劇場でライブで是非見てくだされ!今しかみれないダンスです。
余越さんのインタビューを公演前夜、短い時間でしたが収録しました。ミカヅキ会議のみなさんにも公演後、お話を伺ったので、近いつちにUPします。
そして、来週末は仙台公演で、再び余越作品と森田作品の2か所目、「報告するぜ!!」の取材も入ります。乞うご期待ください!!


(「ZERO ONE」 photo:Shinji Nakashima)