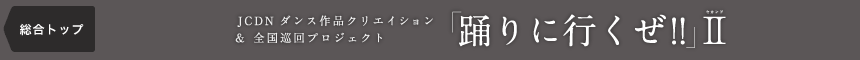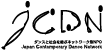作品だけが知っている、そのために。
テキスト:飯名尚人
明けましておめでとうございますー。今月から、いよいよ「踊りに行くぜ!!セカンド」各地のツアーがスタート。作品を楽しむための裏情報コーナー「報告するぜ!!」も、どんどん更新していきます。年明け一発目は、余越保子さんの作品「ZERO ONE」についてです。
昨年末、カポーティ原作の映画「冷血」を見た。アメリカの目立たない片田舎の町で実際に起こった一家惨殺事件のノンフィクションノベルである。カポーティはこの作品で実際の事件を扱いつつも小説としての文体を取り入れた手法でノンフィクションノベルのスタイルを見い出し、その先駆的存在となった。一家惨殺という犯人の冷血が描かれつつも、冷血であるのは一体誰なのか、冷血なのはカポーティ自身か。カポーティは何度も犯人に接見する経過で犯人のひとりへ感情移入が高まりつつも、しかし小説として洗いざらい書き連ねるための取材を進める。この小説を書く過程を映画にした「カポーティ」という映画作品で、主人公カポーティは、犯人が死刑にならないと小説が終わらない、自分はもうこの小説を終わらせたいんだ、と言い、なかなか執行されない死刑に苛立ち、疲れ果てる。好奇心と良心との戦いである。結果犯人は死刑になるが、この小説以後カポーティは作品を発表していない。犯人からすれば、カポーティからの接見は、すべて己の小説のためだったのか、と裏切られた感もあったに違いない。
ところでカポーティはなぜこの惨殺事件を題材に選んだのだろうか?ノンフィクションノベルという手法を実現させたかったのか、それとも新聞に掲載されたこの事件の記事に魅了されたのか、藪の中だ。なぜその題材なのか、という作品の核心であるような質問は、実は作家にとってさほど重要でないのかもしれない。「訳も無く」「なんとなく」魅了されたというのが正しい理由だろう。作品だけが答えを知っている。となると、鑑賞者に答えが委ねられているとも言える。
余越保子さんの作品「ZERO ONE」は、自身で撮影した映像作品を使い、2人のダンサーが踊る。詳しい演出内容はここでは書かないつもりだ。今のところこの作品は、事前に情報を持たずに観てもらう方がいいような気がしている。そうなると広報宣伝ってものすごく大変だけど。
自分でもどうなるか分からない
昨年末、横浜でリハーサルを見させて頂いた。そこで思ったこと、伺ったことをつらつらと書き込んでみることにする。
映像とダンスは、果たしてクロスカッティングなのか、違うのか。「クロスカッティング」というのは、映画用語だが、G・W・グリフィス監督の「国民の創生」で発明された画期的編集方法である。最近の映画、とくにサスペンスものでは当たり前のように使われているが、犯人が女性を襲いに行く準備をしている映像と、襲われる女性がシャワーとか浴びている映像が、交互に編集されて、徐々にそのクロスがテンポアップされお互いが近づいて行く、という編集方法のことを言う。余越さんの作品はサスペンスではないけれど、Aという風景が映像で流れて、Bという風景が舞台上でダンスによって流れている。このAとBは同時には流れず、それぞれに空間と時間を持っている。さて、この2つは作品の最後にどうなるのか?クロスするのか、それとも、、、
「自分でも、どうなるかわからない、ということをやりたいと常に思っているんです」と余越さんは言う。
AとBという素材をそれぞれ持って来たのは余越さんであるが、それらがどうなっていくのかは「作品にしか分からない」と余越さんが答える。僕は作品の途中経過を見せて頂いたわけだから、当然ながら作品の完成品ではないわけだが、この作品の顛末という興味関心は、僕だけでなく、作者である余越さんの関心でもあるようだ。
ライブ作品というのは、思いがけない何かが勝手に生まれてくるものであって、そういう思いがけない何かが無いライブ作品というのは作っていて面白くないだろう。とくにライブパフォーマンスにおいては、毎日上演するごとに違った何かが生まれることを期待して演出するはずだ。
演出家が「作品をこの世界に持って行きたい」のではなく、「結果、こういう世界になった」という未知なる可能性を楽しむということだろう。セッション、とも言える。どういうことになるかは「作品にしか分からない」という余越さんのスタンスが面白い。どうなるか作者にも分からないのである。
観客としての我々は、つい「意味」を考えてしまう。この映像と、このダンサーはこういう意味があるんじゃないか、とか、この作品はこういう意味なんじゃないか、とか。観客の特権として意味なるものを読み取ろうとしながら作品を見る事の面白さがある。しかし意味を求め過ぎると「えー?なんかー意味分からなかったんですけどー」という感想が飛び交うことになる。大抵の場合「意味が分からない」=「つまらない」という解釈になってしまう。「コンテンポラリーダンスって、あんまし踊らないし、意味わからないし」と。作り手であればこの苦難が分かるだろうが、「見て欲しいのは、そこじゃないんだ!」とジリジリする。じゃあ、何が見せたいんだ!と食い下がってくる観客は、実に寛容な観客だ。そういう観客でいたいと自分では思っている。
じゃあ、何を見せるのか?意味ってなぁに?
分かりやすいメッセージ(というか教訓)が提示されていないと「意味が無い」と判断されてしまう。ざっくり言えば、震災についての作品は意味があって、今日のコーヒーが苦いことには意味が無い、というような。社会的道義を求められてしまうことも多い。しかし、作り手には作り手なりの「作る意味」を持っている。震災もコーヒーが苦いのも、作者にとってみればどちらも同じくらい意味があるのである。余越さんの中にある「作る意味」を探りながら見ると面白いだろう。
「ライブパフォーマンスというのは、お話が伝わったからOK、ということではないですよね。でも時間軸を紡いでいくので、見ていて飽きるわけです、お客さんが。だから振り付けの構成というのは飽きないようにどう構成するか。そこは振付家の腕です。
それからダンサーのキャパのマックスをどう捉えておくか。人間を扱いますから、すり合わせが必要ですね。私がやって欲しいことをやってもらえないこともあるわけですよ。人間同士で時間と空間の軸を紡いでいく。ダンスというには、人がそこにいて動く、それを見る、ということです。ですから戦略が絶対に必要なんです。それで、お客さんが舞台上のダンサーを観て、結局のところ、”あなたたちは誰なんだ?”と。そういうことなんです。」
そんなに頑張って踊って、で、あんた何してるの?
「花が、自分自身で美しいと思って咲いているだろうか?美しいと思うか思わないかは人間の美意識が決めているのではないか?」と、そんなようなことを言ったのは、ヘーゲルだったか、誰だったか、どっかの哲学者であったが、記憶は曖昧、しかしそんなような美学。コンテンポラリーダンスとしての作品はそんな関係を持っているように感じることがある。「どう?!私、美しいでしょー!」というダンスを、余越さんは求めていない。
余越「見せつけるダンス、というのはダメなんです。そうではなく、見てしまうダンスにならないと。」
飯名「私を見て!っていうダンサーは職業的に多いと思うんですけども、そういうダンサーに、”いやそうではなくて、、、”ということを伝えるにはどうしたらいいんですか?」
余越「うーん、諦める!(笑) その前に、そういうダンサーは使わない。もちろんショーダンスではそれが必要ですから、そっちの世界でトップを目指せばいいんです。それは悪いことじゃないわけですから。」
キャスティングは重要である。出来ない人に出来ないことをやらせても、そりゃ出来ないのである。それを出来るように教えてあげる、という必要が作品クリエイションに必要だろうか。僕は必要ないと思っている。それは稽古でやるべきであるから。ダンスカンパニーや劇団であれば、徹底的に日々の稽古で、演出家・振付家のメソッドを染み込ませ、リハーサルに望むだろう。カンパニーを持っていない振付家が、自身の作品でダンサーを集めるのであれば、キャスティングのセンスと、コミュニケーションの能力が作品の質を決めるだろう。人を見る力が必要だ。余越さんは今回の作品で、今回ダンサーとして参加している福岡さんに出会って、この作品のアイディアを積んでいったそうだ。キャスティングありきの作品作りというのは、演出家の一方的なイメージ構築だけでは出来ない。むしろ、演出家が出演者から受ける情報の方が重要かもしれない。そうなると、作者であってもこの作品がどうなっていくかわからない。それは、恋人同士のように「付き合いはじめたときはああだったけど、3年くらいしたらこうなった」というような、どっちがどうというよりは、お互いの変化を受け入れることでもある。
「渡米して、向こうの仲間やディレクターに言われたんです。そんなに頑張って踊って、で、あんた何してるの?って。そう言われたとき、受け入れるのに時間はかかりました。若い時は”150%で踊るんだ!”みたいな感じだったわけです、私も。ところが、リハーサルでリラックスしているときの踊りの方がぜんぜんいいよ、って言われたんです。そう言われた時、え?って思った。どういうこと??って。このことは自分自身ダンサーとして通ってきた道なので、他のダンサーをみたとき、どういうダンサーなのかというのがよく分かるんです。」
余越さんはニューヨークでダンサーとしてのキャリアを積み、日本とはまた違う様々な壁に阻まれながら、独学のように演出の技を得てきたにちがいない。
恐怖心しかない
意外にも日本でクリエイションして作品を発表するのが、なんと今回初めてとのこと。
飯名「日本の観客に観てもらう事について、どう思いますか?」
余越「恐怖心しかないです・・・。」
意外な返答に驚いた。
余越「これまでアメリカ拠点で活動してきて、アメリカで作品を作ってきた。それを日本で上演できないものか、と色々トライしてきたけれど、日本では受け入れてもらえなかった。上演できなかったんです。いろいろな問題、課題があって、権利のこととか、内容のこととか。色々な理由で自分の作品が日本で受け入れられなかった。だから今回、日本の土壌で、日本の空気吸って、日本で作って、日本で上演する、というのをやりたかったんです。
でも現実的にアメリカにいて、日本で作品作って発表しても、お客さんもいないし、受け入れてくれる劇場もない。どうしたものかと。それで”踊りにいくぜ!!セカンド”にエントリーしたんです。日本で唯一、予算がでて、制作もやってもらえる。自分で全てのチケットを売らないでもいい。なので、ここでトライしてみようと思ったんです。」
見る側の心持ちで作品が変わっていく、今月1月から始まる「踊りに行くぜ!!セカンド」のツアーで、毎回違った印象の作品になると楽しい。会場によって当たりハズレがあっても良い、と僕は思っている。(ハズレた場合、各地の劇場には怒られそーですが。。。)
★上演情報
余越保子作品「ZERO ONE」
鳥取 仙台 東京 京都 にて
https://odori2.jcdn.org/4/artist/a03.html