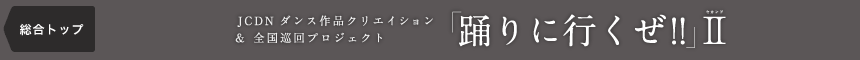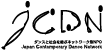「踊2」の主催者が推す理由―今年のAプロ3作品。
vol.4 東京、京都公演はAプログラム/ダンスプロダクションの3作品を上演します!
記:「踊2」プログラム・ディレクター 水野立子
1月より開始した「踊に行くぜ!!」2セカンド、巡回公演6か所のうち最後の2か所東京・京都公演は、Aプログラム/ダンスプロダクションより3作品を上演します。初めて本格的な作品制作となる森田淑子と、先駆的な活動を続けているダンス界の重鎮的存在の黒沢美香、日本では初制作ですが、N.Y.を拠点に常にその活動を注目されている余越保子、以上経験もタイプも違う3名の振付家が3つの作品を上演します。
で、その見どころを紹介したいと筆をとったわけですが、「報告するぜ!!」風にちょっと道草しつつレポートタッチで書いてみたいと思います。ここ数日試行錯誤しましたが、やはり短くまとまらないなあということがわかったので。
まずは制作裏話。皆さんもお気づきかと思いますが、今年の「踊2」Aプロが、過去3回と明らかに違うことがあります。いままでは初めて作品制作をする人がほとんどだったわけですが、今年は黒沢、余越さんというかなりの修羅場をくぐってきた振付家と、森田さんだけは初制作といっていいニューホープ。その結果、何が違ったかというと、だいたい夏から12月までが作品制作期間になるわけですが、例年は新人のAプロはまずグループの危機、崩壊というのがあるわけです。がっつりやる初めての作品制作ですから、いろいろ意思疎通の不和とかスケジュールの管理不足とか、演出家と他のメンバー間で問題多発します。そうなると作品制作が遅れに遅れ、徐々にパニックになり自爆するというパターンが多い。これは巡回公演中まで続くことも。まあそれに主催者も自ずと巻き込まれ、対応していくことになります。
が、今年はそういうことがゼロ、起きなかったですね。新人の森田チームも、初夏からダンサーだけのダンス・イン・レジデンスを行ったり、「報告するぜ!!」チームの第3者からの取材を通してのコミュニケーションの働きかけがあったり、メンバー内にドラマトゥルクが存在していたり、そういったことが、長期間の制作漬け状態になりプラスになったかもしれません。
ですので、どのチームも作品制作に集中していられた、ということがあります。途中経過発表のときは、各地の主催者からの感想や提案を粛々と受け止め、自らを淡々と追い込み制作にむかっていました。やはり落ち着いていました。当たり前といえばそうなんですが。
話を本題にもどして、今年のAプロのみどころです。今年の3作品は、「踊2」プロジェクトの掲げる作品制作の目的がみえてきた、近づいた年ではないか、と思っています。
というのは、そもそも「踊2」を始めた4年前の一番の思いは、本当に伝えたいこと、やりたいこと、みせたいことはこれなんだーというのが何もないのに、やってみました的なダンス作品は、NO MORE!おもろない!と。大きな社会的なテーマであろうが、個人的な私的なこだわりのテーマであろうが、なんか強烈にやりたい核があって作品をつくってほしいのだ!!という思いがありました。そして作家たるやそのことに自覚をもって、自らが手をあげるべきなのではないか、と。
また同様に、「ダンスでないとできない表現」としてダンス作品としてつくってほしい、ダンスそのものの動き、ムーブメントもなるほどという手法を発明してほしい、テクニックを並べるだけじゃなくて、と。<作品性、ダンスそのもの、ダンス作品である必然性>とまあ目的をぶち立てて公募開始したわけです。要望が多い、と思う方も多いかもしれません。が、ダンス公演を主催するものとして、本当に切実にそういうダンス、ダンス作品をみたいと切望しましたし、いまこれを始めないと、コンテンポラリーダンスとよばれているものは、見る人がいなくなるんじゃないか、という危機感を感じていました。
そのためには、ダンサーが集まって音楽かけて踊れば作品になるのではなく、作、振付、演出、美術と、必要なメンバーとつくるほうがいいわけです。でそういう制作環境をサポートしてなんとか、少しでもつくる人たちが時間を費やせるようにできないのか、ということで考えた仕組みが「踊2」の始まりだったのです。
3年間をふりかえるとやはり、<作品性、ダンスそのもの、ダンス作品である必然性>というバランスが偏ることが多かったように思います。よくあるのは、テーマがない、というと、やりたいことかどうかわからない何か、をつくってダンスで説明しようとしてしまうパターン。そうなるとダンスがどんどん逃げていってしまう。ダンスじゃなくてもいいじゃん、作品性も見えん、ということになってしまう。
さて、今年のこの3名の取り組みには、今までと違う共通する点があります。それは、3者ともに口を揃えて「ダンスでしかできないことなんです。」といいきることです。そうなんです、ダンスそのものを命がけで見つけようとしているところから作品制作が始まっています。
インタビューの言葉を拾ってみます。
余越さん「ダンサーが作品です。ダンスがどこにいくのか、作品がどうなるか、最初から私にもわかりません。今しか存在しないダンスだからこそZERO ONEが成り立つのです。」
森田さん「言葉のむこうにある言葉にならないことをダンスにする。」
黒沢さん「ダンスのために、ダンサーが踊らなくたって、ダンスというものは成り立つんだ、という問い。ダンスはいったい、どこに立ちあがってくるんだろう、誰に立ちあがってくるんだろう、という問いをミカヅキ会議が引き受けることになります。」

それぞれアプローチは違えども、ダンステクニックを見せつけるダンスではなく、誤魔化しのないダンスを成り立たせようする、必然のダンスを見ることができます。あるいは、それを見つけようとする手がかりがみてとれます。これまでの各地の巡回地では、これらの作品上演中、不思議と客席が集中力を持ち「じっ」とダンスを凝視していく空気が流れていました。今、この瞬間にしか立たないダンスが在る作品です。
そして、ここからがおもしろいとことなのですが、そうやって必然のダンスを探していくと、自ずと作品世界が表われてくるのです。身体があり、ダンスが生まれる、という舞台の中で、ストーリーやあらすじとは別のところで、表現が成立し作家の望む世界観が表れてくるということを改めてみた思いです。大野一雄や土方巽の舞踏が半世紀たったいまもなお、何故、多くの人々を惹きつけるダンスであるのか、という問いと、同じことなのかもしれない。ダンスという表現をどこまでも貪欲に追及し、そのダンスをつきつめると、世界が表れてくるということなのかもしれない。
「踊2」というプロジェクトが目指すところのダンス作品制作は、今まで参加してくれた作全アーティスト、各地の劇場、主催者のチェレンジングな
結晶でがぜん、おもしろくなってきた。作品制作の広がりを持てるかもしれない。
4年目を迎える今年の作品をしかっと観ていただきたい3作品です。
1月巡回公演の上演に立ち会い、わたしの作品への思いは下記です。
■黒沢美香 「渚の風―聞こえる編―」

鳥取公演 photo:中島伸二
ミカヅキ会議の舞台で踊り唄う必死な感じが、リアルに身体全体からこちら側まで伝わってくる。その不器用そうな際に立つ身体をみているうちに、いつのまにか、それがとてつもなく自由に見えてくる。本物だけで生きるっていいなあ、と嫉妬心が湧く。そう思わせるダンスがここには在る。
■森田淑子「ヤマナイ、ミミナリ」

札幌公演 photo:GO
本当に初めての本格的な作品制作となる森田さん。実は昨年大きな事故にあい1年伸ばしとなった制作。その経験も作品に影響をあたえた。言葉にできない感覚をダンスでしかできない表現として挑戦する。思い通りにならない身体、思い通りに伝えられない気持ち、すぐ隣にいる人に素直にコミュニケーションできない苛立ち、落胆と希望――誰もが当たり前に持つジレンマ。その痛い感覚を共感することはダンスだから可能なのかもしれない。そのダンスを複数の人と劇場でみること、同じ時間をすごすことで、人はまた生きる勇気を共有することにもなる。不器用にしか生きられない森田が、ダンス作品をつくることで、ぎりぎり外の世界と繋がろうとする姿は、どこか、自分をみているように思えるのは私だけではないはず。ここから、ダンスが立ち上がる瞬間に遭遇してもらいたい。
■余越保子 「ZERO ONE」

仙台公演 photo:越後谷出
文学や歌ではなく舞台作品として、これほど不条理の世界を表したものは見たことがない。今というこの同時代の不安や不安定さと、それを跳ね飛ばす力、ある種の開き直りパンク精神が混在する作品。双子のダンスと首つり状態で宙に浮いてはいるが、まぎれもなく生きている首くくり栲象の魂と体の写る映像――自己と他者、存在と不在が入れ替わり立ち代り舞台に現れて、舞台上の双子が自分に乗り移ってくるような錯覚におちいる。同じ容姿であるが、ダンサーとして別々の研鑽を積んできた二つの身体によって、繊細で強靭なダンスが不条理な世界を支える。