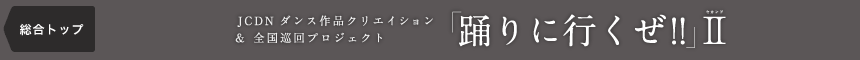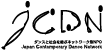隅地茉歩インタビュー[Bリージョナルダンス:札幌]
日頃から全国を飛びまわり、各地の身体に出会う機会の多い隅地茉歩さん。札幌の出演者を募るうえで掲げた「ダンス経験5年以上」という条件の理由。セレノグラフィカとしての活動そのものが土台となる新作『Avecアヴェク~とともに』のねらいとは。2日間のワークショップ・オーディションを終え、翌日からのクリエイションを控えた隅地さんに、今回目指している作品制作や出演者についてお話をうかがいました。

日時:2013年11月7日
場所:札幌市琴似
聞き手:プログラム・ディレクター 水野立子
―セレノグラフィカとしての活動のなかで
— 今回の「Avec アヴェク~とともに」という作品のアイデアというか、こういう事をやりたい、というのはいつ頃から考えていたんですか?
今年の初夏ぐらいからですね。「踊りに行くぜ!!」Ⅱに応募するにあたってどういうプランの作品をつくろうかなということを考えていました。
— 今、何作品目でしたっけ?数えた事ないですよね?
数えた事はないですけど、デュエットだけで数えても、まあ、ずっとデュエットで活動していますから、かなりの数つくってると思いますね。30とか、40とか。もっと超えているかもしれないです。
— ほとんどの場合は、隅地さんと阿比留さんが出演してるんですか?
これまでに数回、他のダンサーに振付けていますね。それは私たちが過去に踊ったものを、新しいダンサーが踊ってくれるという事でちょっとリメイクして。だからやっぱり私たちがつくって、自分たちで踊ってきた、という数が圧倒的に多いですね。
— となると、ちょっと今回は最初の入口から違いますね。
そうですね。しかも、どういうダンサーかという事を私があらかじめ分かっていて、ということではないので。その体験というのは、まあ初めてに近いです。
— そういう意味でいうと、セレノグラフィカは、地域・コミュニティの人に「ダンスを広める」というダンスの仕事がおそらく日本で1番多いと言ってよいほどのグループですよね。今回の「踊2」でのBプログラムと目的は違うけれども、今現在、年間を通してそういった仕事というのは7割ぐらいですか?
7割までいっているかな。でも、半分は超えてますよね。やっぱり初めて踊る方とか、これからダンスを知っていこうという方に、広めていくとか伝えていくという仕事は本当に多いので。まあそれは教育機関のアウトリーチ等も含めると、7割はいくでしょうね。ツアーで実際に遠征に出ている日数の比率とかで考えても、公演で踊るために行っているというのと、ワークショップとかアウトリーチを目的とした活動は比率的にも、やっぱり半分を超えてますからね。
— 1~2週間くらいかけて地域の人とつくるんですか?もっと長いですか?
いやいや、そんなに長いってことはないですよ。
— そこで向き合う人たちと一緒に作品をつくる、ということは大体1週間以内?
そうですね。長くて1週間ぐらいかな。ですので、今回はすごく長いと言えます。
— 今回のこの「踊2」AもBプログラムも共通して『作品をつくって下さい』というものだけれども、Bプログラムは初めて会う人とつくる、つまり隅地さんのことも知らない、セレノグラフィカのことも知らない、という人たちに自分のやりたい世界観を踊ってもらうという意味においては、「踊2」以外に既に経験があるほうですよね、すごく。
まあ、そうですね。
— その隅地さんが、今回特にこのBプログラムでやる、というのは、どこが違うんですか?
まず地域に滞在したりして、コミュニティの仕事をする時ってやっぱり、その良し悪しは別として、ダンス経験の浅い人とか初めての人というのが圧倒的に多いんですよね。でも今回私は“5年以上”活動しているダンサー或いは過去にダンス経験のある人という事を特に希望したんですよね。それのきっかけになった事というのをちょっとだけお話しても良いですか?
— はい、もちろん。
今年の1月に、それは地域創造の仕事だったんですけど北広島市(札幌)に行って、そこで毎晩平日にワークショップをして、最終的にそこでの公演に15分程出演していただくという事をしたんですけど、それがたまたま、ダンス経験のある人たちばっかりだったという、地域に滞在してそういう一般ワークショップに来てくださった方との作品づくりをする、というお顔ぶれの中では非常に珍しいケースだったんですよね。
それで、何も技術至上主義ということではないんだけれども、選択肢がすごく広がったんです 。作品づくりをする時にできることの。それが私にとってやっぱり発見であったし、喜びでもあったので、そういう事をもっと突き詰めてみたい!と思ったんです。その時はほとんどがバレエダンサーでしたね。
— それは偶然にですか?
偶然ですね。募集要項は「誰でも良い」としていたんですが、その時も、今回私がこのBプログラムに参加させていただくにあたって出した条件の「5年以上」というのを、ほぼ全員の方がクリアされていたと思うんですよね。たまたま。
— それでワークをやってみると、今までと違うものを感じた?
違うものを感じて、どっちが良くてどっちが悪い、という事ではないんですけど、ダンス経験がある人たちとの仕事もやってみたい、とすごく思いました。
— 静岡のセレノコンパーニョっていうのは、セレノグラフィカの振付作品を踊る、というコミュニティからできたダンスグループですね、彼らは違うの?
あの人たちは、多少メンバーが入れ替わり新陳代謝もあるんですけど、一人小さい頃からバレエをやっていたという女の子が在籍していたこともあります。大人になってから受けたW.S.でダンスと出会った人の方が多くて、昼間はお勤めで、夜に稽古に来る、ということをしています。そのことの良さももちろんあります。
— ということはその北広島でのことはまた全然違うケースとして触発されて、その中から今回ダンス経験のある人と一緒にやってみたいという発想につながったわけですね?
そうですね、ダンス経験者とやってみたいという事が浮かびました。なぜかというと、つくり手側と踊り手側でその持っているダンス感のようなものも交換できるんじゃないかなと思ったんですね。そういう事もお互いにすごく触発し合えるし。あとは、その人の出演するダンスを見てきている人たちに対して、その人たちが新しいダンスをするのを見てもらえるなーという事も思いましたね。
―男と女が1組になって踊るということ
—今回の「Avec」の作品の中身とかコメントとかを拝見すると、ある程度の年輪がある隅地さんだから考えられるテーマだな、という気もしたんですよ。ちなみに隅地さんは、もう作品つくって何年でしたっけ?30年ですか?
いやいや、そんななってないですよ(笑)私はまだカンパニー結成から16年ぐらいですからね。カンパニーを結成するまでは自分はダンサーとしてしか活動をしてなかったので、作品づくり歴っていうと、カンパニーの結成と全く同じ年数です。
— 今回の作品は阿比留さんと16年一緒にやってきたということ、その事がやはり大きな要素にもなってるんですよね?
そうですね。やっぱり活動体験の主軸がデュエットだったという事もあるので。なんかある時、ふと思ったんですよ。ダンスってどんなジャンルでも、バレエのパ・ド・ドゥでもそうだし、アイスダンスでも社交ダンスでもそうだし、男の人と女の人が一組になって踊るという形態っていうんですか、それがわりとどんなジャンルにもまたがって存在しているなーと。そしてそれは何なんだろう、と。自分にとっては、男一人 女一人で結成してやってきたので、デュエットで踊るということは私にとってはもう「既にあるもの」「そういう風にしてつくるもの」として存在していたんですけど、16年経ってそれをもう一回新しく、自分の知らない踊り手と「デュエットを踊るというのはどういうことなのかな?」と。ソロで踊るという事の次に1番小さな単位ですよね。まあそれは、よく言われていることですが。
デュエットという形態自体、そのこと自体を考察したいという熱というか、願いはありますね。実際つくる事を通して、踊ってくれている人の身体を見て考え直したいですね。もしかしたら、そういう人たちが踊ってくださる姿を見て、自分自身が「こう踊ってみたい!」という発見があるかもしれない、と思っているんですよ。そうすると今後、阿比留と私がつくるデュエット自体が変化する、という事もあるんじゃないかなと予感しています。
―「方言の身体」札幌には札幌の身体性がある
— 今回、セレノグラフィカとしてAプログラムに応募するのではなく、Bプログラムを選ばれた理由は何ですか?
Bプログラムを選んだ理由というのはあるんですよ。Bプログラムで作品創作をするということの方が、自分が創作しているいつものやり方というのを激変させられるんじゃないかと思ったんですよね。地域での作業の方が、これも誤解を招く発言になってしまうかもしれないんですけれど、一過性のものとして捉えられにくいんじゃないかという気がするんです。私は、ですけど。
— それってどういうことですか?
えっとね、お互いの印象形成の事なんですけど。私は彼女たちをよく知らないし。そして今回だったら札幌の人たちは関西じゃないから私たちが普段どういう活動をしていて、どういうことを喋ったり踊ったりしているかをご存知ない方も圧倒的に多いし。ということはお互いの印象形成がなく、つまり「セレノがこういう事するんだったら、おそらくこういう事よね」というような、あるぼんやりしたものであったとしても着地点の予想って多分たっていないと思うんですよ。出てくれる人にとっても。私たちも全く予想できないですよね。それに、地域滞在をさせて頂く方が、すごく集中して取り組めるんじゃないかと私が思ったということがまず一つあるんですよね。だから、作業自体がすごく純度の高いものになるんじゃないかと。
— それはどちらかというと隅地さんが、という事ですか?
私が、創作をするにあたってです。
— でもそこにはデメリットというか、リスクもありますよね?
もちろんありますね。だけど自分自身の振付家としての興味の中に、これも説明が必要なんですけど、『方言の身体』というんですかね。言葉がその地域ごとによって違うように、私は身体性というのもここ数年ずっと色んな地域に滞在させて頂いて仕事をするようになってから肌で感じている事なんですけど、地域によってやっぱり身体性が違うんですよね。子供の身体つきだって全然、子供の反応も違うし。そしてそういう事がおそらく子供だけじゃなくてもあるはずだと思っていて。そういうダンスにまつわる情報とか経験値のようなものがうんと高いとか、溢れている場所じゃないところにいる人の、身体の強度、とか起爆力みたいなものを引き出す仕事というのをやってみたい、と思ったんです。
— そういう事と『方言』というのはどうかかわりがあるんでしょうか?
つまりダンスをとっても、日本全国均一な標準語というのを話されていることはないだろう、と思ったわけですよね。だから札幌には札幌のダンスがあり、札幌には札幌のダンサーの身体性があり、という、そことかかわりたいと思ったわけです。
— それってすごく、専門的な探し物ですね。
まあ、そうですかねー。
— 例えばクラシックバレエとかモダンダンスとか日本舞踊って、別に札幌だろうが東京だろうが、やっぱりそれって変えちゃいけないものなんでしょう、きっと。イギリスと日本ではクラシックバレエが違うとか、そういうものじゃないですよね?
そう、違いますよ。その人たちがやっているクラシックバレエとかモダンダンスというのは当然、そんな大幅に勝手に変えたらいけないものだと思うんですけど、その“受容の仕方”というのは、地域によって絶対違うと思うんです。つまりクラシックバレエとかモダンダンスっていう、ある決まったメソッドをどういう風に受け取って、どういう風に自分の身体の中に入れて活かしていくのかというのは、その土地、土地の郷土料理が違うように、味付け方というのかな、食べ方というのかな。それが違うような気がするんですよ。それはあっちこっちに行って、色んな地域の身体を見るようになってから私が思ったことで、関西でしか活動していなかった頃には一切発想もしなかったことなんですよ。
— それを具体的に何かで感じたことはありますか?
同じワークをあるシンプルなルールでやっても、そのことに対する反応が違っていたりしますね。遅い早いとかいうような、単純なことも含めて。
— それって地域性になるのかな?
それが地域性だけだ、という風には特定できないと思いますけどね。だけど、どこに行ってもダンスが均一なものとしてつくり手が考えたり、扱ったりするという事に対して私は危険じゃないかと思うのです。そこの部分に対して、デリケートな視線や感覚が必要なんじゃないかなと。そうじゃないと地域滞在して仕事をする時に、私のやりたい事ってもちろん大事ですし、作家なので全責任をおいますし。なんだけども、私のやりたい事だけを一方的に押し付ける事になる、という考え方がやっぱり自分としてはどうなんだろうかと。
私のやりたい事が、この地域のこの人たちの身体にはどういう風に入っていくんだろう?という、そこにも興味があるんですよね。だから入っていき方によっては少し入れ方を変えたり、もっとこの事ではなくてこっちの方がいいかも、というような事を色々考えてやっていきたい。それを滞在してやる事によってものすごく集中してその作業ができるだろうと思っています。自分の家から通えるところでしているよりも、今回みたいに札幌に3回滞在して、がっつりその人たちと一緒の土地に泊まって、似たような物を食べて、という事がすごくいいなと思ってる。自分にとってやりたい事だったんですね。
―2日間のWSオーディションを終えて
— 実際にオーディションを2日間やってみてどうでしたか?手ごたえやインスピレーション、この人とやってみたい、というような事はありましたか?
そうですね。最初の日は繊細さだとか素直さとか、そもそもの身体のきめの細かさだったり粗さだったりを見せてもらったんですけれど、2日目には自分自身で考えてきてもらったソロダンスを見て、私は「あーやっぱり勘の悪い人って一人もいないんだな」って思ったんですね。それに感激しました。やっぱりその人それぞれに、ダンスと付き合う時間をちゃんと重ねてきた人たちが集まって下さったんだな、とすごく嬉しく思いました。
「あ、これは!」と思ったのは、中学生と高校生の若い人たちが興味をもって来てくれて、あれだけ堂々と自分の踊りを見せてくれたという事には、すごく心動かされましたね。今回は創作のスタート地点に、自分たちのレパートリーとして持っている5分間の短いソロを、世代の違うそれぞれの男女のペアに踊ってもらうというところからスタートしようと思っていたのですが、それをもう既にオーディションの時点で取っ掛かりまで行けたので。早いですよね。
— そうですね。1日目に出した宿題を見ても、皆さん、ちゃんと形にしてきたもんね。
形にね。だってあれって、前の晩の22時ぐらいに言って、次の日にはお勤めがあったり学校に行ったりしていて、1日中時間をリハーサルに使えたわけではないだろうなと思うとすごいです。
— 3つのルールのある宿題って何でしたっけ?
あれもね、限定付けてよかったなと思うんですけど。ストライドといって全体を大きく左右を使って移動するという事が1点と、私がつくった短い振付を使うというのと、スタンディングで即興してもらい自分が立った地点から動かずに何かを表現するという、その3点を入れてくださいという風にお願いしました。あのオーダーは出してよかったと思っています。完全にフリーで、という事ではなくて。
— その3つを組み合わせてきたけど、皆さん達者でしたね。
達者でしたね!!皆、音楽をよく聴いているなと思いました。もうその中には、音を身体の中に通すということを知っている人もいるし、この決まっているモティーフでも、1番が終わって2番が始まって初めて座ったかたちで踊ってみるという事をしてくれた人がいて。ちょっとこちらが唸り声をあげたくなるような瞬間がいくつもいくつもありましたね。
— 今回の「Avec」という作品では、振付は1から10まで隅地さんがするんですか?それとも今回のオーディションみたいに、課題を与えて自分で振付するという部分もあるんですか?
そういう部分もつくろうと思ってます。それでその人が持っているバックグラウンドというか、その人の踊りの現在そのものですよね、そういうものがちゃんと振付に入っている方が良いと思いますね。私が「こういう風に動いてくれないと嫌なんです」という事が全部というのではなくて。洋服が増えるというか。自分は普段こういうものを着ているけれども、これが好きで、身体にも馴染んでいるのだけれども、今まで自分が着たこともなかったこういうものを羽織ってみた時に、結構これはこれで気に入るもので、次どこかに出掛ける時には着てみよう、と思ってもらえるような“お気に入りの洋服”を増やしてもらえたらなと思うんです。ちょっと比喩的で恐縮なんですけど。ダンサーにとってはそういった体験にしてもらいたいなと思います。
だから、彼ら彼女らがこれまでやってきた事を否定はしないんです。そこにある種の狭さがあったり、硬さがあったり。それはもちろん鍛錬の中で様式を体現していること。だけれども 別のことを知ることによって同じ事を踊っても、これまでやってきた事と同じことを仮にバレエなりをしたとしても、ガラッと変わるといった体験になるようにしたいですね。せっかくするんですから、そこは目指しています。
―「Avec アヴェク~とともに」の狙い
— 今回の世界観というか作品性として、どういったものをお客さんに渡したいと思いますか?
作品性としては、「男と女が踊る」という事に対して持っているある種のイメージ、男女のペアであったり、つがいであったりという事があると思うんですけど、その身体そのものを変えてしまうわけにはいかないですが、男と女が一緒に踊るという事が「こんな風に見えるんだろうか!」「あんな風に見えるんだろうか!」という驚きを持ってほしい。というのと、「一体どういう二人組?」と簡単にはその関係性が認識できないような、「あ、この二人はこういうような二人組で、こういうような関係性なのね。オッケーオッケー。」という風にならないようにしたいですね。そういうのを、ちょっと複雑に組み合わせてみたいと思っているので。だから最初はこの人とこの人がペアかな、とスタートした事がどんどん変わっていって、作品の終盤にはあるペアが出てきても、最初に持ったイメージと全く変わってしまうという事を作業としてやっていきたいと思っています。あまり関係性は固定せずに、その辺は組み合わせて細切れというか、複雑にしてみたいなと思います。
今回出演者を募集するにあたって、これは私が常々願っていることではあるんですけど、なかなか踊り手が長い期間同じものを踊り継いでゆくとか、何十回、何百回と踊るという事はあまりないので、その人にとって何かの時に「これを踊ります」と言えるようなレパートリーになれば良いと思うんです。それと、見る人から「あれはまた見たい」とリクエストがかかるようなものになってほしいですね。
というのは何となく作品って、新作でやって、もちろん何回か上演もその後経る事が出来るって言ったらそれはすごくラッキーな事だと、実際この世界に住んでいて思うんですけど。そういう事がもっと増えれば良いだろうなーと思っていて、それの為にはあんまりフルレングスで用意が大変なものではなくて、ちょっとコンパクトになっていて、作品の中からデュエットの部分だけ、そこのユニットだけ抜き出して、ちょっとどこかで踊れるというような、そういう事も狙いとしてはあります。
— お話を伺っていると、隅地さんというよりダンサー寄りな目線は結構ありますね。
そうですね。やっぱりこうやってオーディションをして、そこに興味を持って来てもらって、実際対面してお話して踊りも見せてもらって「この人を作品のパートナーにしよう」と決めるわけですから。その人と創作の期間が終わってもね、どういう付き合いが出来るのかとか。その人に対してどういう影響を残せるのかという事には責任があると思っていて、そういう事を考えていますね。
— この「Avec」という作品についてのコメントを読むと、人生観というか、色々な人の生き様というか、見た人が自分のことをふと考えてしまうというような、作品になるのかなという感じがしましたが。
それはそうしてほしいです。
— そういう意味では、今回若い子達が出ますよね。そこをどう見せるのかというところに興味がありますね。自分の過去を辿るともちろん中学生だった頃もあって、でもその子たちには未来でもあるわけだしね。
そうですね。まだだいぶ若いですからね。子供がいたとしたら、自分の子供よりも若いですよね。孫とまではいかないですけどね。
— そういう年代の人たちとは、制作を普段からやってますか?
私はあの年代の特定の人に振付ける、というのは初めてです。多人数いて、こういう事をやってみましょうとか、ワークショップの成果公演みたいなのはもちろんありますけど。でもこの子とこの子、と決めている子に対して時間をかけて向き合って、というのは初めてです。だからすごく楽しみですね。自分自身が変わるだろうなっていう予感はしています。
— なるほど、お話しを伺っていると、この作品制作をとおして、振付家本人の隅地さんにとって、たくさんの期待があるようですね。ありがとうございました。明日からの制作が楽しみですね。