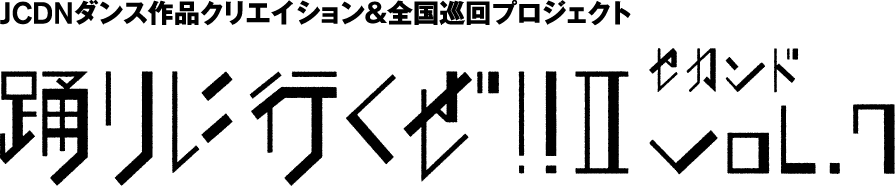2017年02月23日
全国巡回公演札幌・仙台・福岡での上演を終えたAプログラム3作品。
残すところ東京・京都公演のみとなりました。
上演を終えた開催地で、3作品に寄せられたコメント・談話などをご紹介します!
最終公演東京・京都をどうぞお見逃しなく!
THE RELIGION OF BIRDS
黒田育世(東京)
photo:Echigoya Izuru 仙台公演
■三上満良/宮城県美術館副館長
ダンサーたちは、仏の化身である鳥の、そのまた化身。肉体と魂をめぐる問いは、宗教の始原であると同時に、ダンスという芸術の根源的テーマでもあることを再認識させられたステージだった。「無常」を語るプリミティヴな仏教説話の表現に、今日的なジェンダリズムのメッセージも感じたのだが、深読みしすぎだろうか。
■小森はるか/映像作家
まるで重力を持たない身体のような、柔らかな動きの連鎖に圧倒されながらも、時折地面を力強く踏みつける、あの振動音が心に残った。黒田さんが編み出す幻想的な世界に見えていたが、そうではなく、いまここに生身の身体があるのだと、観客の頬を叩くような、そんな仕草に感じた。
まるで重力を持たない身体のような、柔らかな動きの連鎖に圧倒されながらも、時折地面を力強く踏みつける、あの振動音が心に残った。黒田さんが編み出す幻想的な世界に見えていたが、そうではなく、いまここに生身の身体があるのだと、観客の頬を叩くような、そんな仕草に感じた。
■細谷修/美術・メディア研究者
喜び、悲しみ、憎しみ、そして容赦ない変身の狂気。黒田育世による息もつけない身体への集中は、同時に、言葉ならざるものへの挑戦とも言えよう。集団の身体は、我々に踊りの「場所」の意味を幾度となく問いかけてくる。
■長内綾子/キュレーター、Survivart代表
チベットで古くから読み継がれてきたという仏典=物語を踊りへと昇華した本作。これまでBATIKや黒田の作品に触れたことのある者にとっては、予想を一蹴するかのような、自然のたおやかさと摂理がほがらかに表現されていた。と、同時に、ここは死者の世界なのかもしれないと強く感じる公演だった。
■曽和聖太郎/映画作家
(仙台公演レポートより抜粋)
啼き声が紡ぐ音の立体曼荼羅に纏い付くように奏でられる、松本じろによる鼻歌とも童謡ともつかぬアルカイックな調べを聴いていると、北上川を遡って、ある一人の作家を召喚したい衝動を覚えずにはいられない。宮沢賢治である。
すでに原典のある作品に重ねて他の作家を引いてくることが無粋であることは承知しているし、作り手たちが意識していることとも思われないが、彼女たちの舞踊を見ていると例えば「ざあざあ吹いてゐた風が、だんだん人のことばにきこえ、やがてそれは、いま北上の山の方や、野原に行はれてゐた鹿踊りの、ほんたうの精神を語りました。」(「鹿踊りのはじまり」宮沢賢治)というような一文を思い出さずにはおられないのだ。賢治もまた仏教説話としての童話を多く書いた作家であった。
喜び、悲しみ、憎しみ、そして容赦ない変身の狂気。黒田育世による息もつけない身体への集中は、同時に、言葉ならざるものへの挑戦とも言えよう。集団の身体は、我々に踊りの「場所」の意味を幾度となく問いかけてくる。
■澁谷浩次/ミュージシャン、喫茶ホルン店主
向かい合った女たちが霊性を全開にして、花びらのような仕草で迎え合う断固とした場面を観るだけで、これが来たるべき死と誕生についてのドラスティックな物語であることを覚悟しなければならない。顔を覆い、裸の胸を晒す荒々しさ・酷薄さは、このダンスで取り扱われている数々の議論を強化している。
■長内綾子/キュレーター、Survivart代表
チベットで古くから読み継がれてきたという仏典=物語を踊りへと昇華した本作。これまでBATIKや黒田の作品に触れたことのある者にとっては、予想を一蹴するかのような、自然のたおやかさと摂理がほがらかに表現されていた。と、同時に、ここは死者の世界なのかもしれないと強く感じる公演だった。
■曽和聖太郎/映画作家
(仙台公演レポートより抜粋)
啼き声が紡ぐ音の立体曼荼羅に纏い付くように奏でられる、松本じろによる鼻歌とも童謡ともつかぬアルカイックな調べを聴いていると、北上川を遡って、ある一人の作家を召喚したい衝動を覚えずにはいられない。宮沢賢治である。
すでに原典のある作品に重ねて他の作家を引いてくることが無粋であることは承知しているし、作り手たちが意識していることとも思われないが、彼女たちの舞踊を見ていると例えば「ざあざあ吹いてゐた風が、だんだん人のことばにきこえ、やがてそれは、いま北上の山の方や、野原に行はれてゐた鹿踊りの、ほんたうの精神を語りました。」(「鹿踊りのはじまり」宮沢賢治)というような一文を思い出さずにはおられないのだ。賢治もまた仏教説話としての童話を多く書いた作家であった。
■瀬尾夏美/画家、作家
うつくしいものをうつくしいと言おうとするとき、 私はそれを取り巻くものの複雑さに蹴つまずいてしまう。さて、 このダンスはうつくしいだろうか。私には、分からない。けれど、 あなたたちはきっと、それを信じている。ことばの応酬の先に、 その意味の果てに、その指先がすっくと触れた瞬間、——その目撃。このダンスはきっと、うつくしいのだ。
■松崎なつひ/宮城県美術館学芸員
女たちが笑みを浮かべ、せっせと何かの儀式?をしている。それを観ているときの、何ともいえない居心地の悪さは、何だろう?今回の三つの演目の中で一番「わからない」作品だった。だからこそ、一生懸命に考えながら見た。終わった後もずっと考え続けていられることも、その作品の一つの楽しみ方だと思う。
女たちが笑みを浮かべ、せっせと何かの儀式?をしている。それを観ているときの、何ともいえない居心地の悪さは、何だろう?今回の三つの演目の中で一番「わからない」作品だった。だからこそ、一生懸命に考えながら見た。終わった後もずっと考え続けていられることも、その作品の一つの楽しみ方だと思う。
■佐々木治己/劇作家
(仙台公演レポートより抜粋)
ある種の物語を感じた。その物語とは、生老病死や、天人五衰のような物語で、生や死が辿る滅びと再生の物語と言えばいいのだろうか。
立ち現れては消えていくダンサーに輪廻転生を思うというとなんだが出来過ぎな感想になってしまうが、舞台上の物事が何かの化身のように思えてくる。様々な身振りや小道具による状態の変化も、解釈しかねている事象をあらわにしているようだ。絵解きなどのように、この舞台を解いていくことで、生命の在り様が見えてくるのではないか? そんな気にさせる舞台だった。
(仙台公演レポートより抜粋)
ある種の物語を感じた。その物語とは、生老病死や、天人五衰のような物語で、生や死が辿る滅びと再生の物語と言えばいいのだろうか。
立ち現れては消えていくダンサーに輪廻転生を思うというとなんだが出来過ぎな感想になってしまうが、舞台上の物事が何かの化身のように思えてくる。様々な身振りや小道具による状態の変化も、解釈しかねている事象をあらわにしているようだ。絵解きなどのように、この舞台を解いていくことで、生命の在り様が見えてくるのではないか? そんな気にさせる舞台だった。
■水野立子/「踊2」プログラム・ディレクター
「SIDE B」での鮮烈なデビューが記憶に蘇るBATIKの活動は、早15年になるという。
その歳月を重ねてきたからなのだろう、説明したり表現しようとは決してしないダンスだけれど、カンパニー独特の説得力と確かさ、メッセージ性のあるダンスが立ち現れる。
今回の新作は、原作をダンスという鍵をつかって紐解き結び直し、身体表現としての言語をダンサーが探しあてるという緻密な作業を積み上げていく。舞台に絵巻物を広げるように、鳥たちが次々と人間界や自然界の混沌と摂理を優しく荒らしく語り見せてくれる。
確かに、黒田さんが大切にしている“知的に分析しないこと”でしか、本当に大事な真実には近づけないように思えてくる。「それは秘密なの」と言いたげな立てた人差し指が、地球儀を回すように、世界の局面と時間を回しているのかな。ダンス作品に流れる“思想”のようなものが伝わってくる作品。
「SIDE B」での鮮烈なデビューが記憶に蘇るBATIKの活動は、早15年になるという。
その歳月を重ねてきたからなのだろう、説明したり表現しようとは決してしないダンスだけれど、カンパニー独特の説得力と確かさ、メッセージ性のあるダンスが立ち現れる。
今回の新作は、原作をダンスという鍵をつかって紐解き結び直し、身体表現としての言語をダンサーが探しあてるという緻密な作業を積み上げていく。舞台に絵巻物を広げるように、鳥たちが次々と人間界や自然界の混沌と摂理を優しく荒らしく語り見せてくれる。
確かに、黒田さんが大切にしている“知的に分析しないこと”でしか、本当に大事な真実には近づけないように思えてくる。「それは秘密なの」と言いたげな立てた人差し指が、地球儀を回すように、世界の局面と時間を回しているのかな。ダンス作品に流れる“思想”のようなものが伝わってくる作品。