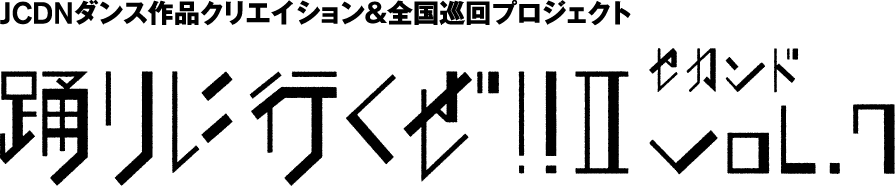2017年01月12日
「珍しいキノコ舞踊団」ポップで奇抜なセンスを持って、ダンス界をリードしてきたパイオニア。主宰にして振付家の伊藤千枝さんを迎えるにあたって、色や造形の切り口から話が聞けると面白いのでは?そんな考えが頭に浮かんだ。
札幌でポップな感覚を持っているアーティストといえば、さっぽろアートステージなど様々なシーンで活躍中の美術家、高橋喜代史さん。
コンカリーニョとの繋がりも深く、過去に演劇祭の審査員も務めてもらっている。この企画には“うってつけ”のアーティストだ。
さっそく相談を持ちかけると、二つ返事で快諾をもらった。
舞台装置や色彩のセンスに非常に興味があったとのこと。
舞台作品と美術作品――遠いようで近い2つのジャンルの二人が出会うことで、どんな話が聞けるのか、期待の組み合わせに心が躍った。
伊藤千枝さんのクリエイションは、まさに「創造」といえるだろう。
出演者から出てくるもの、今までに見たことのないものを探し求めるスタイルだと感じた。
それは9月に行われたオーディションでも垣間見ることができた。参加者にイメージを伝え、そして感じ取られたものを、身体の動きで表現する力を見ていたように思えた。
11月のクリエイションでは、出演者3名のうち、1名が事情により止むなく降板することになった。当初の構想からの方向転換、そして新しく作品として生み出していくため、伊藤千枝さんの思考の量は膨大だったのではないだろうか。しかし、2人になった出演者と共に模索し、思考し、試行を重ねる課程は、生まれる作品が面白いものになるだろうという予感を与えてくれた。
二人のインタビューを聞いて、改めて「創造」される作品の事が楽しみになったことは間違いない。
ポストモダン
高校生が愛だの死だの言われてもですね(笑)
高橋:最初にダンスとかパフォーマンスを始めたとか、これやりたいと思ったきっかけってどこからでしょうか。
伊藤:ダンス始めたのが4歳のとき。おんなじ幼稚園で仲良かった子がダンス習いに行くんで、一人で行くのがなんかさびしいから、チエちゃん一緒に行こうよって言われて(笑)
高橋:バレエですか?
伊藤:モダンダンスっていうやつなんですよね。コンテンポラリーダンスの前にあったやつです。厳密に言うと色々あるんですけれど、クラシックバレエ、モダンダンス、で、ポストモダンダンス、みたいな、現代美術と同じです。
高橋:同じですね。
伊藤:現代美術の流れを追っかけてるんですよ、ダンスって。ちょっと遅れてダンスにそういうのがやってくる感じ。私たちがダンスを作り始めたころっていうのが、ポストモダンダンスなんですよね。自分が習っていたモダンダンスは、物語を抽象的に語ったりとか、愛だとか死だとか、そういう大きなテーマを捉えて作品を作っていた。稽古場の先生がそういうのを作るわけですが、高校生が愛だの死だの言われてもですね(笑)。イメージが全くつかなくて、あまりにもかけ離れてる感じ。そこにポストモダンダンスっていうものがポンって出てきた。意味性を完全に排除した動きだけで何かを語るだとか、アンディ・ウォーホルとかもその辺なんですけど。面白いムーブメントがダンスの方でも、起き始めた。それがポストモダンダンスだった。アメリカ中心にこういろいろ起きて来た感があって、日本でも、お亡くなりになったのですが、黒沢美香さんとか、そういう方々が、そういう事をやってらしたんですよね。私が高校生の時に観たんです。すごい衝撃を受けて、なんじゃこりゃーってなった。こんな面白い事、なになになに?!みたいな。頭パニックで、すごいカルチャーショック。自分でもなんか作ってみたいという欲はすごい結構あったんですけど、どうしていいかわからなかった。そんなときに黒沢美香さんのダンスをみて、あ、何やってもいいんだ、見たいな感じに思っちゃったんです。
モダンダンスってやっぱり確固たるものを自分が持ってたんで、それにちょっと行き詰ってたんですよね。愛とか死とか言われてもわかんないし、これじゃない表現をやりたい、みたいな。そう思ってた時に、アンチテーゼを私の目の前に提示してくれて、表現がこうボォンって目の前に、しかもそれがこっちだよーじゃなくて、あれもこれも、みたいないろんな方法でやってるものをワーって見せてくれたんで、やばかったですよ、だから変な高校生でした(笑)。
高橋:高校生だとそういう情報ってどうやって手に入れてたんですか?
伊藤:ダンスの稽古場にそういう情報を収集するのに長けてるお兄ちゃんがいたんですよ。
あと、「ぴあ」ですね、雑誌のぴあ。
高橋:へぇー。
伊藤:片っ端からだから行ってましたね。だからなんかのビデオ上映会っていって、あ、これきっとダンスだと思って行っても、全く意味わからない現代映画だったりしたこともありました。あっ、ダンスじゃなかったーっていうのもありましたけど。振付って書いてあるものは、これはきっとダンスだっていう、そういう情報の収集の仕方ですよね。
高橋:すごい高校生ですね。
珍しいキノコ舞踊団
ダンスだけどダンスじゃないこといっぱいやりたいよね
高橋:結成されるんですよね。
伊藤:はい。自分で作品を作りたくて、大学選んで入ったっていう感じでした。すごいもう、下心バリバリで、その大学に入れば照明さんも音響さんも、舞台美術もみんないるっていう。日芸(日本大学芸術学部)なんですけど、全部いるから友達になって頼めばお金かからないっていう。
高橋:どういう学科なんですか?
伊藤:舞台照明、舞台美術、舞台監督とか、舞台の製作をするっていう、一応全部コースが分かれてて。私は、その中の「西洋舞踊コース」に入ったんです。受験の時に、「私はダンスを作りたいからカンパニーを作りたいんだよね」って言ったんですよ。そうしたら、「あ、あたしも、そういうつもりで来てるよ」みたいなのが一人いて、じゃあ受かったらさ絶対一緒にやろう、って。大学に入ったら、その人も受かってて、「おお!受かってるねぇ!じゃあやろう!」って言う感じだったんですよね。で、いまだに一緒にやってます(笑)。
太田:運命ですね。
高橋:ちょっと鳥肌。
伊藤:ほんとですか(笑)。途中から、彼女は作るのやめて、演出助手っていうことになった。
やっぱり大学でも私、大分変わってたらしくて(笑)。
高橋:はいはいはい、でしょうね。
伊藤:その当時は、一人で作れる自信がなかったんですよね。自分にその力がまだないだろうと思ったんで、それで一緒に作る人を探してたって感じなんですよ。一時間の作品を一緒に作りたい人って言ったら、もう一人手を挙げたのがいて、三人で振付・演出したんです。ダンサーが必要だったんで、また声掛けたら二人手挙げてくれた。その二人入れて、最初五人でやって。とにかくやりたいことをただやる、っていうだけの作品が最初一回目。「ダンスだけどダンスじゃないこといっぱいやりたいよね」みたいな感じ。役者さんを連れてきてグレープフルーツをずっと食べてるだけのシーンとか、ですね(笑)。人が一生懸命踊ってるのにその横で、ドラえもんクイズ!とか言ってドラえもんのクイズをずっと読んでる人がいるとか(笑)。暗転して、暗転明けたら、なんか意味わかんないんだけど、ヅラをかぶった人が袖からジャーッって滑って腹這いで出てくるとか。そういうアイディアばっかり。それをどう踊りで繋げるかみたいな(笑)。
高橋:それを面白いとする、その基準ってなんですか?
伊藤:みんなで、げらげら笑うっていうそれだけです。ただそれだけです。
高橋:(笑)
伊藤:その頃、竹中直人さんとかテレビでやってたりとかしてて、そういうのがすごい好きだったんですよね。ナンセンスでシュールなギャグ。げらげら笑う感じをただただやってた。そういう事をやりつつも舞台美術がないといけないっていう頭もあって、舞台美術コースにいる子に頼んで、謎の舞台装置を作ってもらったりとかですね。全く作品に関係ない、ロープをぐるぐる首つりみたいになってるのが上から垂れ下がってる。その下で、ドラえもんクイーズ!!とかやってたんで相当シュールだったと思いますけど。
高橋:周りの評判は?
伊藤:そんなに悪くなかったですよ。悪くないんですけど、踊っててもみんなドラえもんクイズの答え考えちゃう(笑)。
伊藤:それで、踊りを見てもらえないっていうことに気がついて(笑)。これちょっと考えた方がいいぞみたいなことになりました(笑)。
第一回の時には、ちゃんとそれぞれ一人四万円くらい持って劇場借りに行ったんですよ。団体名が必要だったんで、「珍しいキノコ舞踊団」ってつけた。マネージャーっていうか制作さんって団体には必要で、日芸ってお芝居の団体がいっぱいあったんです。そこには必ず制作がいたんで、私たちにも制作付けようってなった。大学のロビーみたいなところでダラダラしてる人がいてですね、「あいつ、頼むと何でもやってくれるよ」って聞いた。「今度こういうのやるんだけど制作やってくんない?」って聞いたら、「あぁ、いいよ」みたいな感じ。それが今もずっと制作やってるんですけど。
太田:そうなんですね。
伊藤:その人が、今度こういうオーディションがあるから出てみたら、ってオーディションって言うかコンペティションですよね。演劇のコンペだったんですけど、面白いから出してみようか、って。そしたら半分だけ受かった(笑)。全部受かるほどの実力はないけど、半分受かるぐらいの力はあるんじゃね?みたい感じ。
太田:落とすのは惜しいけど、形は面白い、みたいなことですね。
伊藤:そうそう。全部受かる程じゃない、みたいな感じの事が起きてですね。そこで公演が出来たんですよ。それが渋谷の一等地で、今はもうないんですけど、パルコがあるらへんの、ちょっとしたギャラリーというかフリースペースで。入場料が確かタダだったと思うんですけど、だれでも見れる場所でやったんですよね。
高橋:面白いですね。
伊藤:それがきっかけになって、いろんな人の目に触れることになり。それが大学の3年生ぐらいだったかな。
![]()
気持ちが動く
ドラマが起きているってのは、その場で、
リアルに何かを感じて、過ごしていること
高橋:すごく聞きたいところなんですけど、演劇的な要素とかをちょっと感じるんですよ。演劇とダンス、どのように意識しているんですか?
伊藤:今、すごい質問してもらいましたね、すごい不思議ですね(笑)。今まさに今回の出演者とこのことについて話し合ってる、というか作業してるところでして。元々は物語性とかを否定したポストモダンダンスってかっこいいってやってたんです。なのに、ストーリーって言うよりドラマが欲しいなって思ったんです。私の中で違う種類のものな気がして。ドラマってすごい大事なんだなーって思って。
太田:美術にはあんまりドラマはないですもんね。
高橋:感覚的にドラマティックな人ももちろんいますけどね。まあ、映像作家だといますけど、やっぱあんまりいないですよね。
太田:ドラマ性みたいなのが。
伊藤:体験とか、実感ってことなんですかね。ドラマって。なんか、ストーリーっていうともう、台本脚本っていう感じになっちゃうんですけど。
太田:厳密には違うものですよね、ストーリーとドラマ。感覚的なものですけど。
高橋:感覚的なんですか?
伊藤:よく舞台で起きてることは虚構で、全部ウソじゃんと。本当のことじゃないだろっていう、まあ議論でよくあると思うんですけど、確かに、台本とか脚本の再現をするって意味では嘘かも知れない。舞台にお家はないし、街はない。でも、そこで感じるって言う事が起きるわけじゃないですか。たとえば風が吹く音がしてるってなると、そのほんとにガアァァって猛吹雪の中に自分がいるって感じる瞬間ってあると思うんです。それが、私にとってはリアルだし、私にとってのドラマってそういう事なんじゃないかなって。だからドラマが起きないってのは、何も感じていない状況であって、ドラマが起きているってのは、その場で、リアルに何かを感じて、過ごしていること。なので、舞台はウソっぱちでしょうっていう人と話をしてると、すごく悲しいというか、さびしいよねーっていう気分になってきちゃうんですよね。
高橋:感情とか感覚の起伏みたいなのがあると思うんですけど、何も感じていない、って言うのはあんまりなくて、微弱ながらわずかにちょっと感じていると思うんです。でもドラマって聞くと「ドラマティック」みたいな言葉もあるから、その振れ幅が急に上がる。
伊藤:私って結構オーバーアクションなんですよ。おいしいごはん食べたりとかすると、フウゥゥォ!おいしい!マジ美味くね!?みたいな感じになっちゃう。
高橋:へぇぇぇー
伊藤:自分がこう感動したものに対してのアクションが大きい。感動する、感じる、という触手みたいなものが、結構な人たちがそれが鈍くなってるのかも。ちょっとした違いを敏感に感じ取れるかどうか。それがその人の感覚なんじゃないのかなと思うんですよね。表現者としてはその部分を活発にしておく必要がある。しておかなければならないんじゃないか。だから何を食べても、んーって感じの人は、その人が舞台でなにかやっても、見てる人がその人をみて感動出来るのかしらって思ってしまう。感動するってのは気持ちが動くっていう意味の感動なんですけどね。感情が動く。演じてる人の感情が動いていない限り、見てる人の感情は動かない。表現者は少なくともそこがないといかんだろうと思ってるんですよ。
高橋:おもしろいですね。
伊藤:伝えるってことですね。純粋に。見せるんじゃなくて、自分がある種の媒介者のような、もう媒介者になって、今自分に起きてることを、見てる人に伝える。
高橋:伝えたいことってあるんですか?
伊藤:それが、多分その「感動」なんだと思うんですよね。だからカレーライス食べて、おいしい!って。やっぱそれは伝えたくなるじゃないですか、人にそのおいしさを。
高橋:共有したくなりますよね。
伊藤:踊るってことが本当に楽しくてしょうがないので、自分がやってる行為が、楽しいぞーっていうのを伝えたい、って思ってしまうんです。一緒に踊ってる人と、ビビッって、はまった時に、なんかこの感じすごくない!?みたいなことだったり。だから何か具体的にこの事を伝えたいとか、このストーリーを伝えたいとか、このテーマを伝えたいとかは、一切無かったんですよ。9月の時は。
高橋:うん。
伊藤:音楽をかけて、五名くらいで即興のダンスを踊ったりすると、ものすごい楽しくて、やってる方も興奮してきちゃったんですよね。もう、やばいやばいやばい!みたいな。お客さんを見たら、さざ波のように笑顔で、、見ている人が全員がウワァーって笑顔になってくんですよ、バアァーって。30分間即興ダンスやったんですけど、その30分即興やるっていうのが結構なチャレンジだったんです。そこに向けてのリハーサルを結構やったんですよ。即興のリハやるっていう。
高橋:それってどういうことなんですか。
伊藤:意味はわかんないんですけど、ただその時間を共有するとか、舞踏に近い感覚なんだと思うんです。日本人的な感覚で、何かを感じるとか、なんかそういうことを延々やってましたね。その渦みたいなのをやり終わって、また強く思い始めたっていう感じありますね。なんかすごい舞踏的な発想してたんじゃないのかなぁって。
身体に起きていく
整体に行くよりも大野慶人
伊藤:360度感覚を、ほぁぁぁん!って目覚めさせるというか。うーん、感覚?身体感覚?脳みそも通ってるんだけどね。頭でジャッジしないって感じですかね。なんていったらいいの?
太田:どうなんでしょうね。
伊藤:何にも考えてないんだけど、そういう時って、ハエが飛んでたらバンッってハエがつかめたりするんですよ。私、昔あったんだけど、本番近くなって、全く何にも考えないでしゃべってるときに、あーなんか飛んできた、って。何にも考えてないで、バンってやっちゃったんですよ。ワーと思ってみたら、ハエ掴んでて、ぁあぁあぁ~、っていうことあったんだけど、そのぐらいなんか出来ちゃう。
太田:宮本武蔵ですね。
高橋:すごいなぁ、それもう。
伊藤:Bプログラムの出演者にやってもらったりしてるけど、触ったり触らなかったりしながら、いろいろ動いていく。9月は5人でやったんだけど、まわりに、人が集まってきちゃって。練習なのに。野外だったんで、外でやってたんですけどね。ぶつからないでやるんです。フワッと足が通ったりするんだけど、足が通るのがわかるから避けられる。向こうもわかるんですよ。避けるなってわかる。お互いにわかってる。だからずーっと延々とできるんです。
太田:そうなんですね。これは言葉にはなってないんでしょうね(笑)
高橋:そうですよね。理屈じゃないですもんね。
伊藤:どうやったらそういう感覚が目覚めるのか、目覚めさせることが出来るか、っていうのをずっとやり続けてる。
太田:重心とかから、無意識に拾ってるわけではないんでしょうかね。
伊藤:2、3年ぐらい前に、大野慶人さんっていう大野一雄先生の息子さんに作品を作ってもらったことがあって、私は慶人さんが大好きで、慶人さんのワークショップを、すごい集中して受けさせてもらったりもした。その頃に培った感覚っていうのも多くて。もともとそういうの、求めてたんですよね。慶人さんと出会って、これちょっと欲しいと思ってた感覚かもって、ワークショップ受けたりとかした。そこでまた目覚める感覚っていうのがすごくあった。舞踏的な、まあだから本当に、いろんな種類ありますけど本当に。大野慶人先生からの身体感覚、感覚の捉え方っていうのが、近いものがあるかもしれないですね。冷たい!って思う感覚って、すごく大事だって言って、稽古場にバケツがあって、ほんとに水が入ってるんですよ。そこに手入れるんですよ。真冬に。冷たぁい!ってなるじゃないですか。何度も入れて、出して。そのまんまの身体感覚で歩いて、って、言われた。リアルに全部事が起きていく、っていう。重い物を持って歩いて、降ろしたときの重い物の感覚。この身体感覚で歩けよぉ、みたいなことをやったり。抽象的でなく、ものすごく具体的に身体に訴えかけてやってくれるので、すっごくわかりやすく、いろんなことが身体に起きてくんですよねぇ。
高橋:おもしろいですね。
伊藤:大野慶人先生のワークショップ受けてみてください(笑)
高橋:素人でも大丈夫ですか?
伊藤:全然大丈夫ですよ。
高橋:おもしろいですね。
伊藤:びっくりしますよ。変な整体に行くより、大野慶人先生のクラスに行った方がすっきりさっぱりしますよ。
太田:感覚が目覚める?
伊藤:爽やかな気持ちで帰ってこれますよ。フォウゥーッ!っていうか。うん。全然、眉間にシワな感じじゃないです。あのもちろんそうなってやってらっしゃる方もいるんですけど、私はもフォウゥーッ!って感じ(笑)。
ダンスにしかできないことってあります?
残らない芸術
高橋:26年という長いキャリアですけど、長く続けていく上で、マンネリを回避していくとか、追求していくテーマを変えるとか、転換点みたいなのってありますか?
伊藤:ありました。3回か4回くらいあったと思うんですけど、でも、それも自然に転換していった感じなんで、意識的にそうしてきたわけじゃないですね。
高橋:その都度、自然な流れで変わっていったという感じですか?
伊藤:そうです。はい。
高橋:ダンスにしかできないことってあります?
伊藤:「感覚」なんじゃないかと、今は思ってますね。
高橋:あー。
伊藤:すごく抽象的ですけど、抽象的だからこそ出来る事なんじゃないかと。周りで起きてることを感じるわけじゃないですか、目に見えないことが起きてるんだよね。たとえば音楽も目に見えないでしょ、ね?それを感じて、それを出すときに、それをある形にするんですよ。身体でね。それがまたサッってなくなっていくわけ。なんかすごくないですか。
太田:神懸かってるって言うんですかね?
伊藤:伝えるっていう、なんか媒介している感じ。それがだんだん自分に強くなってきている。感覚的に。芝居ってどうしても言葉になっちゃうし、美術だと形を作んなきゃいけないし、音楽もある音を、、、要するに「残す」ってのがある種のテーマになってる。写真でもなんでも。だけど、ダンスって残らない。そういう芸術なんですよね、ずーっと。
高橋:なるほどねぇ。
伊藤:その場のリアル、ライブじゃないと体験できない芸術。最近は、それをどうアーカイブするか、どう残すかっていうのが問題になってるぐらい。記録に残らないものとして、ずっと存在してきたものなんですよね、ダンスって。だからこそ、今私がやってることって、出来るんじゃないかな、って思うんですよ。すごく。
太田:形に残らないからこそ?
伊藤:そう、唯一って言っていい程、今思えてることかな、それが。ダンスってなんの役に立つんだろうとか、いろいろ考えてるんですけどね。まだ具体的に思いつかないんですけど、でも、これはダンスにしかできないことなんじゃない、っていうのは感じてることですね。
(了)
[プロフィール]
高橋喜代史 アーティスト/コーディネーター
1974年妹背牛町生まれ。書の筆、立体文字、映像、プロジェクトなど、人のつくりだす境界についての作品を制作、考察している。北アイルランドやニュージーランド、中国など国内外で作品を発表。1995年ヤングマガジン奨励賞、2010年JRタワー「アートボックス」グランプリ。2012年より、500m美術館の企画、札幌駅前通地下歩行空間での[PARC]など展覧会やアートプロジェクトの企画運営も行う。
一般社団法人PROJECTA 代表理事/ディレクター
作品紹介