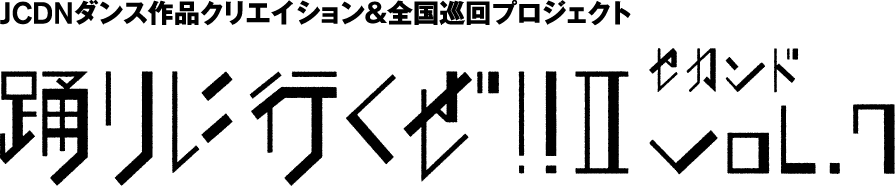2017年01月04日
聞き手・テキスト:みずのりつこ
テープ起こし:内山幸子 渋谷陽菜 インタビュー 2016年12月19日 城崎国際アートセンター スタジオ1
山下さんは大阪の出身。京都を拠点に活動している振付家として中心的存在だ。じっくりとひとつの作品をつくりあげ、再演し続けるその独自のスタイルが、国内外で話題作となり評判となってきた。今回の新作は、タイトルからして謎が多い。どのような視点を持ち、その着想はどこから来たのか?城崎国際アートセンターでの滞在制作18日目の山下残さんに、稽古が終わった直後にお話しをお聞きした。
(c)igaki photo studio
chapter one
京都でダンスを始めた
京都では1990年頃、コンテンポラリーダンスらしき動きが始まった。同じ頃、京都を代表するダンスカンパニー モノクロームサーカスが立ち上がるわけだが、それに山下残が関わっていたということは、知る人ぞ知るトピックス。残さんがモダンダンスを習い始め、京都でうろうろし始めた25年前の出来事。
―― ダンス・テクニックのあるダンスカンパニーとして定評のあるモノクロームサーカスのイメージからすると、残さんが在籍していたというのは想像しにくいですね。
そうですねえ。これは、僕は声を大にして言いたいですけど、坂本公成に踊りを教えたのは僕ですからね。
―― ええ!? それ、インタビューで堂々と書いていいの?(笑)校正で急に削除しないでね。「坂本公成に踊りを教えたのは山下残」これタイトルにしようかな。
公成さんは当時、京大生で演劇青年。ものすごい人気俳優だったんですよ。二枚目プラス三枚目もこなせるキャラは演劇界でスターだった。その頃は、ダムタイプが大人気の時代。公成さんもパフォーマンス作品に興味を持ちつくりたいと。そうするとまわりにいる京大の演劇の人達では難しい。その時、運良く僕と出会って、僕はそのときにモダンダンスを始めていたので、ちょうど良かった、踊りを教えてくれっていう流れですね。
―― 残さんもダンスを始めたばかりで、人に教えるどころじゃ・・・おこがましい人間だったんだね。(笑)
まあ、そうですね。(笑)。でも僕も友達が欲しかったし、公成さんも学生だし。
―― 何を教えたの?
ひととおり、モダンダンスの基礎訓練とか。まわりが頭の良い人ばっかりだったから、僕みたいなちょっとアホが来て、夜にずーっとあの辺ウロウロしながらこういう練習どうだとか、こういうの思いついたとか、ずーっと2人で遊んでいた時期があるんですよね。1990年から1991年くらいの20歳くらいのときでした。
モダンダンスは僕が教えましたけど、僕にとって坂本公成さんは本当に恩師ですから。あのときに仲間に入れてくれなかったら、僕は舞台のことは知らなかった。舞台制作のことや、スタッフワークのこと、作品をつくっていく過程とか、そういうものは全部公成さんに教えてもらったと言えます。
残さんがモノクロームサーカスを退団後の1999年、東福寺駅の近くにある小さな小劇場スペース・イサンで、山下残主宰公演「空の色」が上演された。これが私が初めて観た残さんの作品。1年間滞在していたN.Y.から帰ってきた頃、ともかく舞台作品を観ることに飢えていた。18年経った今でもいくつものシーンがよみがえってくるほど、印象に残る舞台だった。
記憶違いがあるかもしれないが、ビジュアル化してみる。――舞台全体がレコード盤のようなつくりになっていて、客入れ時にはその舞台上に置かれたレコードプレーヤーに針が落とされる。舞台の設え自体が、さあ、非日常の世界へようこそと、誘われるようなワクワク感の持てる装置になっていた。女性コーラスが出てきたり、山下残が女装して歌ったり、何故かマラソンをしてゴールするというエンディングに、お父さんが登場したり、支離滅裂に展開していく構成なのだが、何故これをやるのかがよく考えられていることが伝わる。
振り返ると、記憶に残るダンスシーンはとりたててないけれど、不思議とこれはダンス作品なのか、否か、という疑問を持つこともなく、舞台は一環した熱量の高さに最後まで惹きつけられる。終演後、アンケート用紙に、書ききれないほど感想を書いた。20年前の私は、この作品の何にそれほど興奮したのだろうか。
―― 作品タイトルは、『空の音』という詩的なものですね。
あの時は、生活の音を録りためてたんです。その当時はiPhoneとかも無いですから、MDの録音機械を常に肌身離さず持っていて、日々の生活を録音して振付をしようというイメージがあったんです。その自分の生活の音っていうのは、上から俯瞰して見ると、「空の音」だなと。色んな音が何の音だか分からないけれど、それを一括して『空の音』って言ったら全部説明がつくかなと思い、タイトルにしたんです。
―― 細部までとても丁寧な舞台でしたね。
ありがとうございます。あの時の感覚でもう一回出来るかは、なかなか難しいですね。
それしかなかったからですかね、他に。勿論アルバイトしてましたけども、作品を作るということも年に一回しかなくて、企画に呼ばれるなんて一切無くて、自分で企画を立ち上げて、作品を一年間かけて作るっていう、そうすると、全てがそこに集約されますよね。
”もともと音楽がやりたくてダンスを始めたんです。
ダンス作品全体が音楽のつもりでつくっています。”
基本音楽が好きなので、ずっと音楽かけっぱなしですね。朝起きたときから、寝るまで。へたすると一人でいる時は寝るときもかけてます。インターネットラジオだったら24時間途切れないので、ロック系のネットラジオをずっとかけてますね。それが一番落ち着きます。
—― ロックが好きなんですね、意外な感じ。ネットラジオって私聴いたことないんだけど、ずっと曲だけ?
そうですね。時々、DJみたいのもありますけど、基本的に24時間曲をかけっぱなしで、いろんな曲を次から次へとかける番組。世界中に無数にあります。いくつかお気に入りのネットラジオがあって、それをルーティンで聴いてますね。
—― なるほど、それだったら知ってる曲も知らない曲もとにかくずっとかけてられるのね。どれくらいのボリューム?もしかして爆音?
うちの奥さんがちょっとやめてくれ、静かにしてください、って言うくらいの音量ですね。僕はそんな大きな音のつもりはないんですけど。
—―(笑)そうか残さんは、無音ではなくて爆音のほうが考えられるってこと?
そうですね、落ち着きますね。わーっと音が鳴っているほうが。ウトウトするときもありますが、聴覚を刺激されて、脳みそはすごく活性化されてるのかもしれないですね。だから作品は無音が多いんです。
—― 作曲家になりたかったの?
そうです。
―— 音楽の才能がないと自分で決めてしまったのは?
すぐわかるんですよ、才能がある人は。中学生ぐらいで実際にギター持って、スリーコード覚えますよね、ジャーンジャーンジャーンって。それで「僕はいまインタビューを受けている〜〜」みたいな簡単な歌詞に、才能がある人は簡単なコードでいいフレーズをバシっと、つくれるんですよ。♪「僕はいまインタビューを受けている〜〜」♪とか。それが僕には、いま聴いたらお分かりのとおり、ダメでしょ?ぜんぜん。
―— いやいや、わかんない。(笑)
だけど、身体を動かすことをやると、まわりの人が「おまえの動きおもしろい」と言うてくれてたんで、ちょっとは可能性があるんじゃないかと。簡単に言えばそういう流れです。
―そう言われてみると、残さんの作品中のテキストの朗読が、追っかけるようにセリフをたたみかけたり変な間を作ったり、音楽的だ、うまいなと感じていたのは、作曲をしていたのですね。いまの話を聞くとなるほど納得します。
もともと音楽がやりたくて、それからダンスを始めたんです。音楽の才能がないな、と思ってダンスにしたわけで、いまだに作品自体は音楽のつもりでやってるんですよ。言葉を使ったりしますけど、根本にあるのは音楽的な流れなんです。それは誰かの好きな曲を使うとか、既成の曲を使うというよりは、ダンス作品全体が音楽のつもりなので、自ずと作品は無音になるというか。ただ、足音とか呼吸とか、やっぱり無音といえどもいろんな音が舞台上にはありますので、そういうものを自分でつくっているイメージですね。
―実際に、音楽ではなくダンスをつくり始めてみると、想像とは違うなあと感じるのはどのあたりでしたか?
身体表現というものは、ものすごく力をいれて何か発する・見せるというものではなくて、逆に“身体の力を抜く”脱力するということが、見せることに繋がる、ダンスに惹かれる一つの要因でした。
何か喋っていて喋らなくなった後の「間」とか、何もしていない空間で観客の目線に耐えながらどれだけいられるか、というところが大事な身体表現のひとつだと思います。
それは音楽的な面とも言えますし、”身体の佇まい”というか、そこにどれだけ自分自身のオリジナリティ、身体表現が組み込めるか。これは、ダンスを始めた時から今に至るまで、続いている自分の探求ですね。
2015年 「悪霊への道」 韓国
chapter two
ダンスへのこだわり
”作品の発想が目芽生えるのは、身体の感覚。”
―― こんなこと言うと失礼かもしれないですが、残さんの作品を観てこれってダンス作品なの?って思う人は多いのではと思います。残さんは演劇じゃない、パフォーマンスじゃない、ダンスなんだ、振付家なんだっていうこだわりがあるとお聞きしました。
だからダンスとかけ離れたアイデアが舞台に立ち現れたとしても、それは情報からつくらたものではないです。例えば、『空の音』のように日々音をためながら、そこから生まれて来るアイデアだとか、日々コツコやりながら閃いたことをやるので、自分の身体を毎日使いながら、出てくるものだという自信があるんです。そうでないと自分は、絶対作品を作れないと思っています。出発点は自分の身体。だからダンスだって思います。 自分の中に全部壊してしまいたい、みたいな破壊主義的なところがあります。だけど、それを実際にやってしまうと、生きていけなくなるんだなって。
―― 残さんがダンス作品に言葉を取り入れたのは、早い時期でしたね。初期の作品からとのことですが、その後2002年の代表作「そこに書いてある」も言葉が主要な作品でした。セリフは残さんが全て書いているそうですね。その人の身体から言葉を見ようとするのか?残さんがこういうことを喋りたいっていうテキストがありきなのか?何か言葉に対する法則みたいなものはあるのですか?
なので、どこかで自分の作品を作るときの設定があります。たとえば、今回みたいな若い出演者もいれば、キャリアのある人―伊藤キムさんのような人もいるので、相手が今どういう状態かをみます。その人に対してどう関わっていくか。自分が今こうやったら、ちょっと難しいけれども、今は評判が悪いけれども、もう少し先になったらいいだろうなあとか。いろんなことを考えて「これだ」みたいなところを探します。 最終的に僕が書きましょう、2人で書きましょう、喋ってもらったものを録音して僕がテープ起こししましょう、いろんなパターンを繋ぎあわせて、生き残ったやつを早い段階で決めて、決めたら絶対やる。作品ができる何ヶ月か前にリサーチして一緒にやる人とヒアリングして、どういうふうに言葉を立ち上げて作品に当てはめるかということを決める。そこはわりと丁寧に考えて、計画を立てて共同で作品づくりをしますね。
―― 意外にダンス界の全体をみる戦略家なんですね。
(笑)戦略家というか、究極はどうやっていけば生きていけるか?を考えているんだと思います。ダンスのことを考えていない時も、違うことを考えてる時も、たぶん元を辿っていけば、自分はこれからフリーの、何も就職もしていない不安定なことをしながら、どうやって生き延びていけるかっていうことを。生活とか、多少政治のことも考えますから、そういうことも含めて自分はどうやって生きていけるかということです。
―― 結論はどういうところに至ったんですか?
(笑)。それはなかなかわからないですけど、すごく好きな話があって。僕は京都で左京区に住んでいて、左京区にイズミヤというスーパーがありまして、そこでいつもタクシーが並んでいるんですよ。すごく地味〜なところで誰もお客さん来ないんですよ。僕はそこで、タクシーのおっちゃんに説教したことがあるんです。
―― 残さんが運ちゃんに説教ですか?!(笑)
タバコを吸って道路に並んで、京都のこんなところにいるなと。市内の真ん中に行ったらいくらでもお客さん拾えるじゃないか。なんで1日そんなところにいてタバコを吸っているんだ、と。そしたら、「いや、お客さん違います。」と。
「私らはここでじっとしていることで、みんなで助け合って生きているんです。もし私が町中へ行ったら、私はたちまち生きていけなくなるんですよ。タクシーの中では自分たちの持ち場って決められていて、ずっと何十年もこのイズミヤの前で1日1人か2人、最低でも2〜3人でも乗せられる。町中に行くと時々いっぱい乗せられるけど、競争があるので乗せられないこともある。このイズミヤというポジションは、いきなり入れない。イズミヤの前で並べるタクシーは仲間内だけ。1日数人のお客さんを乗せるっていうことで、何十年間もタクシーを続けていられるんです。」
なるほどと。確かに調子にのって町中に行って観光客を拾うってなると、たちまち上手くいかなくなるんだなって、なるほどと。
―― 自分に例えるとどういうことに?
自分に例えるとちょっとわかんない(笑)。けど、この運ちゃんの考え方というのは参考になります。僕らは言うても、人前でわーっと見せるのが商売なんで、イメージとして「明日死んでもいいんだ!それくらいの気持ちで舞台に立つんだ!」と破滅主義的な感じというか。ダンスとか、音楽とか、表現をやることは、危険な部分というのはどうしてもあるんですよ、自分のなかに。全部壊してしまいたい、みたいな。だけど、それを実際にやってしまうと、生きていけなくなるんだなって。それをやったら長生きできないぞって。そういうことが日々、頭の中にあるんじゃないかなと思いますね。
2014年 「そこに書いてある」 兵庫
それは、今回のこの作品だからこのようにつくりました、この作品を作りたいからこういうふうになりました、ではなくて、生きること・生活していること・作品・が同時並行でレールに沿ってそこに在るからなのだろう。
chapter three
新作「左京区民族舞踊」の行方
「左京区民族舞踊」途中経過発表 @城崎国際アートセンター (c)igaki photo studio
応募のときは「左京区に舞踊団を立ち上げる」ってタイトルだったと思います。
―― 確かに“民族舞踊”ではなかったですね。民族舞踊という一回り大きな括りが出てきたのは?
そうですね。舞踊団を立ち上げるんだったらどこに立ち上げるか、カンパニーの理想みたいなものを考えたときに、自分の地元の左京区だろうと。京都のイメージは閉鎖的、でも、左京区っていうのはちょっと違う。学生の町で色んな人が集まっている。そういう人たちが“民族”と名づけてカンパニーを立ち上げて、何が原型なのが、何が基本的なメソッドなのか、わけの分からないゴチャゴチャした状態で、山下残がそこで舞踊団を立ち上げていく。
これをドキュメンタリー的な見せ方で作ろうとした時に、「舞踊団を立ち上げる」というとちょっと弱いし、●●団っていかにも企画っぽく、オチャラケている。
ある程度問題提起もしつつ、自分が今やりたいことを端的に説明するには、|左京区」|民族|舞踊団 じゃなく、|舞踊| にしようと。色んな思いが集約されている感じです。ちょっとぶちまけすぎて自信は無いですけど。(笑)
―― 最近、山下さんはインドネシアや陸前高田などで、実際に民族舞踊を勉強しに行かれているようですが、本物の(笑)というとアレですが、民族舞踊をどうとらえているのですか?
民族舞踊のマスターと呼ばれる人はいい意味で適当にやっているところもある。集団の場合リーダーよりも、メンバー皆の主体性にまかせて、いい加減にやっているからこそ、継続していけるものがあると思います。
―― これまで、残さんがカンパニーを立ち上げようとしなかった理由は?
1995年頃、モノクロームサーカスを辞めて、丁度同じ頃、水野さんのいた白虎社も解散しました。これからは「個」の時代だと盛んに言われてましたので、必然的に自分はソロで活動しようと。ただ、集団とやるのが好きだし、舞台はチームワークですから、自分が作品を作るとき個人の名前で毎回プロデュース形式でやろうと思ってたんです。ただそこから10年くらい経って、毎回違う人を集めるのではなく、常に何も言わなくても分かってくれるメンバーが必要。ああ、やっぱりカンパニー欲しいなと。
―― それって何時ごろから考えていたんですか?
30代後半くらいに。
―― 結構経ちましたね。なかなか実現しなかった理由は?
その辺から再演とか、海外公演やレジデンスのお誘いを受けるようになってきて、じっくり京都にいるってことが無くなり、京都で公演もしていないですね。あえてカンパニーをつくって、身動きできなくなるというのも困るなあと思いつつ、反面、京都にグループが欲しい、とジレンマがありましたね。
―― 今回のコンセプトは、舞踊団の特性としてリーダーとメンバーが、身体的にも思想的にも阿吽の呼吸で作品をつくりあげるというものなんですか?
自分がカンパニーを作るんだったら、このやり方でこうしていくだろうなという。実際は作品のなかで、音楽の田島さんが僕の代わりにリーダーとして、僕ら三人はダンサーとして、田島さんに言われたことに従ってやってます。作品を作っていくダンスのカンパニーのメソッドが、お客さんに伝わるようにしています。このあとの公開稽古を経て、初演の札幌に向かいます。
**
山下残のカンパニーが設立するかどうか、そんなことは、他者にとってはどうでもいいことかもしれない。そういうことよりも、何かを成し遂げようとしたときに、自分と他者がどう関係性を成立させ、目的を成就できるのか。自分の思想なり考えをかたちにするために、どのような方法論を他者・異物と持てばよいのか探していく。今回はそれを日本・アジア・世界と大きな単位の民族もあるけれど、左京区・山下残族という小さい単位の中で、ダンスカンパニーとしてオリジナルなダンス手法をつくり継承していこうとする。これは結構、リアリティのあるテーマで、私たちの日々の社会生活の営みの中にも共通点があるように思う。
「左京区民族舞踊」途中経過発表 @城崎国際アートセンター (c)igaki photo studio