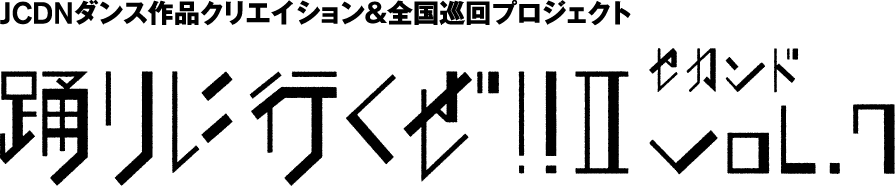2017年03月04日
話:
佐々木治己
黒田瑞仁
水野立子
司会:飯名尚人
テキスト起し:渋谷陽菜
編集:飯名尚人
収録:2017年2月9日
<ダンス作品を観てそこに流れる”思想”というものが感じとれる体験>
飯名:では、おひとりずつ、感想を聞いてみたいと思います。
佐々木さんから感想をお願いします。
佐々木:目の前で、輪廻転生を見ていく感じっていう面白さのようなものを感じました。そうすると舞台の虚構性、一人一人に特定の役割があるというよりも、交換可能というより、輪廻転生していく生物の在り様というように展開されていたように思いました。そういった部分が、テーマと方法の合致という感じもして説得力もありましたね。
飯名:鳥というものを通じて?
佐々木:鳥も一つの仮称というか。変形の一つ。何にでもなりうるし、何でも滅んでいく。生物がずっと何かをくり返してる感じがしていて、食物連鎖とか自然淘汰とか、見ながらそんなことを考えていました。
飯名:黒田君は、福岡公演で観てどうでした?
黒田瑞仁:寓話的という印象がまず強いです。これは宗教についての作品というより、「THE RELIGION OF BIRDS」ていうタイトルの一つの物語。鳥になって出てくる人たちがいて、初めは少し怖かった。一心不乱に鳥であろうとする人たち。凄い力で踊っていて、この人たちはとにかくこのお話を表現しているんだ、っていうのを割りと早々に気づいて、そこに集中して見ました。じゃあ何で鳥をストレートにやるんだろうとも思いました。岩渕さんや山下さんと違って、ダンスの状況とか社会とか、そういうものに対してメタをはってる感じがしない。見てる人がどう思うかは、ひとまず脇に置いて。まず黒田さんたちが題材をやり切る。それに圧倒される時間なんだろうと思います。登場する鳥たちの意思もあるんでしょうけど、彼らの仏教がどう、というよりもその人たちがこの物語や鳥たちを信じているということ。そのひたむきさというか、それに情熱を傾けられるダンサーたちに見入ってました。
水野:他のダンスカンパニーの作品とは特別に違った?
黒田瑞仁:割と現代社会に対してとか、他の作品を前提があってとか、お客さんはこういう人が見るんだろうという計算をしているというより、真っ向勝負。自分たちの思ったことを強烈にやっていて、そうすることで他のダンス作品とかカンパニーと違うんじゃないかという印象は受けました。
水野:ダンス作品を観てそこに流れる”思想”というものを感じとれる体験は、それほど多く持っていないのですが、この作品からは、物語でなく作品の持つ思想が受け取れたとように思います。
飯名:作者である黒田育世さんの思想が感じられた?
水野:そうですね。この作品は原作がありますから、作者は原作者と、そこから離れて黒田育世さんがオリジナル化したところもある。原作本からダンス作品にする過程で、育世さんが身体表現としての言語を見つけ出す必要がまずあって、結果、舞台作品から”思想”が伝わってくるというのが面白いと思いました。広い意味でコンテンポラリーダンス作品としてつくられる場合は、観る側とすれば原作そのものを忠実に再現するのだろう、とは思わずに客席に座ると思います。その上で、原作以外に何を受け取れるのかを期待し、まだ見ぬ何かを求める。原作は既に完成し価値を得ているものですから。今回はダンスだけれども、ダンスの躍動感とかテクニックとか身体表現としてのダイレクトな感動が最初にくるのではなく、不思議と思想を受け取った、という印象です。
<言語的でない思想、育世さんの言葉だと“知的でない”を意識してつくられている>
飯名:僕は記録映像しか見ていないのですけども、僕はこの作品の単純さ、簡単さ、というのが面白かった。例えば、マハーバーラタを舞踊とか音楽にしたりとか、もともと物語があって、その物語を知ってる人が観て楽しむ。知らないと誰が何の神様で、誰と誰が戦ってるのかよくわからないところもある。でも、踊りや音楽として面白いから見ちゃう。もちろん宗教的価値観や物語を知っていると、もっと楽しめるけど、知らなくても楽しめる。こういう見せ方の作品というのは、コンテンポラリーダンスという領域だと、説明的だ、とか、物語の解説になっちゃってるって、マイナスな評価も受けるときあるけど、実はそれと別のエネルギッシュなものがある。そのことと、作品の持つ物語性とは全く別なものな気がするんです。
水野:マハーバーラタは、ストーリーは誰もが知っているものだから、ダンスというかパフォーマンスに集中させるみたいな?
飯名:マハーバーラタを舞台作品で観るときに、当然説明的だし、実は簡単な”お話”なわけです。いかにも神様っていうのが出てきて、「怒り」とか「戦い」とか、そういう踊りをしたり。観客は、マハーバーラタのコンセプトとかダンステクニックとか、アートのコンテキストとか、そういうところを分析したり批評したりはしないで、純粋に楽しく観てるんじゃないかと思います。ダンスでそれらを扱うときに、言語で書かれた物語を再現しているのではなく、その物語に描かれている喜怒哀楽を表現するようになっていきます。説明的な要素はダンス表現だと削ぎ落とされてくるのは当然で、そうすると、逆にどんどん簡単にしていく、ということの面白さはあるんじゃないかと思ったんです。言語的に複雑な物語をダンスで表現するのは難しいでしょう?黒田育世さんのインタビューにあったように「知性でみるのではなく」ということは、インドで子供達がマハバーラタを見るときに、知性を持ってみているか、というとそうではなくて、面白かったり怖かったり、そういう単純な感情で観てると思うんです。
黒田瑞仁:異国のものを見るようにちょっと距離をとってみると、いいかもしれませんね。
水野:確かに現実的な何処かという印象はないですね。その印象と繋がるのかもしれないですが、先ほど“思想”を受け取ったと言ったのは、スケール感が関係あるかもしれない。仏教の教えを読み取るということは、当然、深いわけで、そんなに簡単に、了とは言えないものがある。それをダンス作品にする場合、抽象だから表現できるメリットがあるのかなと思いました。鳥の説話として、優しい絵巻物語のような体をとっているけれど、ストーリーが軸になっている原作ではないので、抽象的なダンスシーンの展開になるけれど、抽象的すぎてぐちゃぐちゃにはならない。訓練された体から繰り出すダンスがやっぱりしっかりしているので、グイグイっていう感じでいつの間にか集中してしまって、その世界に入り込んで受け取れている感じです。
佐々木:例えばTシャツで顔を覆ったりなど、繰り返されてるイメージや動きがありますね。分析をするつもりはありませんが、繰り返されている動きが何かに結びついていると思って見ていきますよね。これは何だろうかと、探っている見方が生まれてくる。そうすると色々なシチュエーション、色々な場所、違う人が同じ動きをするというのを見ていると、やはり、生物、生命、人間の物語みたいなものをそこに見出してしまうんです。生まれて死んで、また生まれて、再生の物語みたいなものを分析ではなく、勝手に読み取ってしまう。そういうところがこの作品のある種のイメージの強いところがあるのかな。
水野:育世さんがこの原作の中でアクセスするポイントというものがあり、そこからダンスを立ち上げようとする時点で、言語的でない思想、育世さんの言葉だと“知的でない”を意識してつくられている。自分の心がそれを感じ取ろうとするなら、勝手にいくらでも膨らませていいよ、というダンスの良さがあると思います。
<15年やってるカンパニーだからこその確かさと説得力>
水野:BATIKの代名詞的とも言える群舞の力は、相変わらず健全でした。後半にかけて、それまで行われてきた出来事を終息に向かわせていく、それまでの個々の役割を超えて全員での力強い群舞をみていると、やはり納得させられるものがあります。それは、舞台上のダンサーを見つめつつも、自分と向き合うような感覚が沸き起きるからかもしれない。あぁ、そうか、こういう風にしなきゃいけないな、と自分自身のことを顧みてしまうような。説明でも表現でもない、だけどメッセージ性を持つダンス。その力は15年やってるカンパニーだからこその確かさと、説得力があるなあと。
佐々木:構造として面白いなって思ったのは、仙台公演では一回礼したらみんな終わったと思って拍手したりするじゃないですか。それでもう一回始まるっていうか、それもある意味終わりと始まりという感じがしました。舞台自体にも死がある。そういう意味で、非常に論理的な作品だと思うんですね。ガチガチの論理ではなく、ある種の原理を強固にくり返す論理って言うんですかね。そういったものをこの舞台に凄く感じましたね。
水野:そうですね。育世さんは舞台のシャーマンと言われるほど感性の人だと思われている一方で、作品構造はしっかりとある作品をつくりますね。15年の活動の中で1期から現在4期まで来たそうですが、今回の作品は特に絵本を開くように、絵巻物のような流れがあり観やすい作品だと思います。その中で、原作の違う章にも出てくるのですが、人間界だけのことを描いているのではなく、元々、仏教の思想は動物界にも理解されるものという、舞台上に鳥やほかの動物も出ます。赤児から母までいましたね。ダンス作品の中で、演劇のような役ではないのですが、あきらかに等身大の女性ダンサー以外のものをダンスしている、ということが自然にできていることは特徴的でしたね。それが何故か何かを演じているのだと、主張がないところが伸びやかにみえました。
黒田瑞仁:前半とは、全く別の位相というか、次元とういうか、展開があった感じがしました。途中、これでラストかな?と思うところまでは、鳥たちの物語を見ていたような気がします。そこから先は物語だった鳥たちが、もっと概念的な領域に入っていく。世界や思想の状態そのものを見ているというか。
水野:終わりの始まりのような、それぞれがこれまでのキャラというか役割を捨てたような、それでいてまだあるような。顔見世というか、さよならなのか、皆さんに挨拶して飛び立って行く。育世さんのインタビューの中で、“原作の最後ではトビとワタリガラスが置き去りにされるけれど、この作品では一緒にお辞儀をしたい”と語られています。そのことと一致するかどうかわからないけれど、最後のデュオというか二羽なのかな、の短いシーンですが心惹かれました。この二羽がトビとワタリガラスかどうかわからないし、違うかもしれない。このダンスからは、何かすんなりと生きていけていない、うまくいっていないものを抱えている姿、それでいて鋼のような強さがリンと響く感じがして、なんというか前向きな孤独の生を感じました。
(了)
<LINK>
巡回公演地からの声・レコメンド集③ THE RELIGION OF BIRDS 黒田育世(東京)
https://odori2.jcdn.org/7/?p=1344
公演情報
東京公演 3/17-19 チケット取扱
https://odori2.jcdn.org/7/?tag=loc-tokyo
京都公演 3/25-26 チケット取扱