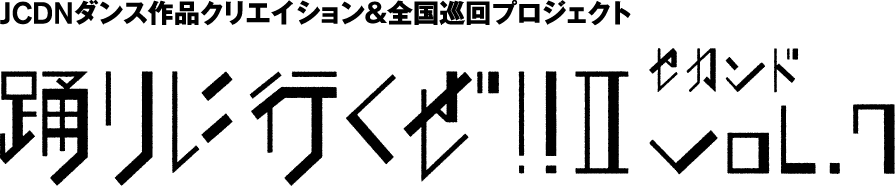2017年02月28日
記事:黒田瑞仁
撮影:藤本彦
![]()
劇場は平日の昼間も地上に地下に活気の絶えない福岡の中心街。天神イムズの9階にあるイムズホールだ。ここに2017年2月4日の土曜日、三つのダンス作品がそろった。東京からは各地を巡る今年の踊2のAプログラムとして岩渕貞太。ニューヨーク・京都からは踊2で過去に上演し、その後は鳥取、アメリカと作品を磨いていき、国内外で好評を博す余越保子『ZERO ONE』の再演。ゆみうみうまれはオーストラリアのメルボルンで普段は活動していて、Bプログラムとして地元福岡のダンサーや現代美術家とともにこの公演のために作品を作ってきた。会場となったイムズホールは舞台・ロビー・楽屋ともに同フロアに収まり出演者たちも気軽に中を歩き回れる居心地のいい劇場だ。劇場自体は、舞台と客席は広くて高低差は少なく舞台は客席よりも腰の高さほど上がっている。だから客席に座るとちょうど目の前にダンサーたちの体が現れて目の前で踊ることになる。観客と演者が近い劇場だ。
私は「ああ、オバケが出てくるとしたら、ちょうどこのへんなんだろうな」と思いながら一度きりの本番を観ていたが、そう思ったのはこのイムズホールで上演された3作品が全く異なる作風でありながら、どれもが観客をトランスさせるような変幻の演目だったからである。
![]()
![]()
![]()

岩渕貞太『DISCO』(Aプログラム)
ゆっくりと舞台上の世界観に入り込む気分でいると、1作品目の岩渕貞太『DISCO』の冒頭の爆音でかかるポップ・ミュージックとチカチカと切り替わる映像に全く騒然とした別のどこかへ引き込まれる。その音楽と映像、照明のモノトーンでありながら派手な設えを目の当たりにすれば、これはコンテンポラリーダンスの会場とは脳は認識しない。その爆音と、舞踏のような内向的な踊り。岩渕貞太は危うげに立ち、髪は揺れ、唸っていた。しかしその一見緩慢な踊りは「誘惑」であり「色気」として観客の前に、ソロダンサーの姿を借りて存在感を示す。舞台セットはないが、映像と音楽が切り替わり、舞台の色を塗り替えていく。ノリの良い曲に決して乗らずに対抗するように、しかしうごめきる人物がいた。
観客たる自分はというと、音楽とそこに立つ謎の存在に気圧され、客席に縛り付けられている。しかし、「自分も!」という衝動が内面で暴れまわっていた。私はダンサーでもなければディスコ、クラブ通いの経験もない。しかしどういう理屈で行われているのか想像もつかないよくわからない踊りと同じことがしたくなっていた。それがこの作品に於ける誘惑であり、踊りというものの色気だろう。あのエネルギーや、乱暴さが欲しくなる。別に何かを壊したいとか、憎いわけではない。

ところで、なぜ人は夜遊びをするのだろう。酒に溺れ、自転車に乗って大声で歌ったり、ドラッグに手を出したり、わざと喧嘩したりするのだろう?『DISCO』も然り。自暴自棄なのだろうか。でも自暴自棄にだって原因がある。ここでは高尚さや、含蓄を音楽に求めていない。信頼に身を任せているわけではないのだ。もしかすると、この舞台で岩渕貞太が体現している、一つのバケモノのように唸り暴れる形のない欲求を満足させたいのではないか。きっとそれはディスコでなくたって構わない。もっといいものがあれば教えて欲しいくらいなのだ。しかしそれはラディカルでなければならない。もしかして人によっては破壊ではなく秘密の偏執として現れるかもしれない。どのみち理性は追い出さなければいけない。
そんな、生半可なアクティビティでは満足しないバケモノを誰もが飼っている。岩渕貞太の形をしたその「何か」が舞台上で硬質な不満をさらけだすことで、観客の中のそれを共鳴させたのではないか。誰もが知っている孤高を見せつけるからこその、独り舞台だった。
![]()
![]()
![]()

ゆみうみうまれ『白い昼の夢〜White Day Dream』(Bプログラム)
しだれた糸が空間を区切り、左奥にはレースの垂れた傘、右前には枯れ草のカタマリ。舞台上はどこか輪郭が曖昧なものばかり、まっ直ぐなものはなにもない。すべてがヨレヨレ、ガサガサとしていてまるで子供が定規も使わずに描いた世界に見える。この上を7人の出演者が動き回ることになるのだがこの舞台装置の中では、人体さえもとてもいびつな造形に思えてくる。
悪夢だった。不条理といってもいい。しかしどこか懐かしいのだ。ダンサーたちは妖精のように、縦横無尽に動きまわり、のっけから混沌が舞台を席巻する。知らない言語を喋り爆笑しあう若い女たちがいたかと思えば、空気を意のままに動かそうと躍起になる誰かもいる。誰もが目的なき目的をこなすことに忙しい。だれもかれも怪しく非常識で目のやり場に困る一方、郷愁にも似た魅力を持つおぞましさがそこにはあった。『不思議惑星キン・ザ・ザ』や『バーバレラ』に見るような理不尽さ、愚かしさだ。しかし恥ずかしながら、人間というものは、もちろん自分もそんな部分があると納得しながら見入ってしまう。

奇妙な人々はやがていなくなる。舞台上が無人になったかに思えた時、枯れ草のカタマリが動く。枯れ草からビッグフットのような毛むくじゃらの怪人が現れた。ネイティブ・アメリカンの輪っか状のお守り、大きなドリームキャッチャーが振り回され、人々は現れ、またすぐにこの世界は説明のできなさを回復してしまう。二人の女性がクルクルと回って観衆の視線をさらいに来る。何もかもが曖昧模糊に広がる時間の中で、彼女たちは颯爽と現れた。音と色が一気に舞台の鼓動を促進していく。一人が手の平で一閃、空を突く。これは私だけの体験かもしれないが、私にはその突きが忘れられない。その突きだけが素早く鋭敏で、その奇妙に鈍い世界の何とも違う。驚きだった。でもそれはきっと酩酊させられた脳が見ただけの、悪夢の底に輝く宝石のようなもので日常に持ち帰ればたちまち石ころのように色あせるだろう。夢の楽しさは持ち帰れない。
幻のような、夢のような。言葉にし得ないものを表すというのは、ある意味では舞台芸術の王道だ。しかし表現は形にはまらずに、観客の脳を侵食する。他の2作品とは全く違う、ゆみうみうまれ『白い昼の夢〜White Day Dream』の武器は鋭さではなく、得体の知れない鈍さだった。
![]()
![]()
![]()

余越保子『ZERO ONE』(Dプログラム)
出演者は2人だが、登場人物は3人。バックスクリーンに映し出された老人は、あろうことか首を吊っている。舞台上には一人のショートカットの女性。スケートをするように舞台上をスイスイと泳ぐように踊っていく。思わず見とれていると、彼女とまったく同じ容姿の女性が現れる。双子だったのだ。
彼女達は作品を通じて見上げるほど大きく映し出される男(首くくり栲象という人らしいのだが)とは何の関係もなく、動き、じゃれあい、三味線に舞い、関西弁で誰にともなく説教を垂れたり、しまいに喧嘩もする。怪しげな音楽、垂直に眠るように宙に浮く巨大な老人の映像の前で、踊る双子のダンサーたち。なぜ首をくくるのか、この二人は誰か。何かそこに必然性を感じながらも、納得のいく説明などはつけられない。
まるで異国の寺院で見たこともない儀式を目の当たりにしたような心持ちで、圧倒されるが眼前の光景の説得力は凄まじい。そしてその奇妙は互いに、そして観客である自分と和解することなく、幕が閉じるのだ。彼と彼女らはコインの表裏のように無関係を装う。首を吊る老人はどうやら死ぬ気がない。数センチ地面から浮いていて、その分だけ現世から離れているが、それが生を肯定する行いだとカメラ越しに感じさせる。双子は虚しいまでにガランドウの舞台上で、身勝手なほどに元気に動き回っている。

実は、彼女たちが舞台上で喧嘩した時、客席を含めた劇場全体が明るくなる演出が挟まれる。客席は明かりに照らされ安心しきって舞台を見ていた私たちは少し居ずまいを正すのだが、舞台上の二人は口論に夢中で客席にはこれっぽっちの関心も示さない。その瞬間は観客よりも、彼女たちのほうが堂々としていて、存在としての確からしさは上なのだ。きっとお客さんたちはポカンとしたり、少し気恥ずかしくなったりもするのだが、自分と彼らが対等かつ、無関係な存在であると理解する。異国の儀式が信者でない自分に関心を示さず続くように、老人はこれからもどこかで首をくくり続けるだろう。これからもあの女たちはあのがらんどうの空間で踊り続けるだろう。観客である自分は劇場を後にする。そもそも全く関係のない三者がこの劇場空間でニアミスしたことが奇跡のようにも感じられた。『ZERO ONE』。私たちが連続すると思い込んでいる0と1は、お互いに接してはいない。無と有ほどの隔たりがある二つの現象なのだ。
英語にはMind your own businessという慣用句がある。「他人に構ってないで、自分のことに集中していろ」というちょっと相手を突き放すような言葉だが、ここでこの言い回しを思ったのは不愉快を感じてではない。彼女達は、首くくり栲象は気持ちのいいまでに自己完結していて、愚図愚図と誰かに構ってやしないのだ。劇場を出る自分も、あのヘンテコな世界を思い出しつつ、自分の世界にドライに戻るための勇気を貰ったような心持ちだった。