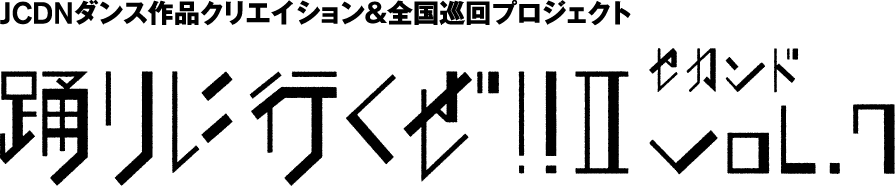2017年02月18日
記事:佐々木治己
撮影:越後谷 出
![]()
「コンテンポラリーダンスは基本的には何をやってもいいというのがあると思っています。バレエなどの場合だとテクニックや解釈を見たりすることもありますし、古典という共通認識があるわけですから、何をしているのかというのは比較的わかりやすいものでもありますが、コンテンポラリーダンスではそれがない。そのため、コンテンポラリーダンスって分からない、と言われることがあります。」と、仙台公演の最終日のポストパフォーマンストークで司会者が話しはじめた。「古典の代わりに共通している認識のようなものがあると思うんです。例えば、子供のときにトイレで一人になったときに、急に宇宙と自分が繋がるような気がしてきて、自分はなぜいるんだろう? と思うようなことがあります。なぜ、この私はいるのか? この体はなぜあるのか? といった漠然としたものを、コンテンポラリーダンスを見ていると思うときがある。私に対するなぜ、というものがコンテンポラリーダンスを見る上での共通認識になっているように思うんです。」と司会者は分かったような分からないようなことを言って悦に入っていた。そんな司会者は私です。
![]()
![]()

北村成美『黒鶏 –kokkei-』(Bプログラム)
黒鶏を模したショーダンス風の衣装に身を包み数羽の黒鶏が騒いでいる。奇声をあげ飛び跳ねながら、挑発的に客席を睨みつけてはまた奇声をあげる。言ってしまえばそれだけだった。それだけにも関わらず、この舞台に惹かれるものを感じるのはなぜだろうと思っていた。鳥は何を考えているのかいつも分からない。犬の気持ちや猫の気持ちが雑誌になっても鳥の気持ちは雑誌にならないのではないかと思うことがある。明け方、ゴミを漁るカラスと目が合うと、飛びかかってくるのかも、と思うことがある。飛びかかってきたらこうしてやろう、ああしてやろう、と考えてしまう。愛でる気持ちなど一切起きない。なぜだろう。愛鳥家というのもある。文鳥を愛でる友人もいる。九官鳥や鸚鵡など犬猫並みに愛玩される鳥もたくさんいるだろう。しかし、私は、鳥は何考えているのか分からないと思ってしまう。そして何を考えているのか分からないというたった一つの理由によって鳥を拒絶してしまう。あの足はきっと恐竜だ、とか思ってしまう。
あの仲間に入れない。そこに惹かれるのではないか? と思った。あの何をしているのか当人たちも分かっていなそうな行為、そして狂騒。あの場においてはせずにいられぬものがあるようだ。舞台を見ながら異邦人のような気持ちでいると、振付・演出を担当した北村成美さんのインタビューを思い出した。詳しくはインタビューを読まれるといいと思うが、インドネシアに行ったときに黒鶏を見て驚いた、というエピソード。この何気ない、どこにでもありそうなエピソードを思い出した。黒鶏に対して拒絶的な振る舞い、それを異形だと判断する私が挑発されている。<お前こそなんだ>と問われているような気がした。そのような姿が舞台で現れたとき、私の差別、私の憧れ、私の拒絶、私の私の私の、と多くの私の何かがピクリと揺さぶられる。
![]()
![]()
![]()

岩渕貞太『DISCO』(Aプログラム)
パーティーやクラブの感じは私も分からない。パンフレットやトークで、岩渕さんも分からないらしいと思った。だから分からない。と、そんなことではない。パーティーというものが開かれると、そのパーティーの内側の人しか考えられない。パーティーの外側で、漏れ聞こえる音楽を聴きながら体を揺する人もいるかもしれない。嫌悪を示す人や憧れる人もいるかもしれない。パーティーピーポーと俗に言われる人たちとなかなか共に過ごす機会はないが、一歩引いてみれば、不安と空虚さの誤魔化し、承認欲求、帰属意識の現れでしかないとそんなことは賢しらに言われなくても、パーティーの渦中の人だって分かっているだろう。
DISCO、パーティーよりも懐かしい匂いのするその響き。ダンスミュージックに流されずに踊る岩渕さんを見ながら思ったのは、別の場所を探している、のではないか、ということだった。パーティーが悲しい誤魔化しでしかないにしても、では、なぜ誤魔化すのか、「私たちは楽しんでますよ!」となぜ頼まれもしないのにアッピールするのか。そして、今ではあまり聞かなくなったDISCOとは何を意味していたのか。「別の場所を探している」と岩渕さんを見ながら思いつつも、パーティーもDISCOも「別の場所を探した」のではないかと思った。ちょっとややこしくなってしまった。日常とは違う場所を作ろうとしてパーティーやDISCOは作られたのだしよう、きっとそういう欲望があったにちがいない。そしてそういう場は次第に廃れていく。何かの場として成立した途端に、場としての意味を喪失していく。場としての意味を喪失した中で、場の本来性を探すでもなく、陳列するように動いている岩渕貞太。ニジンスキーのようになってみたり、室伏鴻のようになってみたり、男前な岩渕貞太だったりするが、それらは全てフラットだった。何かに成る、変身する、演技をする、ということではない。地続きのように、同じようなリズムで動いている。音楽や映像が変わっても大きな変化はない。たゆたうように、何かを探すようにその場にいる。
地続きに全てを受け入れようとするところが岩渕さんの体なのかと、パーティーの内側にも外側にも属さず、その上や下で何かを探すような印象を受けた。
![]()
![]()

黒田育世『THE RELIGION OF BIRDS』(Aプログラム)
壮大な感じがした。1作品目の「黒鶏」の鳥とはまた違う鳥だった。鳥に対する私の鳥恐怖症的なものは「黒鶏」で現れていたけれども、「THE RELIGION OF BIRDS」では、ギリシア喜劇「鳥」(アリストパネス)で感じるような鳥。人間の社会とは別の価値基準で作られる鳥の世界とでも言えばいいのだろうか、そんなようなものを感じた。舞台は物語を追っているつもりではないのだが、ある種の物語を感じた。その物語とは、生老病死や、天人五衰のような物語で、生や死が辿る滅びと再生の物語と言えばいいのだろうか。
立ち現れては消えていくダンサーに輪廻転生を思うというとなんだが出来過ぎな感想になってしまうが、舞台上の物事が何かの化身のように思えてくる。様々な身振りや小道具による状態の変化も、解釈しかねている事象をあらわにしているようだ。絵解きなどのように、この舞台を解いていくことで、生命の在り様が見えてくるのではないか? そんな気にさせる舞台だった。