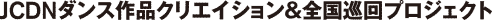2016.02.24
1月から巡回公演が開始し、札幌・松山・八戸・仙台と4地域での開催が終了しました。
これから後半戦に入り、残すところ3都市―神戸・福岡・東京公演に突入します!
回を重ねるごとに、確実にブラッシュアップされていく作品をみていると、やはり稽古だけではなく、実際に上演できる巡回公演は貴重だなと実感。各地の共催者・観客の皆さまの手で巡回公演を成立させていただき、再演が可能となる。ありがたい!今年の色々なスタイルのある上演作品を観ながら“ダンス作品”について3月まで考えを巡らせていきたいと思います。
ダンス作品を観ること、つくることーその時、脳内に何が起きているのか?
今年の「報告するぜ」の初心表明にもあるように、ダンス作品をみて“ダンスを語る”っていうのは楽しい、面白い。けど同時に難しい。何故なんだろう。
私がダンス作品を観る時の感覚は、擬音にするとドーン、とか、ガーン、とかドヒャー、とか、つまりは、“観る”というより、強烈な何かを“体験する”ことに近い。なので、観終ったあとの私の体はいつもガチッガチに固まってしまう。それは、作者がつくり出そうとする作品世界を丸ごと受け止めようとして体がこわばるんだろう。
その時の脳の状態は、分析とか構成を考えるとか、そういった論理的な思考はしていない。むしろ自分が生きてきたこれまでの記憶や感情、それにプラスして持っている知識を総動員して作品を“経験・体感”しようとしている。舞台上で起きていることが波動のように、まるごと客席を伝染していく感じ。
なので、舞台を観ることで強烈な体験をすればするほど、これを後から言語化しようとすると、ある種の限界を感じてしまう。いくら話そうとしても書こうとしても、スルリと抜けていってしまう消失感。だからこそ、それが何かを掴みたくて、たくさんダンスを語りたくなるのだろう。
そう考えると、観る側だけではなく、全てを言語化できないダンス作品をつくりだす作者の側―演出家・振付家・ダンサーはどう考えているのだろう。テーマ・コンセプト・手法を思考していく言葉が必要な部分と、理由はわからないけれどこれをやる、これなのだろう、という直観のような要素が共存して、作品制作が成り立っていくように思う。そしてそこに在るダンスする体と対峙していかねばならない。だからこそ、ダンスと言葉は正反対なようで、実は表裏一体にあり、抽象に特化した表現が成立する。それがダンス作品の醍醐味なのだと思う。「報告するぜ!!」で飯名さんと、佐々木さんと、<ダンスと言葉>でたくさん語りました。
とはいっても、「踊2」で上演する作品をみていると、制作のアプローチの方法や、目指そうとしているところが、作品によってまるで異なる。それがまた興味深いところなのだ。

山崎広太作品 『暗黒計画1~足の甲を乾いている光にさらす~』 photo:yixtape
映画「アクト・オブ・キリング」と「マルホランド・ドライブ」から、
とてもダンス的なものを感じた。
巡回公演が始まる直前の慌ただしい昨年末、各地を回って12作品もの途中経過を続けて観ていたちょうどその頃、八戸で滞在制作をしていたBプログラムの作・演出の岩岡傑さんから出演者に、2本の映画鑑賞を正月休みの宿題として出した。ジョシュア・オッペンハイマー監督の「アクト・オブ・キリング」と、デビット・リンチ監督の「マルホランド・ドライブ」だった。岩岡さんがこの宿題を出した意図は全く別の意味だったと思うけれど、それとは関係なくこの正反対の2本の映画は、私にとってダンスについてハッとさせられ、とても面白かった。
まずは1965年インドネシアでの大虐殺の真相を暴くことになった「アクト・オブ・キリング」は、観た人も多いだろう秀逸したドキュメンタリー映画。笑えない映画なのに、何故か力ない笑いが込み上げてしまう。「あれは正義のための殺人だった」と自慢している男が、過去の殺人行為を再現し演じ続けるうちに、閉じ込めていた自己の大罪に気が付いてしまう。人間が地獄をみた悲鳴のような男の嘔吐シーン。これはちょっとすごい。これから一生、自分の十字架を背負って生きていく、茨の人生が始まった瞬間の本物の“アクト”だった。最後に流れるクレジットの出演者名が全部匿名になっていることが、この映画の影響力の大きさと、インドネシアの今、を伝えている。

ドキュメンタリー映画とは対局にあるデビット・リンチの「マルホランド・ドライブ」。つくりごと=お約束のフィクション映画というほど枠におさまらず、超絶フィクション映画と言うほうがしっくりくるくらいわけが分からないが、面白いところがスゴイ。物語的な筋立ても、時系列も、登場人物も、全てぶっ飛んでいる。リンチ映画に正当なフィクションやドラマを求めるなら全然、楽しめないだろう。現実的なこっちの頭が妙に嘘臭く感じ、この空間に存在する自分さえも虚なんじゃないか、と疑いたくなる。“作り物”とわかっていながらも、それが妙にリアルで魅惑的で痛快。筋立てはどうでもよく、一生忘れられないシーンが強烈に残るという映画だ。

この2本の映画は、世界中で大ヒットし人々に確実に何かをあたえた。私はこの2本の映画からとてもダンス的なものを感じていた。ダンスと同じだなあと思った。映画と、生身の体がある舞台とは違うだろうが、冒頭に “ダンスを観るとき理解しようとするのではなく、体験する”と書いたが、ダンスだけではなくアート全般で同じ事なのだろう。何かを強烈に受け取る、そこに存在を感じる、価値が揺らぐ、何かが見えてくる、ということに変わりはない。ただ、ダンス作品を観る時、これはドキュメンタリーなのか、フィクションなのか、なんて考えないし、この作家はどちらのタイプです、というカテゴリー分けもしない。ダンス作品は、ダンサーが舞台にいることの全部がリアルで、説明や筋立てがなく全部が超絶フィクションで、分けがわからない、のがとても当たり前だと思う。ここでいう「分けがわからない」という意味は、もちろん肯定として。
ダンスという独立した表現として成立できる“ダンスそのもの”、そこにプラスして物語を紡ぐ作品もあれば、プラベートな題材をパブリックなものに置き換えられる公共性を持つ作品、あるいはテーマやコンセプトを排除したムーブメントの開発を追求する作品、etc…もはや、コンテンポラリーダンスという名の元に限定されたものはない。“ダンス作品”のキャパは広く、「「踊2」でもこの手法でなければならない、ということはなく振付家・作家の発明したい手法に窓口は開かれている。ただし、それが新しい価値を提示する発明であってほしいし、作品から強烈な体験をさせてほしいと願う。今年の12の新作たちが、どのような手法のもと着地点に向うのだろうか。
作家と作品の関係性 「わけのわからない作品」のこと。
そんな時、保坂和志の昨年秋刊「遠い触覚」をamazonで買った。小説だと思って買ったのだが、目次を開けてみると半分強がデビット・リンチの映画の『「インランド・エンパイヤ」へ』だった。「観るたびいろんなことを考えて、考えが次々出てきて止まらなくなる。」とある。笑えた。例の岩岡さんの宿題となっていた「マルホランド・ドライブ」のことも出てくる。
ダンス作品で何が伝えられるのか、伝わるのか、どうやってそのつくる行為を真摯で真実に近づけることができるのか、ということをぐるぐる思考していた私にとって、この本とナイスなタイミングで出会えた感がある。まだ完読していないけれど、作家保坂氏が、自分の人生におきた出来事とともに、作品とそれをつくり出す作家との関係や、作品というものの正体をどんどん暴いていく。まるで作家のドキュメント本みたいだ。「作者と作品との闘争がついに最後まで緩解しない」ことで、「わけのわからない作品」が生み出されるという記述がある。ここでは小説のことなのだが、わたしはやっぱりダンス作品も同じなのだなあ、と思ってしまうのだ。もちろんこれは「分けのわからない」だけで何も観客が受け取れないことではなく、「分けのわからない作品」だからこそ、それ以上に体験できる強烈なものがある、という作品のことだ。
最後に保坂氏が「遠い触覚」でピナ・バウッシュ「パレルモ、パレルモ」について書かれている箇所をひとつ抜粋します。
「・・・公演から五ヶ月経っているので私にはもうダンサーたちの個々の動きは記憶になく、言葉として残っているだけなのだが、ダンサーたちは苦痛に耐えるようなことばかりやっていた。それは見ているこちらにまで苦痛としてくるようなものではなく、ダンサー自身が経験する苦痛なのだがそれによって肉体があることが現れ出る。」
「踊2」巡回公演でどれくらい分けのわからないダンス作品、に出会えるか是非、観に来てください!