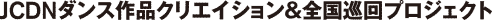2016年01月31日
八戸公演 Bプロ 岩岡 × 岩岡 対談
2016年1月13日(水)おらん洞 (岩徳パルコ3F)
岩岡 傑 × 岩岡徳衛(いわおか・のりえ)
傑:岩岡です。よろしくお願いします。
徳衛:私も岩岡です。当然ながら(笑)。
傑:岩岡さんの岩岡は、八戸の岩岡なんですか。
徳衛:そうです。昔は苗字がなかったでしょ。士族を除いて。うちの本家は実は岩岡ではないんです。うちの家系は商家だったので、屋号と家印があった。うちの屋号は岩屋。本家は、磯屋でした。うちは、岩屋という屋号をもって、この場所で、雑穀商をやっていた、200何年前。昔、新井田というところがあって、そこの大地主が磯屋で、造り酒屋さん。うちは、造り酒屋になれなかった、なぜかというと、ここは裏通りのビルでしょ。表通りは呉服賞とか、米商人がいる。西町書店とか、豪商だった。ここは、造り酒屋の河内屋さんもあったけど、表通りの商売。裏通りは、魚を商ったり、野菜をもってきたり、米は扱えないから雑穀を扱っていた。で、雑穀で作れるものはないかというので、醸造業。裏通りには、醤油屋さんがたくさんあった。苗字が許された明治以降。新井田の橋の高いところにあったので、本家の人たちは高橋さんという名前だった。うちは、本家の高橋さんより、もっと上を目指したいというので、橋より高いのは岡。屋号の岩屋の岩をとって、岩の上の岡で、岩岡さん…という苗字になったようです。高橋に謀反をおこして、このまちなかに出てきたので、高橋から岩岡に分かれたんです。
— 岩岡傑さんは、なぜオランダにいったのか
徳衛:在住はアムステルダムなのですね?私が行ったのは、40年くらい前なんですが、運河があって、お寿司屋さんみたいなお店があった。
傑:にしんの塩漬けがオランダでは有名ですよ。最初、イギリスに行って現代芸術をやったんです。ファインアートとコンテンポラリーアートというのがあって、私はコンテンポラリー。心象心理学、社会学、フーコーや、ベンジャミンとか読んだし、ジェンダーのことについてのディベートもあって。セオリーみたいなのをどうやって作品に落としていく作業を特化してやろうという学科だった。アウトプットは何でも良かったんですね。
徳衛:イギリスに行かれたのはいつ頃ですか。
傑:19歳のときです。
徳衛:そのころは、ダンスはなさってないんですか。
傑:高校は、工業高校。そのあとデザイン学科に行こうと思って、バンタンデザイン学校に行きました。最初はファッションデザインを1年やったんです。こんなことして何になるんだろうと思ったけど、ものづくりをする人になりたいと思って。もうやめて実家かえろうと思ったんです。愛媛に帰って、1年間学校には通わず、バイトとかして、その1年間で、「自分から何もつくることをしないんだったら、自分はものづくりができないんだ」ということにして、あきらめて他の道にいこうと思った。やめようと思った。ですが、ちょうどバンタンデザイン学校が、留学専攻科をつくろうとしたときだった。海外にはいきたいと常々思っていて。
徳衛:送り出すにあたっての資金は学校もちなの?
傑:自分持ちです。親に払ってもらって。僕は、ノッティンガムに行きました。バンタンの留学専攻科から、やっと自分のアートがはじまった。イギリスの教育はいいよ、ということで、行きました。アメリカだと銃で殺されるかもしれない、とかそういう中学生みたいな考えもあって(笑)。東京出る前に、どこを専攻するのかを決めなくちゃいけなくて、コンテンポラリーアートにしたんです。
— ハプニング、パフォーマンスアートの出会い
傑:バンタン時代に、アメリカから来ている先生の「ハプニング」の講義があったんです。ハプニング、パフォーマンスアートを教えてくれた。それがショックで。作家・作品・観客、この3つのダイレクトな感じがすごいなと思って、パフォーマンスアートというのをやりたいと思ったんです。それができそうなのがコンテンポラリーアートだった。イギリスに行くと決めたのはいいけど、何も知らないから、「ぴあ」を買ったんです。それで、身体を使っていそうなものを見ることにしたんです。勅使河原三郎、伊藤キム、イデビアンクルー、能美健志、、、伊藤キムワークショップのチラシがあって、受けたんです。バンタンの卒業制作展で、先生の知り合いで舞踏を勉強しているドイツ人が見に来て、自分の作品をみたときに「大野一雄さんのところに来ない?」って言われて、1日だけ受けに行きました。身体表現はそのころからです。イギリスに行ってから、即興とビジュアルアートを選んで受けました。即興は、ダンスインプロというか、何でもあり。パフォーマンスをつくるきっかけとしてのインプロだったんです。それが今でも生きています。
— 岩岡徳衛さんの大学時代
大澤:徳衛さん、 けっこう専門的用語も多く出てきてますけども、、、 今までの岩岡さんの話、わかりますか?
徳衛:いや、わかりません。年代もちがうしね。そういう世界は近くにあったけど立ち寄らなかった。私は通っていた学校は、外から見るとアートの学校ですけどね。デザインの学校でした。東京造形大学。インダストリアルデザインの学科でした。うちの学校のなかでは、ファインアートは虐げられていたんですよ。桑沢デザイン研究所のほうが、名が知れてますよね。ファインアートとは違うし、コンテンポラリーアート科とも違うし。私は学校にいたときには、コンテンポラリーアートという言葉は聞かなかったな。アバンギャルドな学校だった。岩岡さんと、私も動機不純なところは似てるんだけどね。というと、失礼かな(笑)。
私ももともと、興味の対象は芸術にはなくて。未だに、私は工学系のことにすごく興味があった人間で。電気とか、そういうことやっていて。普通科の学校なんだけど、物理室にこもってハンダゴテ触って。でも、高校3年生になったとき、そんなことでは行ける学校がないんだ!ということに気がついた。それまでは、ハンダゴテ、アマチュア無線、わけのわからない機械をつくってみたり。今思うと、たいしたことないんだけどね。高校3年生の1月くらいに志望校きまったんですよ。直前。造形大は、当時、入試が遅かったんだよ。当時は、芸大、ムサビ、多摩美、女子美、日芸、その次くらいかなーみたいなところだったかなー。いい先生には出会えましたが、4年間遊んでたね。手が動く人たちはすごいと思った。デッサンができるのはすごいね。私は全くできなかったから。大学前に、美学校みたいなところに行って「お前は、全くデッサンがダメだけど、ちゃんと勉強はしているみたいだし、立体造詣とかはできるだろう、造形大を受ければ?」と、美術の先生がちょっとバカにして言ってたようなところがあるかな。
岩岡徳衛(いわおか・のりえ):八戸の中心街どまんなかにある、いわとくパルコのビルのオーナー。
— 青森からきたけど、寺山修司が青森出身だと知らず
徳衛:大学に神様みたいにすごいやつがいたの。アクリル板でしかもの作らない、みたいな人とか。そいつには、「青森から来たのに寺山修司のこと知らないの?」って言われたんだよ。「書を捨てよ町に出よう」は知ってたけど、それが寺山修司で、青森県出身なんだ!って。そいつは、寺山修司に大道具作りに来ないか?って言われて行いっちゃった。小竹信節(こたけのぶたか)さん。人間を動かすような椅子をつくってた。後期の寺山修司の大道具を彼が作ってた。
— 岩岡徳衛さんの大学後の話
傑:大学の後、どうなったんですか。
徳衛:大学後ブランクの時期があって、普通の勤め人をした時期があって、八戸にそろそろ戻ろうかなと思って、お試しで戻ってきたら父親が病気してしまって、しょうがなくこっちにいることにした。受身でね。
傑:岩徳パルコのオーナーになったのは何でですか。
徳衛:おじがオーナーをやっていた。この建物は、父親時代に建てた。動機不純で、やることないからここに建物建てたらどうかなーと思って建てたんだよ。醤油屋さんとかやってたから土地はあったんだよね。でも、酒屋や味噌やは残るけど醤油屋は残らない。ビール工場みたいに、絶えず作ってないとだめなのね。酒蔵はシーズンがあるけど、醤油はシーズンがない商売。吟醸醤油とか、何年ものの醤油とかってないんだよね。ヤマサとキッコーマンと…ってあればいいんだよね。醤油ってあまりたくさんメーカーないでしょ?お寿司屋さんに行って、この醤油は?って聞かないですよね。
大澤:このビルに、アトリエや、うみねこ編集室とか、文芸的な場所をかまえたのは、徳衛さんの意図なんですか?
徳衛:うちの父は物書きだった。だから、そういう環境の人が寄ってきた人がいた。うみねこ出版の初代の吉田編集長の時代、全国で、地元の飲み屋さんの紹介なんかをする冊子をつくればおもしろいかな、という発想ではじめたんだよね。それを引き継いでやっていたのが、岩館さんだね。そういう場所としては、ビルの一角を化すということは、父もおじも、そういうことが好きだった。うちのおじは、油絵描いてた。私は、恥はかくけど絵はかけない。あはは、笑わないでよ。写真はね、手軽だから始めたんです。工業デザインをやってると、自分の作品を撮るために必要で。自転車に乗ったり歩いたりして、肩からカメラを提げて撮ったりしてて、でもこの町だから、3年くらい撮ってると、撮り尽くしてしまったのでやめました(笑)。
傑:今聞いておもったけど、二極化というのはいろんなところで進んでいますね。カメラもしかり、社会構造もしかり。中間がない。グラデーションがないですね。
徳衛:モノクロのコピー機みたい。モノクロのコピー機を使ってアート作品とか、そんなことやってた時代もあったなー。そういえば、日本の今の総理大臣は好きじゃないけど、一億総活躍社会はそうなのかなとは思うよ。というのも、今芸人が多くて、観客が少ない時代。みんな簡単に芸人になっちゃう。芸術かも含めて芸人。発表する人が多くて、見る人がすくない。見る人が少なくなったというより、やる人が増えた。カラオケくらいから増えたんだろうね。
— 八戸の踊り手、豊島和子
徳衛:八戸に、踊りをやってる人が居てね。豊島和子(としまかずこ)さんという舞踊家がいたんですけど。もうお亡くなりになってしまった方です。私がはじめてみたときには、もう70近かったですが。踊りというのか、「固まり」のようでした。火山弾のような、ドンと真っ赤な石があるような、その燃え尽きる姿をしているような踊りで、すごかった、すごいとしか言いようがなかった。八戸の人は、踊りの神様と思っている人も多いでしょう。でも、コンテンポラリーダンスも含めて洋舞は難しい。音楽だったらそのまま感じればいいのだけど。
傑:私は武道をやっている人に影響を受けているんですけど、踊る前にやることっていっぱいある、と。動きの前に、関係性、自分の身体をわかっているのか、自分がただわかっていると思っているだけで完結しているから届かないというか。人間的な技術がないと。声が出てるから届いているのではなくて、人間性に深みがないと、音は聞こえても声がきこえないという状態。音色を通して何かが来るから伝わる。言葉でも、言語に乗せているものがないとだめなんではないかと。日常はルールに乗っかっていれば上辺でも生きていけるようになってますけど、切羽つまってくれば、やるぜ!という心を入れる生き方しないとだめですよね。文化的に豊かになるとふわふわしてくる、観念的になってくる。「つながり」を持ってそこでやらないと、いろいろやっているけど、それで?っていわれちゃう。
徳衛:つながりというのは?
傑:手法が先行してもだめで、それを用いるのはなんでか。その形になった理由。そういうものとのつながりがあってこそ、創造的なコミュニケーションがとれるんだと思っている。とかいって、まだ自分の作品ではそれは出来てないんですけどね。作品って、その人が今までやってきたことが見えてくるから、強度を出すって難しいです。
— 作品のインスピレーションになった、河鍋暁斎
傑:今回作品のインスピレーションのひとつに、日本画の河鍋暁斎という人の絵があります。幕末から明治にかけての人。明治政府に目をつけられるまでは、河鍋“狂”斎と名乗っていたらしいです。偶然、はっちで、河鍋暁斎の特集された雑誌を手にしたんですよ。奇抜なピンクの色の本で。美術の中の、狂とはどういうことか。孤独に対してどんどん進んでいく。一人になったとしてもつきつめていく、ということでしょうか。おもしろい人だなと思います。頼まれたものは何でも描く、狩野派の勉強もしっかりした人。5歳で歌川国芳について浮世絵も習って。反骨精神、今までやったことがないことをやる。なんでもできるすごい人。
徳衛:今の作品とはどう関わっているんですか?
傑:よくわからない世界、世の中は、いろんなものがごった煮になっていて、河鍋暁斎が反骨的なものから、猫の絵から、いろんなものをやっているところに共通するかな。クラシックバレエがあったと思ったら、ラジオ体操があって、こたつに入ったら、テレビはピタゴラススイッチみたいな、ごちゃまぜが、同じ土台にのっている。分裂症でありながら、逆にくっついてきているみたいなよくわからない世界。ぜんぜん違うからこそ、全面がみえる。多重性、ということが、河鍋暁斎の本に書いてあって。今までは、多面性ということはやってきたかもしれないけど、多重性はないなと。キーワードで、挑戦してみたいのが多重性だなと。
徳衛:多面的から多重的なことに移行したいと思っているんですね。
傑:海外で作っているときは、ちょうどいいぬるま湯で血行にいいですよ、というところで作っている感じ。それが、今回は、風呂といったらあっついお湯でそれから水風呂だー!みたいなところに投げ出されたような。ちょっと自分を変えなきゃなと思っているところです。今回、やりたいことの完成形はできないかもしれません。でも、実験ではあってほしい。いろいろ実験したいですね。