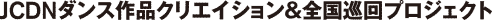2016年01月23日
神戸Cプログラム
2015年12月23日(水)
会場:ArtTheater dB神戸ロビー
アーティストインタビュー:
上野愛実
中間アヤカ
インタビュアー:竹田真理(ダンス批評家)
竹田:コンテンポラリーダンスの世界には多くの人がいろんな経歴を経て入ってこられますが、2人にはバレエの素養があります。小さい時にバレエを始められ、そこからそれぞれのきっかけでコンテンポラリーの世界に入られたと思いますが、まずはバレエが根っこにあるということ。それからもう一つ、2人とも別の地域のご出身ですが(注:中間は大分、上野は京都)、国内ダンス留学(http://danceryugaku.wix.com/main)をきっかけに現在は新長田に拠点を移して活動されています。
中間アヤカ『月月火水木金金』
— 役割の名前とか肩書きみたいなものに何の意味があるんだろう(中間)
竹田:さて今度の作品は、お二人がこの新長田で暮らす中で、日常的に見つけたものから着想していると聞いています。中間さんの今度の作品は『月月火水木金金』というタイトルですが、どんな作品になるのでしょうか。
中間:ダンス作品を作るときって振付家がいてダンサーがいて、あとは演出助手やドラマトゥルクなどの名前を持つ人がいたりいなかったりします。そうやって役割が細かく名付けられ振り分けられていても、私たちがやっているダンスの制作過程ではその役割以外のこともやる場面がとても多いと感じます。たとえばダンサーが出演だけでなく振付を兼ねていたりするような、よくある曖昧な部分も含めて、役割の名前とか肩書きみたいなものに何の意味があるんだろうとずっと考えていたんです。春から神戸の老舗の瓦せんべい工場でアルバイトを始めたんですけど、そこでダンスとしか呼ぶことのできない瞬間を目撃して。じゃあその工場の組織図を作品の座組にそっくりそのまま当てはめてみようと。振付家とかダンサーとか、従来ダンス作品で当たり前のように使われている名前を持たずに制作の過程を運転していけるのかっていう試みと、工場で見たようなダンスとしか呼ぶことのできない瞬間を立ち上げたいという想いからこの作品は始まりました。
竹田:メンバーの組織としてのあり方と、工場での作業の動きにダンスに引っ掛かってきそうなものを見つけたと。工員が正木悠太さんと佐藤健大郎さん、研究員が藤澤智徳さん。藤澤さんは出演されるんですか。
中間:どうしようか迷っているところです。そういうのを濁せるなって最近気づいて、それってすごく不思議に感じるんです。ドラマトゥルクって書くとこの人は出演しないと理解できるけど、研究員だとそもそも何をする人なのかもよく分からない。
竹田: 工場長に工員に研究員。それはどこか工場での組織図とダンスをつくるためのチーム、あるいは座組みを重ねて、それが作中の役名でもあるけど制作上の役割分担でもあるということでしょうか。実際のクリエイションは、振付家とダンサーとドラマトゥルクという役割ですすんでいるのですか。
中間: そうなんですけど、ただその振付を行う存在っていうのが、この4人の中にはいないんです。
竹田: おや。いないのですか。
中間: はい。というのも、私はその動きとか、出てきたものに対して、まぁ演出といっていいのか、編集みたいなことはするんですけど、その動き自体を振り付ける存在っていうのがまた別にいるんです。4人以外に。
竹田:なんと。4人以外にですか。昨日ちょっとお稽古を拝見しましたが、工場での作業の動き、それをそのままやっているのかなと、それが振付のオリジンであって、それを実際の稽古場にもってきて編集しているということではないのですか。
中間: ではないんです。
— ダンスというものが日常のどんなところに潜んでるか(竹田)
— 振付を行う者と、振付られているカラダとっていう関係性がみえること(中間)
竹田:ではあれは作業の再現ではなくて創作した動きなんですね。この労働しているときのカラダにダンスとしか呼ぶことのできないあるカラダの瞬間を見つけたという話ですが、着眼点としてとても面白いと思います。ダンスというものが日常のどんなところに潜んでるかということを発見する目がここにあるなと思います。ただ工場の働いているカラダというのがいまの社会的な文脈で言うと、例えばある牛丼チェーン店の従業員が作業中の動きをすべて規定されている、物を運ぶとか給仕をするとかの逐一の動作が全部秒単位で決められているという話がありました。これなど広い目で見るとまさに他人のカラダを振付ている状況と言えるけれど、それはむしろ批判的な視点で語られますよね。要するに、効率一辺倒で動かされているその人自身のカラダというものは全く当人から疎外された状態にあるわけです。ところが中間さんが瓦せんべい工場で発見したカラダというのはそういう悲観的な感じではなくて、むしろそこにこそダンスらしい何かがあるということですよね。そこが面白いなと思っています。抑圧されているとか強いられているというよりむしろそこに積極的なダンス的なカラダがあるのだという。
中間: わたし結構強いられてる感じのカラダも好きなので。強いられてるっていうよりも、振付られてるカラダって言ったらいいんですかね。そういうものが見えることが自分の好みとしてあるなと思います。さっき仰っていた牛丼屋で何秒単位で行われる細い動きやカラダ自身のこともそうですけど、周りの環境とか、なんて言ったらいいんでしょうかね、他人に言われて出てくる動きであったりとか、その他人の言葉にリアクションするための動きっていうことだけではなくて、例えばモノに適応するカラダの形であったり音とかも振付と呼びたいっていう気持ちがあるので、そういうものを含めた振付られている抑制されているカラダっていうものに興味があるのかなと思います。
竹田: そこを取り出していきたいと。何か、こう、カラダを取り巻くモノや環境、条件といったものに動かされる、振付けられていく様子を取り出して舞台でみせたい、ということですね。
中間: 振付を行う者と、振付られているカラダとっていう関係性がみえることを私はダンスと呼んでいるんだろうなって思うことがあります。
竹田: 必ずしもカラダへの直接の指示だけではなくて、社会の様々な関係性から作用が及んで今このカラダの動きを決定しているというような、そんな感覚を想像していいでしょうか。
中間: そうですね。
竹田: すごく面白い、広がりのある視点だと思います。
上野愛実『談話室』
— 昼間はあんなに楽しそうなのに、なんで同じ場所やのにこんなに悲しい感じがするんやろうと思って(上野)
竹田:さて今度は上野さんの作品について伺っていきます。やはり新長田で生活する中で、ふと目にした情景からイメージを膨らませたのだろうなと思うのですが、どんな作品になりそうか話して下さいますか。
上野:新長田って、地下街にスーパーが多いんですよ。よく地下で買い物をして、そのまんま次のスーパーに行って、そこで何かを買って地上に上がって帰るとか、そういう事が多くて、しかもそのスーパーとスーパーを行き来する中に、談話室みたいな、机と椅子が置いてあるところが結構たくさんあって、必ずおばあちゃんが、もしくはおじいちゃんが溜まってる。もしくは一人で座ってるのをいつもよく目にしていて、それが結構印象に残ってたんですよ。それで、ある日一人で夜歩いていた時におばあさんが一人でベンチに座ってタバコ吸っていて、なんか結構それが意外やったっていうか、昼間はあんなに楽しそうなのに、なんで同じ場所やのにこんなに悲しい感じがするんやろうと思って。それを見た時に自分の過去を思い出して、私の過去と新長田のあの夜にいたおばあさんって、すごく似てるなと思ったんですよ。孤立している感じが。同じ場所やのにまったく別次元にいるような、なんか追い出されてしまった、孤立していく存在みたいなのを感じて、じゃあこれをテーマに作品をつくろうとしたのが始まりですね。
竹田: 情景をキャッチする視点が独特だと、そこから何かしら想像や妄想が始まりそうですね。
上野:そうそう、勝手に想像して、「この人家帰って何してんのかな」とか、「なんでわざわざこんなところでタバコ吸うんやろ、どうして家じゃあかんのか」とか、「よくダイエーでご飯食べてる人もなんで家で食べへんねやろ」とか、ほんとに家の延長線?家からこのダイエーまでが廊下みたいな感じで、ここか食卓?みたいな、普通に家で過ごしているみたいに食べて、またお家に帰って行ったりとか、なんかそういう境目がよくわからない感じ。
竹田: 新長田の特徴かもしれないですね。
上野: それがすごく印象的で。
竹田: タイトルの「談話室」、そこから来てたんですね。上野さんの作品には、不思議な世界があって、この作品は『コンテンポラリーダンス@西日本版』で今年の秋に一度発表されていますよね。それを拝見した時も、全体的なトーンはひたひたと静かなのですけれど、そこからなんともいえない不条理感がにじみ出てくるというか、そのテイストは、ダンス留学の成果作品にもやはりあったなと、もう上野さん色満載な感じがするんですね。今回のフライヤーに書かれている作品についての文章も、風景を眺めている眼とか、それを自分の過去や内面につなげていく回路とか、それを語る言葉が、あたかも詩を読んでいるような…
上野: 作品コメントは4回ぐらい書き直しているんですよ。結局あれに行きついて、あれが一番自分に馴染んでいるようで。
— ずーっと時間を持続させることで少し日常と違う別の次元に引き込まれていく(上野)
竹田: 今のところ、作品はイメージしたことに近づいて、それを表現できている手応えはありますか?
上野: いやー、五分五分ですね。なんか、うまくいってる部分もあるし、まだまだやり方を試していかないといけない部分もあります。
竹田:上野さんの作品でもう一つ面白いと思うところは、いつもバレエの影響、というより、その語彙をもろに引っ張ってきて素材として使ってしまう感じですね。自分のルーツはここにあるよと拠り所にしながら自分を表現するというよりも、もっとずっと冷徹な目で色々な素材のひとつとしてバレエのテクニックも持ってきて操作しているというような。そういうところがある気がするんですね。今回もつま先で立ってひたひたひたひた、と…
上野:パドブレ…
竹田:そのパドブレの動きがベースにあって、その上に自分でつくったいろんな振りや、椅子が意味ありげに配置されていたり、移動されたりということがあると思うのですが、バレエのパドブレ、左右のつま先を交互に細かく動かしてヒタヒタと移動しますが、つま先で立つこと、ポワントと言いますね、あれはもともと重力を感じさせない存在ということを表すのだと思いますが、上野さんはもうはじめからその意図でつくって使われていますか?
上野:どっちかって言うとあのパドブレは強制的な感じで、もっと縛るためのもの?
竹田:そちらの意味なんですね。
上野:私はもともとバレエは好きではなかったので。毎週火曜日にバレエに行ってたんですけど、今でもその火曜日って言うだけで気分が落ち込む。「もう、火曜日なんて来なければいいのに」なんてずっと思いながら小学生時代とか、中学生の時とか過ごしてたんで、今回は自分の過去を使うということもあったので、特にその嫌いだったバレエのパドブレって言う要素をそんな得意じゃないんですが、この中に縛るもの、ルールとして入れ込んでみようかなと。
竹田: 身体の規範みたいなものでしょうか?そのルール、規範で身体を縛っている状態でヒタヒタと続く、そこから何かいろんな動きが出てくるというのは、その動き自体がとても面白いと、すごく独特な動きをつくっていらっしゃるなと思いますが、それは、縛られた規範に従っているところから逸脱するとか、ほころびからこぼれ出てきちゃったとか、そういうものだと思って良いのでしょうか?
上野: バレエをやっている時は、あんな動きは絶対に許されない。私は最初登場するシーンで「こうやって出たいんですけど、こうやって良いですか」って先生に言ったら、「絶対ダメ」って言われて、「あー、なんてバレエって堅苦しいんだろう」って。私はこうしたいのにみたいなのがあったのに。その時の私が実感を持って踊れる振り付けを選びたかった。そういうものをやりたくてコンテンポラリーダンスを選んだし、なんか今回の作品の中でもバレエみたいなもの、そうやって縛られたものの中から漏れ出てしまうとか、隙間に落ちてるものを掬い上げるような、なんかそういう振りは絶対に入れたいな、と思って。
竹田:パドブレそのものが伝えるカラダの印象というか、作品のトーンというものもあって、あのように動かぬパドブレでヒタヒタヒタヒタとずーっと時間を持続させることで少し日常と違う別の次元に引き込まれていくような、別の時間に移行していく方法のひとつとしても読み取れるのかなと思ってみていました。上野さんの独特なつくり方だなといつも思います。前回の作品でもそういう規範に対してこぼれ出てくる得体の知れないものっていう対比があったので、その辺をやはりしっかり意識的につくってらっしゃるんだろうなとわかりました。
—「おもしろくない」って言われました(笑)。(中間)
竹田:では、その作品が今どの辺まで出来ているのか。先週の水曜日にワークインプログレスでいろんな方に見ていただく機会がありましたね。『踊りにいくぜ!!セカンド』の中のすごく特徴的なプロセスで、そこがプロジェクトの肝になるところ、すごく重要なプロセスのひとつだったと思います。ワークインプログレスを経て、どうでしたか?中間さんからお聞かせください。
中間:ワークインプログレスでみせた時は舞台も客席も含めてアクティングエリアを作って、観客がそのまわりを囲むような形の設えにしたんですね。その見せ方っていうのがこの作品にとって一番重要なもので、こうでなければならないと私はずっと思ってたんですけど、実際にお客さんを入れてみると意外にそうでもなかったなという。
竹田:そうなんですね。
中間:拘りが結構あっさり取れました。
竹田:今現在は、それから一週間と少し経っていますが、どんなことに取り組んでいるところですか?
中間:具体的なことでいうと、作業をしている中で、あ、私たちは稽古のことを「作業」って呼んでるんですけど。その作業の中で、なにかをつくっているように見えるシーンがあるんですけど、そのシーンと対比してサンバを踊るっていうのをこれまで何回か試していたんですね。
竹田:踊りのサンバですね。
中間:そうです、陽気なやつですね。それを試していたんですけど、サンバを入れるとそれまでやっていた作業の動きが一瞬で吹き飛んでしまう。サンバのイメージがあまりにも強すぎるっていうことが作業中に起きたので、「じゃあサンバはなしだね」ってメンバーと話して、この間は作業のシーンだけを20分間みせたんです。でも、ワークインプログレスを経て、そのサンバがまた戻ってきました。
竹田:そうですか。それは誰かからサジェスチョンがあったのでしょうか。アドバイスとか。
中間:色々意見を聞いてるなかで、いや実は作業している時にこういう案もあってっていう話はしました。そうしたら意外と「なんでそれやらなかったの?」って言われることが多かったのと、「なしだね」と言いつつも私はずっとサンバをやりたいっていう気持ちがあったので、「じゃあもうやるしかないよね」ってなりました。
竹田:拘ったり、悩んだりしていたことに弾みがつくということ、背中を押してもらうような機会だったようですね。
中間: そうですね。はい。
竹田: 逆に厳しい指摘ってあったりしましたか。
中間: ありました。「おもしろくない」って言われました(笑)。
竹田: それは厳しいですね。
中間: でも作品をみせて感想をもらうときに「面白くなかった」って言ってくる人って意外といないなって思うんです。
竹田:(大きく肯いて)そうですね。
中間: まだまだ完成形とは遠い中途半端なところを他人にみせて、それに対して感想をくださいっていうことは心苦しいです。でもそれに対して「面白くなかった」ってはっきり言われると、やっぱりめっちゃ悔しくて、火が点きました。
— 今回はある発作のための準備を粛々と進めていく感じ(上野)
— 不条理感、それがなんなのかというところまで伝わるような工夫を(竹田)
竹田:上野さんはどうですか?ダンス留学で一緒に作品をつくった仲間同士は色んなことを言い合ったり、ダンスボックスのスタッフの方たちや近しい方たちから意見をもらえることはこれまでにもあったと思いますが、例えばJCDNのスタッフの方からも途中経過としてみていただいた訳ですよね。
上野:とりあえずひとつの流れとして皆さんにおみせして、基本的にどんなことを考えたかとかどんなことを想像したかっていうのを中心に聞いたりしました。
竹田: 意図は通じていましたか。
上野:それが結構、他人に頼りすぎてるなっていうのが今回の発見でもあった。それと、私自身が勝手に想像しすぎ。自分で踊って、自分でつくってるんで、すごい自分の感覚にかなり偏りすぎていて。もちろん演出助手もいるんですけど。その子ともちょっと似ているところがあるから、2人して同じように偏ってしまっている。もっとわかりやすくしたい訳じゃないんですけど、わかりやすいラインみたいなものもつくるべきかもしれないっていう風には思いました。
竹田:「わからない」って言われたんですか。
上野:自分自身で通しの映像をみて、これじゃ私の言いたいこと全部伝わらないなって思ったんです。このままでは。
竹田: 全体的に独特で静かなトーンがありますが、動きの面白さだけでみせようという作品ではなく、街の中で垣間見た時間の不思議さというか、やはり伝えたい内容があるわけですよね。そこをどう伝えるかというのが、思ったようにあまり出ていないのではないかということなんですね。演出助手の人とは似ているのですか。
上野: そうかもしれない。的確に言ってくれるんですけど。ずっと淡々とみてられる作業みたいな動きなんです。でもそれだけじゃみてられない人っているじゃないですか。その繰り返しの作業みたいなものが。その狭間ですごく揺れてるような感じ。
竹田: 動きというよりは、構成で変えていこうと思っているわけですね。
上野:振付自体もなんかまだ即興の部分がたくさんありすぎて。完全振付にしたいんですよ。それも混ぜてその構成の中でもっと生かす方法があるんじゃないかなっていう考えが。
竹田:すごく拘りがあることもわかりますし、自分の世界もしっかりあるということも分かります。そのことが感覚でわかるだけではなくて、ドラマツルギーとしてしっかり伝えるべき作品だろうなと。動きの面白さだけでつくる作品ではないだろうなと思います。なんとなく不条理感とかそういうものは伝わってきますが、それがなんなのかというところまで伝わるような工夫がなにかひとつ必要かなと。「談話室」について上野さん自身が書いている言葉が拘りをもっている感じなので、そこを是非。でも、理屈で分からないことがあっても最後に観た人がなにか、「あ、そうか」って腑に落ちる瞬間があるとグッと印象に残る作品になるんでしょうね。
上野: そうですね。今回は特に物語があるような感じがあって。魅せたいこともかなりはっきりとしています。いままでは淡々と平坦な道の中を探していくという感じだったのですが、今回はある発作のための準備を粛々と進めていく感じですね。
竹田:演出助手が中根千枝さんですね。2人で作業をされていますけれど、このチームでは、今までと違う作業をしていかなければいけないということですね。
上野:昨日初めて中根さんに椅子を動かしてもらいました。そして、私は座ってみている。いつも私がやってたんですけど。「あぁ、全然違うな」って感じでしたね。映像でみててもこんなに情報は伝わってこないし、もっと細かいことに気づいたり、もっと大きなことに気づいたりみたいな。やっぱりやってもらうべきなのかもしれない。
竹田:今変えなければいけないという課題が目の前にあったら、やり方自体を変えていくということも必要なのかもしれないですね。今まさにチャンレンジしつつあると、昨日拝見した稽古ではその真っ最中だったのですね。椅子の位置について拘っていらしたので、そのような構成上の壁にぶち当たってるところなんだろうなと思って見ていました。
— 「Cプロ、ヤバかったね」ってなったらいいのにって(笑)(中間)
竹田:中間さんはワークインプログレスで背中押してもらったり、拘りがとれたり、このままいっていいんだって思うところがあったということでしたよね。昨日私が拝見したのは工場での作業をしている部分ですか?某番組の主題歌が聞こえてきましたが(笑)。
中間:昨日はすごく有名な曲を使って試していました。
竹田:昨日、研究員の藤澤さんと話したのですが、歌(作業歌)を入れたいと仰っていました。近代の工場労働者は規律に従って動いていますが、それ以前の、例えば「家内制手工業」の時代には、機械や効率優先のリズムではなくて、みんなで気持ちを合せて歌を歌いながら作業をしていたのではないか。そういう時代があったのではないかと。そこから作業歌というアイデアが出てきたそうで、興味深いなと思いました。
中間:歌うシーンを入れたいというのは最初からありました。研究員の藤澤が調べた話によると、作業歌っていうのはその労働の場で生まれたものだけじゃなくて、その当時の流行歌だったり広く知られているものを歌うっていうこともあったと。そういうこともあるし、なによりあの歌詞はすごく的確なところをついているんじゃないかって私は思うんです。
竹田:最後にもう一つ!聞いてみようと思っていたことがありました。お2人とも新長田のダンスボックス周辺でずっと活動されていますが、今回の『踊りにいくぜ!!セカンド』のAプログラムは、梅田宏明さんと山崎広太さんという主に海外に拠点を得て活躍しているベテランのアーティストですが、そういう方達と一緒にプログラムされていることで何かしらお2人は刺激を受けることがあるのではないかと、期待しているのですが。こういう方々と同じ公演にプログラムされて同じ舞台を経験できるというのは、どうでしょう?
上野:まったく未知の世界って感じしますけどね。だって大学生の時に映像でみていた山崎広太さんと一緒の舞台にのるなんて。一体それってどういうことなんだろうって。
上野:気は引き締まります。すごく。
中間:「Cプロ、ヤバかったね」ってなったらいいのにって(笑)
インタビュアー:
竹田真理
関西を拠点に活動するダンス批評家