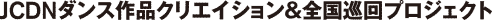2016年01月20日
インタビュアー:海野貴彦
同席者:高橋砂織(dagdag)、赤松美智代(dagdag)、井藤英晴(道後館取締役支配人)
テープおこし:佐野和幸
日時:2016年1月14日(木)
場所:温泉旅館 どうごや
海野:まず余越さんの経歴から聞いていきたいと思います。
![]()
余越:広島県の三原市で7歳からバレエを始め、15歳までやっていました。そして高校は剣道部にいました。
![]()
余越:剣道が私の身を助けることになるんですが、その後、大学受験に失敗しまして。
![]()
余越:そうですね。15歳の時までバレエをしていましたが、当時の日本の状況を考えるとダンスでは生きていけなかった。わたしの周囲には振付家なんていませんでした。それで15歳になって高校受験が始まるころに、バレエはやめなさいと(親に)言われ、やめることに。そして、どうしようかなと思って、体を動かすことが好きだったのもあって剣道を始めたんです。その後大学受験に失敗し、東京の語学学校のバイリンガル秘書科に進むんです。
![]()
余越:Bilingual secretary。バイリンガル秘書になろうとした。私の性格を考えたら、日本の企業で働くのはちょっと無理だろうと感じていたんですね。それでバイリンガル秘書科に進み卒業するんです。当時結構英語がしゃべれたんですが、もちろん、ネイティブのようには話せない、話せなければ第一線の秘書にはなれないと思い、それで親に頼んで、留学を目論んだんです。80年代だったので留学が流行っていて、アメリカには日本人留学生が多かったので色々大学を探しました。親の許しを得て、1年短大へ行かせてもらえることになったんです。大学のアドバイザーに呼ばれて、君の英語はちょっと問題だから、体育の単位を取りなさいと。選択肢は、バスケットボール、バレーボール、水泳、その他もろもろあって、その中にダンスがあったんです。その学校がダンスはとても盛んな学校でして、マーサ・グラハムっていう20世紀の巨匠がいるんですが、その大学のダンスの先生がマーサの写真を見せてきて、「この人を知っているか?」と聞いてきたんです。そして、私は「知らない」と答えると、先生から、バレエをやったことがあるのに、この人を知らないのかとびっくりされて、君は絶対ダンスをやるべきだと言われるんです。マーサ・グラハムは裸足で踊るんですが、私はバレエシューズを履いて踊ってましたから、えー裸足?と戸惑うくらいその頃は何も知らなかったんです。次の日オーディションに行って、バレエをやっていたことで、アドバンスクラスに入った。そして大学のカンパニーに入ることになって、そこからダンスの道にのめり込んでいくことになるんです。
![]()
海野:現在のダンサーがニューヨークに行く目的っていうのは、ダンサーになるってことだと思うんですが、そうではなく。
![]()
余越:全然違う。ダンスをやるとは思ってなかった。それで向こうでは、ダンスを本気でやろうと思った時に、ダンサーが職業として成り立つ環境があるんですね。
![]()
海野:バレエをやっていた時にいずれ職業にしたいなというのはあったんですか?
![]()
余越:ないですね。自分の周りにロールモデルがいなかったから。
— 舞台のこと現場で学ばないと、無理だなと思って、ダンサーとして出発した(余越)
海野:自分の自己紹介をします。松山在住、画家の海野貴彦(かいのたかひこ)と申します。なぜ、いま自己紹介を挟んだかといいますと、職業に対してロールモデルが無いっていうことについて、自分はもちろん画家っていうロールモデルも無いんですけど、今そのないモデルを実際松山でつくって、どうやって表現をしながら生きていけるかっていうのを実践している環境です。
![]()
余越:日本にはそういう芸術家として生きていく人があまりにも少ないので、私は海外でやってきて、おそらくニューヨークでなければ、振付家にならかっただろうし、なれなかったと思います。
![]()
海野:大学でダンスに出会って、振付家としてデビューしたのは何歳の頃だったんですか?
![]()
余越:ダンサーとして踊っていたのが15年くらいで振付家としてデビューしたのは、40歳くらいかな。まあ、そもそもわたしの頭の中には、振付家という概念がなかった。バレエは、古典芸能ですから、くるみ割り人形も白鳥も振付が決まっているんです。わたしには、このバレエをつくった人が昔いたんだ、というアイデアさえ、なかった。「振付家」の存在を知ったのは、4年制の大学に転入したときでした。その後、2年目に怪我をして、それと合わせてもうお金がなかったので、早く大学を卒業しないといけない。それで、ハーバード大のダンスのサマースクールに入った。しかし、怪我をしているからクラスが受けられないんですよ。それで困ったなとなって、クラスのガイドブックを見たら、「振付、コレオグラフィー」っていうワークショップって書いてあったんですよ。ダンスのつくり方を学びますって。当時コレオグラフィーって言葉さえ知らなくて、辞書で調べて、「振付」の意味を知って、もしかしたら足くじいててもいけるかもっていうのがあって、クラスに行きました。そこで初めて「振付家」というものが存在するのを知るんです。
![]()
余越:そう。でも大学で振付を専攻して私は振付家になるんだっていうのもあったんですけど、いざ卒業してニューヨークに行くと、振付家になりますっていっても、すぐにはなれない。これは業界のすべての仕組み。舞台のこと現場で学ばないと、無理だなと思って、ダンサーとして出発するんです。
— ソロだけだと何年もやってると耐えられなくなってくるんです(余越)
![]()
余越:大学はマサチューセッツ。そこからニューヨークに行きました。それでダンサーとして15年踊るんですが、いろいろな振付家のことを知りかったので、同じ人とは2回は組まないと決めました。
![]()
余越:そう。1人の振付家とやるとその人の癖がつく。それはなかなか抜けないんです。私は短大でやったグラハムテクニックから4年大に入ってやったリリーステクニックをやったときにものすごく苦労したんです。だからありとあらゆる動きをやるためには、ありとあらゆる人とやって動きをやっておかないと使えないなと思ったんです。
![]()
海野:もともと振付家を視野に入れてダンスをしている人って珍しくないですか?向こうでは普通ですか?
![]()
海野:そうですよね。ダンサーの方をリスペクトしているんですが、その尊敬している理由が、人生で身体の使えるピークって山の形みたいに放物線状になっているじゃないですか。その放物線をちゃんと見せるっていう生き方を選んでいる段階で僕にとって尊敬の対象なんです。さらに言うと、身体の放物線状の性質、その時間軸をずらして舞台に出る環境をつくりダンサーとして立ち続けるっていう生き方をしている人たちは、舞台に立っているというだけで尊敬の対象なんです。そうではなく、最初から振付家としてのちのちキャリアを行くんだ、って人に僕は今まであった事がありません。
![]()
余越:それって難しいですよね。私はダンサーとして長かったから、ダンサーに納得させる演出ができる。自分はダンサーだったけど、つくるってことが念頭にあるから踊れるっていうのもあるかなって思う。
![]()
余越:ソロだとその両面がありますよね。でもソロはとても孤独な闘いなのでソロだけだと何年もやってると耐えられなくなってくるんです。すると、やっぱりグループだよねってダンサーと作品を作る、その場合は作品に自分が入ると作品が成立しないから、私は外から見て振り付ける。すると、人とやってると疲れちゃうから、またソロかなってぐるぐる行ったりきたりだから、ダンサー/振付家かな、私は。
— 当時、リリーステクニックができなければ仕事がこなかった(余越)
海野:剣道はどこに活かされているんですか?
![]()
余越:80年代の後半、ニューヨークに行った当時活躍していた、トリシャ・ブラウンという振付家がいるんですけどね、その彼女の動きっていうのが完全なるリリースなんですね。当時、リリーステクニックができなければ仕事がこなかった。トリシャは、武道からインスピレーションを受けて動きを作り始めたんですよね。だから、私は剣道を知ってるから、重心を下げるとか、抜きつつ速く動くとか、対応していけたんですよね。
![]()
海野:ということは、剣道だけをやっていた時には気付かなかったけど、ダンスの世界から剣道を眺めたら、あーこういう動きをやっていたんだって後からわかったんですね。
![]()
余越:はい、それから話はグーと飛んで、2003年に私はアメリカからダンサーとして日本に留学してくるんですが、その時に日本舞踊の師匠に入門しました。それで歌舞伎舞踊素踊りを勉強をしていくんですけど、その時にすべてが繋がっていって、その時の先生がダンスをやってる人は日本舞踊をやっても全く形にならないのになぜあなたはできるのと不思議がられたんですよ。剣道をやっていたことと、アメリカでリリーステクニックを習得していたからでしょうね。
![]()
海野:聞いてておもしろいのは、余越さんは体を空き箱のように使いたいのかなと思うんですよね。
![]()
海野:いろいろ学んだ結果、自分がいかに空き箱でいられるか、こだわらないというこだわりですよね。ダンスにもいろんなジャンルがあると思うんですが、ジャンルがあるってことは、偏る。作家としても偏る表現の仕方をするのが普通だと思うんですが。
— アンタッチャブルなところをあえて触って表現する(海野)
— 自分のアイデンティティーを作品として出してもいい時代がきた(余越)
海野:僕の話で恐縮ですが、僕は画家として松山でやっていて、表現を“あおる”ってことをするんですね。この前、余越さんの作品の様子を見にいったときに、余越さんと積極的に関わりたいと思った理由があったんです。
![]()
海野:なにかアンタッチャブルなところをあえて触って表現する。僕の受け取り方としては、世の中が不安定だったり、そわそわしたり。原発だったり地震だったりね。そういうものを表現者として表現すれば、世の中を表現することだから、どうしても緊迫感のあるものを表現してしまうっていう触り方ですよね?表現に対して。
![]()
余越:あー、それはですね。私は、日本人っていうのと、広島出身っていうのが大きいと思う。
![]()
余越:アメリカに行くまでは全く意識がなかったの。行って、広島から来たって言うと、アメリカ人に「ごめんなさい」って言われるんです。
![]()
海野:一説では“仕方ないって”と“ごめんなさい”のアメリカ人が半々くらいだと聞いたことがあります。
![]()
余越:だいたい半々ね。でもニューヨークは「ごめんなさい」が多い。田舎の方はちょっと「仕方ない」が増えるかな、自分自身意識して思っていなくても、日本人であることを、背負わされるというか日本人であるってことは、必ずなんですね。で、ニューヨークでダンサーになった当時、ダウンタウンのダンス界には、私ともう1人しか日本人のコンテンポラリーダンサーはいなかったんですよ。だから、私に仕事が入ってくるのは、その子の仕事がぽしゃったらダブルキャストの形で私が踊るっていう。アジア人の体っていうのはあの頃特殊だった。
![]()
海野:その特殊で何年もダンサーとして生きてこれた理由を知りたいっていうのが今の質問なんですね。
![]()
余越:それは、時代があったと思うんですね。80年90年代の日本はバブルだったので、日本人が海外にわーっと進出していった。けれど、日本文化はまだ今のように浸透していなかったんですよね。だから、大学時代は日本人も韓国人も、中国人も同じという時代だったんですよね。それで、ダンサーになった時は、アジア人ダンサーがいないところで、なんていうのかな、最初はアジア人として踊るのはかっこよくなかった。わたしは白人に混じって、白人の文化の一部として踊る。しかし、時代が変わってきて、アジア人というのを出してもよくなってきた。それで、自分のアイデンティティーを作品として出してもいい時代がきた。日本から見たアメリカ、アメリカから見た日本という作品を出してもよくなった。行った当時はそれはあまりイケてなかった。ダンスを長くやっていて、状況が変わり、つくれる環境ができ、求められるようになり、賞をもらったりして、時代が変わっていった。
海野:向こうに行って、徐々にそうなっていったって感じですかね?今の世の中を表現するというか。
![]()
余越:いやー、自分もあおったかもしれない。それやばくない?ってものを。
![]()
海野:やばいっていうのは、世の中がやばい状態にあるとやばくない?ってものが生まれてきますよね。
![]()
余越:それもあります。たとえば、今回の映像、サリン事件、9.11。
![]()
海野:9.11の時はニューヨークに?そのときの表現っていうのは?
![]()
余越:シャッフルという作品があったんですけど、死者とコミュミケートするっていう、ちょっと危ない作品なんですけど、あれは9.11の直後。
![]()
海野:やっぱり当たり前に世の中にあることを、危ないというか、そういうあんまり触れられないようなところを、時と場合により表現しなきゃいけない状況っていうのがあるってことですよね?
![]()
余越:そう、あと私がメインストリームのものにあまり興味がないので。
![]()
余越:そうそう、そういうことに興味がないんです。だから、自分はどうしてもマイナーな方に目がいってて、そういう意味では、アングラ、、、っていうのかな?こっちにも文化あるよって。
![]()
余越:いやー、意識的にというか、そういうものに目がいくように生まれてきたのかなって思う。
— ダンスが、成り立つ。(余越)
海野:今回の滞在の目的である1月29日の公演、松山での作品制作について話にしていきましょうか。
![]()
余越:踊りに行くぜ!!に申請した時は、全く違う作品の構成でした。それで、だんだん作ってくると、偶然性が重なっていって、作品ができていって、あーこんな風になっていくぞっていうのがあるんです。そのことが私の作品には多いです。
![]()
海野:まさしくそれが今だってことですよね?その時その場にいて感じたものをつくって、今のものをやる。っていう。
![]()
余越:そうですね。自分の目の前に提示されてくるものについていく、力でぐいぐいと作っていくんじゃなくて、後ろから作品にお仕えして、あーそうですかーって作るタイプですね。
![]()
海野:振付家っていろんなタイプの人がいるでしょ。世間一般では、“こうである”っていう振付家が一般的じゃないですか?
![]()
余越:私は全然違いますね。予定調和は全くない。予定がないから(笑)
![]()
海野:で、把握した後、方向性はつけるんですよね?こっちの方なんじゃないかな、という作品としてたどり着かないといけないところまで行くには。
![]()
余越:はい。見たいものをつくっていきますよ。あらわれた素材に、これは違う!っていうのはすぐわかる。これだ!っていうのはなかなか出てこないですけど。
![]()
余越:リハのときは良くても、本番ぽしゃることも多いんですよ。私が見てるときに、起きた!って思ったことも、本番では起こらなかったり、ただ私が見てるものっていうのは、すごく特殊だからお客さん見てもわからないかもしれない。
![]()
余越:振付が仕上がったら、ダンスが成り立つって思いがちなんですが、ダンスは生ものだから、ライブだからダンスはなかなか成り立たないんですよ。生きてる人間が素材だから、生きてる人間がダンスだから、それがその舞台でちゃんと見えて、ダンスで時空を紡いでいくでしょ?だから、30分、1時間や100分の間、ダンスが成り立つっていうのがとても難しいです。
井藤:作品をつくるときっていうのは、海外に出てたら、日本人っていうのがあるから考え方も表現も違ってできるけど、日本に帰って来たら、感性が近くなり、誰かと合わせてしまうと、合わせるというものになってね、本当に自分がやりたいを表現した時に、熱が入る。僕はお茶をやっていてね、先生が構えたときに、かっこいいと思ったんですよ。シンプルなものをかっこよく見せるのは難しい。
海野:一見自由に見える表現は、ルールに基づいた担保があって、そこをどうやっていじっているかってこと。世の中にルールがあって、ここはいじられるところ、それが表現の隙間、っていうのかな。ルールと制約がないと自由はない。
余越:それはそうですね。制約が狭いほど自由になれるっていう、まあパラドックスなんですけど。
— 松山に二度と呼ばれないかもしれないけど(笑)。(余越)
— 二度と呼ばれないかもしれないけど、表現者としては正しい行い (海野)
海野:前に映像を見せてもらったときに、これが松山で伝わるかという質問を僕は受けました。せっかく松山でやるんなら、松山の人に目線を落とすのではなく、いつも通りのニューヨークや各地でやっているものをやるしかないですよ、という受け答えをやんわりしたのですが、それはなぜかっていうと、それでこそ余越さんが松山に今いる最大の意味だと思うんです。
![]()
海野:二度と呼ばれないかもしれないけど、表現者としては正しい行い。
![]()
余越:でもそこで悩むわけですよ。これやって生きていけるのか、もっと穏やかに生きる方法はないのかってね。
![]()
海野:それが僕がもっと関わりたいっていう理由の1つであって、30年間ニューヨークでなぜ生きて行けたのかっていうことを探りたかったんですね。その理由は、日本ではあまり居ないかもしれないけど、ニューヨークではダンスが“成り立った”という瞬間を見られる人、感じれる人が居るのではないか、さっき言っていた、成り立つという瞬間を感じられる人間が多い?
![]()
海野:職業として成り立っているから、共感できる人がいて職業としてちゃんとお金も回って、生きていける。
![]()
海野:日本ではない。ないと前提しましょう。もしかして観客、見てる側は、さっぱりわからないっていう危険性があるっていう話ですよ、これ。
![]()
海野:おいていく、ってなっちゃうけど、そのさじ加減と塩加減をどの程度やろうかっていうのが、この前僕にくれた質問だったんですね。ただ今回は、そのさじ加減と塩加減はなしでいきましょう。なぜならば、この現場ではこれが正しい、というか余越さんが松山に来ている意味はそういう事なのではないでしょうか。
![]()
余越:どうなんだろう。この「踊りにいくぜ!!」っていうのは、あまりにもダンスが世に広まらないので、ダンスってこんなに素晴らしいんですよっていう啓蒙も含めて地方に行っているわけですよね。だから、おいてけぼりの作品ばっかりつくったらお客さんがより少なくなる。
![]()
高橋:だけど、今回の余越さんの作品かっこいいんですよね。なんかかっこいい。
![]()
海野:そういったことを踏まえつつ、見に行くのがすごい楽しみ。

<温泉旅館 どうごや>
愛媛県松山市、道後温泉にありますこの旅館は、昭和初期の建物を愛情込めて美しく手直しした、「昔ながらの旅館」と「ゲストハウス」の良さを兼ね合わせて2013年に開業した旅館です。
ホームページ http://dougoya.com/
<「どうごやーと」>
どうごやで2015年10月9日~2016年3月27日までの期間限定で行われている、
どうごやの客室、全7部屋のうち、4部屋を全国から招集されたアーティストによって制作された部屋に、お客さんが実際に作品と触れ合いながら宿泊できるアートイベントの事。
「どうごやーと」に併せ「ゴロゴロナイト2」
https://www.facebook.com/events/1650086165259100/ と題された“ライブ型”のイベントも「どうごやーと」の一環として行われ、どちらもこの度、余越保子さんの対談者海野貴彦によって企画、構成、プロデュース、制作されている。
<井藤さんと海野くんのつながり>
井藤さんは、海野が愛媛で活動するうちに出会った海野の良き理解者。兼、飲み仲間。余談だが文中に出てくる“茶道”の師匠である中島宗津の共に弟子である。茶道では井藤は海野の兄弟子にあたる。しかも海野は態度があれで破門状態の上、ろくに茶道が身についていないのだが何故か中島宗津と井藤に良く可愛がられている。
インタビュアー:
海野貴彦(かいのたかひこ)
東京都生まれ。画家。
2012年愛媛県松山市に移住。現在は松山市の三津浜という海沿いのまちから日本を盛り上げるべく、全国各地を演歌歌手さながらに渡り歩き、作品発表を続けまちおこしならぬ「ひとおこし」に全身全霊を捧げる。海野がいる所が、いま一番面白い所とされている。得意なスタイルは「そこでしか出来ない、そこの最大公約数で制作する」こと。主な使用画材は「絵の具」そして「人」。絵の具でキャンバスにえがき、人でまちをえがく。まちの彩りになる事も含めて「画家」と名乗る。
表現方法は、絵画制作、ライブパフォーマンス、プロジェクト制作、デザイン、講演、執筆、TV・CM出演など多岐にわたる。
2015年の主な活動
・展覧会、「激情」@island 東京、「どこぞ、だれぞ、なんぞ、」@愛媛県三津浜、「Paio2」@愛媛県道後。
・滞在制作、「椎名町サロン」@東京都豊島区、混浴温泉世界「わくわく混浴デパートメント」@大分県別府市、吹上ワンダーマップ @鹿児島、天文館ワンダーマップ @鹿児島。
・制作、「Say YO?」 -東京を捨て、西予に受け入れられる- @愛媛県卯之町、
「どうごやーと」 @愛媛県道後、「混浴温泉世界・大大大大大フィナーレ」、
・TV出演「新昭和」企業CM、NHK「U29」、他新聞・雑誌取材、掲載など多数。