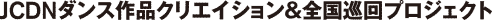2016.03.13
Aプログラムの3作品の上演が、最終公演地東京を残すのみとなりました。
どうぞお見逃しなく!
3作品に寄せられた作品解説・レコメンド・談話などをご紹介します!
梅田宏明作品『Movement Research – Phase』
【文:飯名尚人/映像作家・演出家】
僕なりに解説するならば「雨粒が空間を漂う規則性」と「人間の踊り」を同じレベルに置いて、人間も自然の一部なのだ、という自然回帰とも言えるダンス作品である。人間が自然の一部である、と芸術表現において挑むとき、例えば「太陽の恵み」「緑の大切さ」「動植物との共存」、、、といった人間目線のナラティブな解釈において作品が創造されるだろう。時にそれは教条的な意図に成り代わり、芸術表現とは素晴らしいものだと盲信させる。梅田宏明は、そういった既存のヒューマニズムから一線を画す。離れようとする。喜怒哀楽に溺れることを許さない。自然とはそういう厳しさのことなのだとも思う。雨が降ってるから哀しい、なんてことは、人間が勝手に思っているだけのことだ、というのは正しい。だからダンスも自然に近づくために、喜怒哀楽から逃れてみようじゃないか、という実験にも見える。人間も自然の一部なら、感情ではなく、人間なるものを構成する細胞にダンスさせよう、ということではないか。ふと荒川修作を思い出す。ノーベル賞を受賞した利根川進に向かって「君はまだ人が死ぬだなんて、考えているのか?人は、死なないんだよ」とけしかける。人は死なない。確かにそうかもしれない。人を個人として考えれば、ある人の死で哀しみに暮れることもある。しかし、人を自然の一部と考えれば、人の死は悲しいとかそういうことではない。それは非常にドライでクールな見解だと思われることも多いけれど、僕はその考え方が好きである。
無秩序の秩序、というのは自然科学の領域だろうか、雨の一粒一粒はどんな規則で降っているのだろうか、ああみえて規則がないわけがないだろう。木の葉が風に巻かれて舞うときに、葉の動きに規則があるだろうか。人間はあんな風に群舞できるだろうか。できないはずがないだろう。花は自分が美しいと思って咲いているのだろうか。自然のルールを人自身も作れるだろうか。しかも人間目線ではなく。デジタルの究極はアナログである。ぽつんとした空間の中で4つの「人」という個体が踊る。そういう作品である。

八戸公演 photo:naoto iina
平井優子 『Ghosting―軌跡の庭』
【文:佐々木治己/劇作家】
「誰かいる」そう思いながら、そわそわする気持ちで舞台を見ていた。どこからか声が聞こえているのだろうか、地中から声が聞こえている? いや、そんなことはない、設備の整った室内の舞台機構に地中へと突き抜ける場所などはない。にもかかわらず、ふいと地中を考えた。照明がぴかぴかと光る。それはきっと照明の伊藤さんがぴかぴか操作しているに違いない。だけれども、勝手にぴかぴかと照明自体が反応しているように思えた。煙が出てきた。きっとスモークマシンで煙を焚いているに違いない。けれども、どこかから自然に湧いているように思った。客席にも侵犯してくる。音、光、煙が、舞台を超えて、やってくる。そして、そこには「誰かいる」。
平井作品を見ながら思ったのはそんなことだった。舞台効果の嘘ごとに飽き飽きとして、イリュージョンなんて下らないとそう思って舞台に関わってきた。しかし、平井作品の中のイリュージョンはそわそわさせてくる。舞台の中にある対立要素が未解決のままにそこにあり、舞台と客席の敷居を舞台効果が越えてやってくる。
例えば、光と闇、例えば、生と死といった呆れるくらいシンプルな対立は、それを対立として見てしまう見る側の欲望を巻き込みつつ、平井優子は当事者でもあるにも関わらず、観測者としてそこにいる、踊りながら。
踊りとはなんだろう、「私は私の体を律することによって私とも無関係になってしまう。」そう知らされるような踊り。対立構造を解決するわけでもなく、光と闇に寄り添いながら、生と死を傍らに見つめながら。平井の踊りは、私には見えない誰かと踊っているように見えた。そこには「誰かいる」。

松山公演 photo:一楽-ichigaku-
平井優子 『Ghosting―軌跡の庭』
【文:みずのりつこ/「踊2」プログラム・ディレクター】
タイトルの「Ghosting」は、聞き慣れない言葉だ。どうも最近できたトレンド語らしい。ネットのSNSなどの世界では、気に入らないことがあると簡単に人と連絡を絶ち、人間関係を一方的に終わらせてしまうことができる。さっきまで会話していた人が、突然、消えてしまうことを“Ghosting=幽霊になる”と言うそうだ。これを知るまでは、Ghostingには幻想的なイメージしか持っていなかったので、こんな風に社会的な意味合いがあることに驚いた。平井さんは、どちらかというと古風な佇まいの淑女という雰囲気なのだけど、このタイトルのつけ方にも表れているように、古い価値観を大切にしつつも、現代社会を敏感に察知して、コネクトすることが得意な作家なのだろう。
童話「ナルニア国物語」では、洋服箪笥の奥や、壁にかかっている1枚の絵が、あっちの世界の入口と繋がっていたように、この作品では、「私」と「もう一人の私」のダンスが、その装置の役割となり時空を飛び越え、不在者の影を追う。音・光・映像が舞台作品版の極上のエンターテイメント力を発揮し、現代のおとぎ話を描きだす。平井優子の影と戯れる白い肢体を見ていると、闇から聞こえてくる囁き声にいくつかの死生観を想起させられた。 たどたどしい日本語の囁く声は、コミカルでもあり怖くもあり、現代のおとぎ話はブラックユーモア的な世界であることを暗示している。
縄文時代も、人は今と変わらず手を組んで空を見上げ祈ったように、これだけ文明が闇を無くしてしまった現代でさえ、私たちは不在の存在に目を凝らし、期待し、怯え、寄り添って生きたいと願う。平井さんが舞台に描こうとした庭とは、ひょっとしたら、誰もが心に持っているGhostに会える場所、秘密の庭ならぬ、秘密の闇だったんじゃないだろうか。
山崎広太作品『暗黒計画1~足の甲を乾いている光にさらす~』
【談話:大谷燠/DANCE BOX executive director】
山崎広太作品は、誰も触れなかった<暗黒>について独特のアプローチをしている。今、何となく出来てきたコンテンポラリーダンス界というものの中で舞踏とバレエを経験して、コンテンポラリーダンスをやっている山崎広太という人が<暗黒>というものにトライしているということ。踊り手にも自由度があり、身体が生き生きしているのは、観ていてとても面白い。
山崎広太という人は普遍的に15年前から変わっていないように思う。何を言っているか分からなくても、彼の中では辻褄が合っているようなところがある。 踊りながら何かを発見していく、身体で思考するような、稀な才能を持った人だと思います。
「自分の身体の中には先祖やこれから生まれる人たちの記憶が入っているかもしれない」と話しているように山崎広太さんにはこのような、『踊る哲学』があるのだということを、見ている人には発見してほしいなと思います。そして、今の若いアーティストにも『踊る哲学』のようなものを持ってほしい。哲学がある作り手って強いですよね。
***********************
山崎広太作品『暗黒計画1~足の甲を乾いている光にさらす~』
【談話:ダンス批評の竹田真理】
山崎広太さんのダンスは、ギアを軽くして踊る身体と、反対に重心を落として粘り強く質量をともなって踊る身体、その大きな振れ幅が魅力だと感じます。今回の作品ではご自身の言葉で「スキゾフレニック」と言われる通り、分裂的に、拡散していってしまうような質感があって、たとえば途中のMCでも、言葉がやっとの思いで追い付いていくような語りのスピード、リアルタイムの思考の速度がすごく早い。踊り自体も風に転がされていくような、都市から都市、フィールドからフィールドへと疾走している感じがありました。その速度で日本のコンテンポラリーダンスシーンを引っ掻き回してくれる存在。ニューヨークの風を感じました。
出演の西村未奈さん、武元賀寿子さん、笠井瑞丈さんによるパフォーマンスも密度があって素晴らしいです。それぞれのジャンルで踊って来たダンサーの異なる時間が舞台にあって、重く均衡している。そこを山崎広太さんが速度を体現しながら踊っていく。とても見ごたえがありました。
作品は舞踏への応答でもありました。土方巽の引力から自由になろうとしながら、周囲をめぐり続け、様々なキーワードが飛び交います。暗黒舞踏と宇宙のブラックホールを重ね合わせ、インスピレーションでガツッと世界観をつかんでしまう握力、直感的につかむ思考の運動神経、そこが何といっても山崎広太さんの魅力ではないでしょうか。がっちりしているのに尻軽である。キャリアを積んで、自分を失くすくらい踊り込んできた人が初めてつかめるような、速度と軽さではないかなと思います。

札幌公演 photo:yixtape
***********************
山崎広太作品『暗黒計画1~足の甲を乾いている光にさらす~』
【詩:佐々木治己/劇作家】
「暗黒計画へ」
体には記憶があって
私はこの様に在るのだと
決定されている
私の寝言も、歩くときの足も
まばたきも、髪をくしゃくしゃにする手も
私として在るのだが、
それは記憶だった。
滅亡の、滅亡が、決定された
体の記憶
抗いも、慈しみも、暗黒の徴
私はなぜ在るのか!
涙がこぼれる
嘆くでもなく、拒むのでもなく
粒子の揺れが連なり波のように
物質が持つ記憶に暗黒を見つける
暗黒が体を求めている
在るべきだと放射される
体は要請された
滅亡の記憶から、私として、私の体として。
***********************
山崎広太作品『暗黒計画1~足の甲を乾いている光にさらす~』
【文:みずのりつこ/「踊2」プログラム・ディレクター】
ダンスというものが、言葉で説明しきれないところで存在するとすれば、それは、まさに今回の山崎広太作品のことに違いない。毎回観るたびに文句なく、ダンスと生きることの肯定さに心が興奮する。
「自分の人生の転換期には、いつも舞踏がある。これはまさに僕の転換期の作品です。」と山崎は語る。舞踏譜を初めて書いたという山崎広太が、舞踏を初めて踊るダンサーに託す。西村未奈・武元賀寿子・笠井瑞丈の舞踏は、いわゆる“舞踏”というイメージとはま逆で、驚くほどカラッとしている。こんなにもカラッとした体はそうそうお目にかかれない。“からっぽの体”が踊っている。だからこそ見えてくる風景が雄弁に語りだす。
作品中に散りばめられた言葉と、どこまでも無秩序な舞踏、時間と空間が勝手にそこらへんに浮かんでいるような開き直り感―そのどれもが居心地良く自由に存在している。
今、話題の米国ポップシンガーSiaの歌う「Alive」「Bird Set Free」の歌詞は暗黒だ。暗黒を絶叫するソウルボイスと、4人の舞踏が衝突する。暗黒は生と死をひっくるめて無限の闇として広がっていく。土方巽が暗黒舞踏と名付けたのはこのことだったのだろうか。舞踏というものが死語ではなく、今日、生きた舞踏になる瞬間。西村未奈と山崎広太が、正反対のダンスを踊る。この世界は何と言えばいいのだろう。ただただ生きることが、ダンスになる瞬間だった。闇、暗黒、恐るべし。