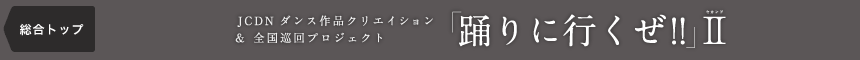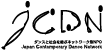再演について
TEXT:國府田典明
踊りに行くぜセカンドには「再演」という上演枠がある。
踊りに行くぜ”セカンド”とは(何度も書いているが、、)。ダンス作品のクリエイションプロジェクトである。作品を作る事に重きが置かれた企画である。作品制作において、この企画のおよそ10ヶ月というのは短い時間だと思う。あくまでも、「作品構想を実現し、人目に触れるところ」の最低限の機会がこの踊2では提供される。スタートアップし、その後その作品が成長していく事を主催者は願っている。その一端が見えるのが、この「再演」という上演枠なのではないだろうか。(ここでいう再演とは、踊りに行くぜセカンドで制作された作品を、制作年度以降に踊2で再度上演するという事。)
再演作品は、作者は既に一度”完成”したものに取り組むので、当年の作者に比べれば精神的に余裕がある。主催者としては、興行的な観点では、完成度の見通しがついている作品である。これは、作品を育てる機会としても捉えられるのではないか。この企画は助成金の力が大きく、年度区切りにせざるを得ない制約がある。その中では、作品に時間をかけるいい方法だと思う。再演が保証されている訳ではないが、良い作品であれば、さらなる上演機会を与えられる可能性があるという事だ。
さて、Vol.4では、村山華子さん、菅原さちゑさん、青木尚哉さんの3作品が再演された。先に”完成度の見通しがついている作品”と記した。ただ実際には、再演とはいえ身体表現なので、その”再現性”は作品の性格による。何をもってその作品と成り得るのか。ダンス作品とは、シナリオなのか、舞台上の身体なのか。身体表現特有の問題かもしれない。
村山さんの作品はシナリオ的であり、そのストーリー・場面で描かれるテーマが作品といえる。台本に作品の重きがある。出演者が変わっても成立するのかもしれない(村山さん自身が踊るシーンを除いて)。そのような点では再演しやすそうだ。
一方、菅原作品、青木作品は、舞台上の生のやり取りに作品性がある。
菅原作品は、お客さんとの空気づくりで見え方が変わってくる印象。特にお客さんの言葉の受け方でも変わってくる。笑いから勢いを見せる時もあれば、冷笑から葛藤に見える時もある。見せられる作品の印象は固定されるべきなのだろうか。噺家のように毎度お客さんの調子も見ながら、空気や印象の持って行き方はその場で判断されるべきなのか。MESSYという作品はどの部分をもってその作品であるのか。
青木作品は、舞台上の二人のダンサーの意識のやり取りに作品性がある。今回はスケジュールの都合でオリジナルメンバーが揃わないという条件だった。準備の過程で、青木さん自身が出ないでも成立するのか、ダンサーを募集して、男性2名パターン、女性2名パターンを試した。結論としては、青木さんが出演するという判断がされた。制作当時は音も美術もライブであり、作品中では4人のエネルギーがぶつかり合うという状況だった。今回は美術のカミイケさんも公演に参加できず、この点でも、初演とは異なる状況。
後者二作品について、求められる内容と結果で、ズレが生じやすいといえそう。主催者や観客がどこを買ってその作品を見たいと思うのか。見るたびに見える景色が異なる、というのも舞台芸術の醍醐味だが、仕事として依頼する場合は、どこまでその違いが許されるのだろうか。主催者と作者の間でのコミュニケーションが必要だと思う。どの部分がその作品なのか。
この解釈次第では、作品がどこで”完成”なのかも曖昧になりうる。それとも、身体表現とはそういうものなのだろうか。上演毎の違いを楽しむためには、見る側のリテラシーも必要だ。ファンになる必要があるかもしれない。一回見ただけじゃわからない。この観点での”作品”の場合は、踊りに行くぜセカンドは、本当にスタートアップの企画であり、作品の評価は主催者の手が離れてからという事になりそうだ。
踊りに行くぜセカンドが求める「作品」とは、どのようなものなのだろうか。興行的に申し分なければいいのか。10年くらいかけて上演し続け、やっと評価が見えてくるようなものなのか。