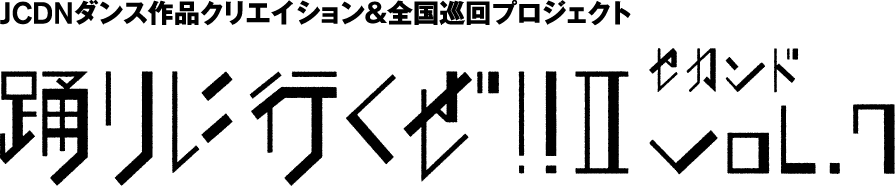2017年02月23日
全国巡回公演札幌・仙台・福岡での上演を終えたAプログラム3作品。
残すところ東京・京都公演のみとなりました。
上演を終えた開催地で、3作品に寄せられたコメント・談話などをご紹介します!
最終公演東京・京都をどうぞお見逃しなく!
岩渕貞太 『DISCO』
photo:Echigoya Izuru 仙台公演

■千田優太/一般社団法人アーツグラウンド東北代表
私が東京に住んでいた頃、よくクラブ(DISCO)に遊びに行っていた。
爆音の心地よい音楽が流れる中、お酒を飲みながら踊りたいときは踊り、飲みたいときは飲み、休みたいときは休んで自由な時間を楽しんでいた。そこには、さまざまな踊りたくなる仕掛けが隠されていたのかも知れない。日常の生活の中で、知らない人がたくさんいる空間の中では、踊るという行為は恥ずかしさなのか、自分にはなかなかできない。だが不思議なことに、この作品を観ていたとき、とてつもなく踊りたくなる衝動にかられた。ただ、ここはクラブではなく劇場の客席だ。
この踊りたくなる衝動と戦いながら、音楽に合わせるでも無く、音楽を無視するでも無く、見せること見られることに縛られない岩渕貞太を観ていた。その身体は自由に存在し、そしてとても美しかった。一瞬、彼の内側が溢れ出てくるのを感じた。クラブで踊るという行為は、大勢の中で他者の視線を気にするのではなく、意識は常に自分の内に向かっているのかもしれない。ここにはいない彼にとって大事な誰かに向かって踊っているのかもしれない。
私が東京に住んでいた頃、よくクラブ(DISCO)に遊びに行っていた。
爆音の心地よい音楽が流れる中、お酒を飲みながら踊りたいときは踊り、飲みたいときは飲み、休みたいときは休んで自由な時間を楽しんでいた。そこには、さまざまな踊りたくなる仕掛けが隠されていたのかも知れない。日常の生活の中で、知らない人がたくさんいる空間の中では、踊るという行為は恥ずかしさなのか、自分にはなかなかできない。だが不思議なことに、この作品を観ていたとき、とてつもなく踊りたくなる衝動にかられた。ただ、ここはクラブではなく劇場の客席だ。
この踊りたくなる衝動と戦いながら、音楽に合わせるでも無く、音楽を無視するでも無く、見せること見られることに縛られない岩渕貞太を観ていた。その身体は自由に存在し、そしてとても美しかった。一瞬、彼の内側が溢れ出てくるのを感じた。クラブで踊るという行為は、大勢の中で他者の視線を気にするのではなく、意識は常に自分の内に向かっているのかもしれない。ここにはいない彼にとって大事な誰かに向かって踊っているのかもしれない。