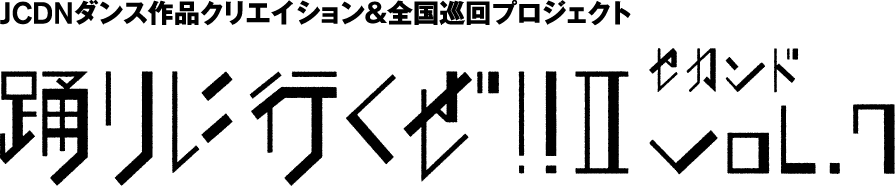2017年02月23日
全国巡回公演札幌・仙台・福岡での上演を終えたAプログラム3作品。
残すところ東京・京都公演のみとなりました。
上演を終えた開催地で、3作品に寄せられたコメント・談話などをご紹介します!
最終公演東京・京都をどうぞお見逃しなく!
山下残 『左京区民族舞踊』
photo:yixtape
■真下百百子(真下教子バレエ研究所)
「この人たちは、なんなんだ?!」左京区から突然現れた異民族たちは、その、えも言われぬ存在感で札幌の観客を大いに戸惑わせ、笑わせ、最後なんだかわかり合えたような気持ちにさせた。左京区に行ってみたい。
■佐々木治己/劇作家
何もないところからはじめるというのは集団創作では当たり前のことだろう。では、何もないところとはどんなところだろうか。何かをはじめるときには、それぞれが持ち寄った考えや技能が元になることが多い。そしてその考えや技能を尊重したり、批判したりしながら創作がされていくわけであるが、この作品では、そのような「はじめる」ということに疑問を投げかけているように思えた。
ダンサー三人が指導者の模範実技を繰り返していく。やり方は笑いを誘うようなものであるが、そこには再現の可能性と不可能性、反復によるズレがどことなく滑稽に示唆されている。「トイレに行きたい」などの生理現象を口走ったことまでも指示として理解されてしまうというやや説明的なお笑いがくるのかと思いきや、誤解された指示ではなく、「トイレに行きたい」というイメージを行えという指示であるとすぐさま展開され、見ていると予想を一つ一つ外される感じがある。いわゆるベタにも思える仕掛けがベタから外される。指示は不明瞭な言葉になり、1人だけが理解する。そのような仕掛けや謎は解明も究明もされずに、そういうものとして舞台は進んで行く。
「何をしているんだろう?」という疑問も、稽古が中断されたような場面の中で話されているが、すぐに再開される。そのあとに、混沌としたダンスに仕上がっていくのかと思いきや、未成立のままに放り出され、最後に何事かをしたかのように終わる。見せられたのは、何かをはじめようとして、それが何だか見ている方もやっている方も分からないようになりながら、ごちゃごちゃして、突然、終わる。終わりだけある。と告げられたような気がしてならない。
「はじめる」ことへの柔らかい批判は、「おわる」ことを受け入れる準備をしているに過ぎないと思わせる。はじまりにあった伝達、反復のズレと集団のパロディは、何も生み出さないまま、おわりになる。この舞台はおかしみを振りまきながら、最後に寂しいような恐ろしいような印象を与える。終わりだけがある。
何もないところからはじめるというのは集団創作では当たり前のことだろう。では、何もないところとはどんなところだろうか。何かをはじめるときには、それぞれが持ち寄った考えや技能が元になることが多い。そしてその考えや技能を尊重したり、批判したりしながら創作がされていくわけであるが、この作品では、そのような「はじめる」ということに疑問を投げかけているように思えた。
ダンサー三人が指導者の模範実技を繰り返していく。やり方は笑いを誘うようなものであるが、そこには再現の可能性と不可能性、反復によるズレがどことなく滑稽に示唆されている。「トイレに行きたい」などの生理現象を口走ったことまでも指示として理解されてしまうというやや説明的なお笑いがくるのかと思いきや、誤解された指示ではなく、「トイレに行きたい」というイメージを行えという指示であるとすぐさま展開され、見ていると予想を一つ一つ外される感じがある。いわゆるベタにも思える仕掛けがベタから外される。指示は不明瞭な言葉になり、1人だけが理解する。そのような仕掛けや謎は解明も究明もされずに、そういうものとして舞台は進んで行く。
「何をしているんだろう?」という疑問も、稽古が中断されたような場面の中で話されているが、すぐに再開される。そのあとに、混沌としたダンスに仕上がっていくのかと思いきや、未成立のままに放り出され、最後に何事かをしたかのように終わる。見せられたのは、何かをはじめようとして、それが何だか見ている方もやっている方も分からないようになりながら、ごちゃごちゃして、突然、終わる。終わりだけある。と告げられたような気がしてならない。
「はじめる」ことへの柔らかい批判は、「おわる」ことを受け入れる準備をしているに過ぎないと思わせる。はじまりにあった伝達、反復のズレと集団のパロディは、何も生み出さないまま、おわりになる。この舞台はおかしみを振りまきながら、最後に寂しいような恐ろしいような印象を与える。終わりだけがある。

■前田透(演出家/劇団・木製ボイジャー14号)
彼らがどこに行くのか、どこに行ってしまうのか、という事を思いながら見ていると、時折置いていかれそうに、そして、実際どこか遠くに行ってしまっていたのだと思う。なのに、なぜだろう、とてつもない快感だった。
■櫻井幸絵(演出家、劇作家、劇団千年王國)
サイババにしか見えない師匠の田島さんにのっけから目を奪われる。とぼけ顔で必死に師匠についてゆく弟子たちの様子がたまらなく可笑しい。音と舞踊が、呼吸という命の音をベースにして、吐き出し、吸われ、ほどけ、ぶつかり、不器用に織りあげられてゆく。混沌がスッとひとつになるラストが美しい。確かに神話の成り立ちを目撃した思い。
■端 聡(現代美術家、CAI現代芸術研究所代表取締役)
左京区民族舞踊は観客を笑いの渦に巻き込みつつ、人類が構築してきた社会システムを風刺する。力ある者と、それに従う者の奇妙で滑稽な関係性を言語とユーモラスな身体運動で表現!これは現在の日本なのであろうか?
左京区民族舞踊は観客を笑いの渦に巻き込みつつ、人類が構築してきた社会システムを風刺する。力ある者と、それに従う者の奇妙で滑稽な関係性を言語とユーモラスな身体運動で表現!これは現在の日本なのであろうか?
■イトウワカナ(劇作家、演出家、intro代表)
ダンスというものに思い込みなどわたしにはない、と思っていた。が、そうではないと山下残さんの作品を観ていて3分で気づいた。軽くショックを受けたそこからは、存分に楽しんだ。滑稽なのに、格好いい。愉快で、不穏。それをビシビシ受けて客席の幼児が笑い転げ、泣き、また笑う。「なんだこれ(笑)」と心の中で呟くときは、喜んでいるときだ。
■水野立子/「踊2」プログラム・ディレクター
舞台上に仕組まれたフィクションの中で、ダンスが生まれる前触れと、瞬間と、弾けた後が、まるで真空パックに梱包された荷物になって浮かんでいるようだった。この作品は、ダンスがつくられる瞬間をとらえた舞台上で起こるダンス・ドキュメント、いや、正確にいうとダンス・フェイク・ドキュメントということか。
かなり怪しげな師匠と真面目で不真面目なダンサーが、ダンスをつくるためにモーレツに稽古をしている。この、ダンスを生みだす、ということに真摯に向かっている姿は、バカバカしくて面白い。マスターたるものは、いい加減にやるくらいがちょうどよい、とも思えてくる。そこに人の本質が見え隠れするからなのか、苦笑してしまう。
こんな混み入った構造をつくるのは、もともと山下残の考えるダンスというものが、ある種のドグマ性を持っているからかもしれない。何が自分たちのメソッドなのか、テクニックなのか、と言われればはっきりわからない、通用するかも確信が持てない。けれどそこに近づくための方法論を虎視眈々と見据えているような気もするし、まるでそうでないかもしれない。山下残の振付法のネタバラシを観客と共有しつつ、ダンスの発露を感じたい。
舞台上に仕組まれたフィクションの中で、ダンスが生まれる前触れと、瞬間と、弾けた後が、まるで真空パックに梱包された荷物になって浮かんでいるようだった。この作品は、ダンスがつくられる瞬間をとらえた舞台上で起こるダンス・ドキュメント、いや、正確にいうとダンス・フェイク・ドキュメントということか。
かなり怪しげな師匠と真面目で不真面目なダンサーが、ダンスをつくるためにモーレツに稽古をしている。この、ダンスを生みだす、ということに真摯に向かっている姿は、バカバカしくて面白い。マスターたるものは、いい加減にやるくらいがちょうどよい、とも思えてくる。そこに人の本質が見え隠れするからなのか、苦笑してしまう。
こんな混み入った構造をつくるのは、もともと山下残の考えるダンスというものが、ある種のドグマ性を持っているからかもしれない。何が自分たちのメソッドなのか、テクニックなのか、と言われればはっきりわからない、通用するかも確信が持てない。けれどそこに近づくための方法論を虎視眈々と見据えているような気もするし、まるでそうでないかもしれない。山下残の振付法のネタバラシを観客と共有しつつ、ダンスの発露を感じたい。