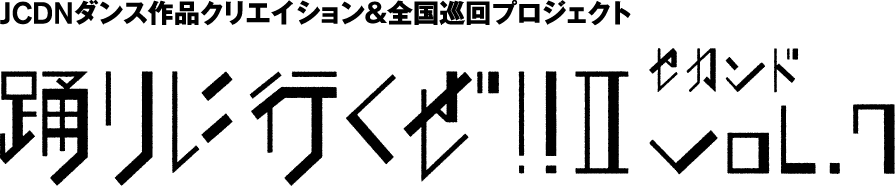2017年01月16日
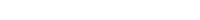
郷土芸能とコンテンポラリーダンス。
異なる角度から「踊り」に向き合う。
対談 小岩秀太郎 × 北村成美
《なにわのコリオグラファー・しげやん》こと北村成美がみちのく仙台にやって来るからには、《東北》をもって迎え撃つのが正しい歓待のあり方だろうと思われた。彼女はJCDN主催「三陸国際芸術祭2016」への参加を経ていっそう東北に心惹かれていたし、東北の人との出逢いを求めていたからだ。
からだとメディア研究室はそんな北村氏と東北の“これぞ!”という人物との出逢いを企んだ。
その白羽の矢を受けたのは小岩秀太郎氏。郷土芸能の魅力を伝えるべく日本全国のみならず欧米、アジアと縦横無尽に飛び回り、自身も鹿踊(ししおどり)の継承者として八面六臂の活躍ぶりが目覚ましい岩手出身の好漢である。
郷土芸能とコンテンポラリーダンス。異なる角度から「踊り」に向き合う二人が出逢い、はたしてどんな化学変化が起きるのか。話を聞いた。
小岩秀太郎(こいわ しゅうたろう)
岩手県一関市舞川地区出身。東京を拠点に全国の芸能のネットワーク作りを行う。震災後は被災地の郷土芸能の復興支援にも取り組む。公益社団法人全日本郷土芸能協会職員。舞川鹿子躍保存会会員。東京鹿踊代表。縦糸横糸合同会社代表。北村成美とは2016年「三陸国際芸術祭」で出会う。
聞き手 伊藤みや(からだとメディア研究室)
![]()
コンテンポラリーダンス
100年も200年も残るような作品が出てもいいんじゃないかと思う
− カラダ同士で300年ずっと伝えてるってことですよね。
小岩:
そうそう。どこかのタイミングでめちゃくちゃ身体能力が高い人か、変なことをする人がたまに出てくる。その人たちの良いところの集大成が今になっているのかなと思います。
− 突然変異的にね。小岩さんはそういうことはやらない?
小岩:
あの…実はジャンプに力を入れた時期があって(笑)。うちの鹿踊は漢字で「鹿子躍」と書くんですけど、「躍動の躍と書くからには躍動しなければならない!」と思ったんです。ただ踊るんじゃなく、「跳躍に力を入れなさい」って言われてる気がしたの。だから若い頃は、跳躍に力を入れてた。さっきは「踊りでは自分を出さない」と言いましたけど、ジャンプに関しては理由もわからずそんなふうにしてたんです。そうすると、周りの人たちと合わなくなってきた。年寄りも多いし、やっぱりタイミングが合わないっていうことがあった。写真を見たときに自分だけが宙に浮いていて、それを見たときに「そうじゃないんだな」って痛感しました。
で、今度は下を気にするようになったのね。地面との距離感を気にするようになって、上にあがるんじゃなくて下にさがる、地面を意識した踊りに持っていこうと思うようになった。
− 伝承ということを考えると、コンテンポラリーダンスはどうなんでしょう。その人一代で消えてしまう寂しさがあるようにも思えますが。
しげ:
寂しいと言うか…死んでも踊りが残らなかったら意味ないなあって最近思うようになったんですよ。作り始めたときは、「これが私の踊り!」という意識でやっていた。まあ入り口はそれで良いんだけど、それをやっている間は「それはしげやんの踊りだね」「しげやんだから踊れるんだよね」って言われて終わってしまう。だけど、「私の踊りではあるけれども、誰が踊ってもそうなる」みたいな、まさに伝承したいという意識が芽生えてきて。コンテンポラリーダンスだから一代で終わるとは言いたくない。やっぱり残せている人は残してはりますからね。単に振付だけじゃなくて、それを踊るときに何が良くて何が無粋かっていう価値観や美学から、踊りをつくりだす方法みたいなことまでも、残している方はいらっしゃるなあと。ま、若いときはね「行くんじゃー!明日死んでもええんじゃー!」って大酒呑んで、ホンマに死にそうになりながら踊ってたときもあったんですけど、それは若かったからできる話で、それも通り道としては必要で、それを通り抜けて、そこからじゃあ何をつくっていくかってなったときに、どうするのか。
『黒鶏-kokkei-』に関しては、今回の公演のためにつくるというよりは…ちょっと悪い言い方をすると「仙台のため」なんかじゃないかもしれない。でも、仙台でつくるからにはこの仙台でつくったっていうことが後あとにも残る。「これは仙台でつくったからこういう作品で、こういうリズムになったんだよね」っていうことが、それごと残るような作品にしたいと思っています。作品が残るということは、コンテンポラリーダンスの世界で言うと「再演可能」ということなんでしょうけど、でもね、再演ができるだけでは、果たして後世に残る作品と言えるのか。300年続くという意味では、やっぱりまだまだだなって思う。
私が死んでも『黒鶏-kokkei-』というものはずっと生き続ける。それぐらいのことやりたいなあっていう感じです。
コンテンポラリーダンスは、作ってるのは現代だけど100年も200年も残るような作品が出てもいいんじゃないかと思うし、いま古典と言われる作品、たとえばバレエの『白鳥の湖』って当時は新作やったけど100年くらい残っているわけですよ。
系譜
その人の美的センスが300年以上続いちゃってる
− しげやんは、三陸国際芸術祭2016で踊ったとき、現地の人に何か感想を言われたりしましたか?
しげ:
鹿踊の会長さんや、虎舞の会長さんに「元気が出る」ってお言葉を頂きました。(照)
一同:
おお~!(笑)
しげ:
「ホントかなあ?」と思ったんですけど、すっごく嬉しかった本当に。私がつくる踊りそのものの年数はまだ浅いんだけど、歴史あるものをやっている人が同じ様に見てくれて、そういうふうに言ってくれるということは、私にとってはすごい嬉しいことで、それこそめちゃめちゃ元気を頂きました。
− さきほど、しげやんが「踊り手が見えない踊りが良かった」と言ってましたけど、小岩さんが思う良い踊りとは?
小岩:
踊りを見るときに、芸能の世界では足を見る人が多いです。足さばきのいい人が良いと思われる傾向がある。あまり上半身とか顔は見ない。それはなんでかなぁ…そういうふうに言われてるからかもしれない。
例えば七福神踊りとか賑やかしの踊りだと上半身、手の動きとか顔の表情とかが面白いんだけど、鹿踊とか剣舞(けんばい)とかの鎮魂系と言われる踊りは、足もとに注意を置くものが多い。「地面を大事に扱いなさい」ということを言われるし、練習でもバンって大きな音を立てるように足を踏む。意味はわからなくてもそういうふうにやるように、あとは、あまり足裏見せないようにと言われて習った。
− ところで、鹿踊の系譜がいろいろある中で、あれほどダイナミックに造形をデフォルメする岩手の感覚ってすごいなあっていつも感心します。
小岩:
もともと仙台藩が発祥だった鹿踊をこの形にしたのは宮城の沿岸部の南三陸町だと言われています。それまではずっと太鼓は(衣装の)幕の中で静かに叩いていたんですが、「太鼓、外に出すか」と言った伊藤さん(行山流元祖の伊藤伴内持遠)っていう人がいて。
しげ:
何年くらい前ですか?
小岩:
1700年頃かな。その伊藤さんがどうやら、太鼓を幕の外に出して、「背中のササラも長くした方が良いよね」って言ったらしいです。まあ本当かどうかは知らないけど、その人の美的センスが300年以上続いちゃってるわけ。その人が始めた美的センスが岩手の南半分まで普及したってことですね(註:このタイプの鹿踊は仙台以北、岩手県南まで60組ほど伝わっている)。
− 一種デコトラや暴走族のバイクのデフォルメ感に近いものがありますよね。この赤と黒の組み合わせを見ていると、生と死の両面を持っているもののように感じられます。
小岩:
伊藤さんの考えは単なる流行じゃなくて、300年後も通じているであろうっていう思いも持ちながら組み立てたんじゃないか、と思うんです。みんなに「かっこいい」って思われ続けているのは、なかなかできないことですよ。
しげ:
やっぱり、かっこいいから残ったんですよね。
小岩:
ということですよね。「この方がかっこいい」って伊藤さんは思ったんだよね。
− 人類の普遍的なところまで到達したと言ったら大袈裟かもしれませんが、「これだよね!」と思わせる力のあるデザインです。
小岩:
そうなんです。だから、そういうことができないのかなって思うんですよね僕たちも。
しげ:
そうなんですよ。
小岩:
結局、民俗舞踊にしてもその時代だけのその人たちのためだけじゃなくてやっていて、ずっと継がれてきているわけだし、今やっている人たちも、その土地でじいさんくらいの世代も、自分の次の子どもたちも次の孫も生きていくんだろうなという覚悟があったと思う。村の外に出る人だけじゃなくて、そこに残る人たちも当然いて、その人たちが30年後もちゃんと食っていけるような理想の村を考えて、そのうちのひとつの大事な要素として踊りをやっていたっていうことがあるから、この踊りの中に50年後の理想が入っているはずなんですよ。「かっこいい」ってことがあれば継ぐべき人が継いでいってくれる、そういう表現なんだと思います。
しげ:
うわぁ…50年60年後の理想の村を考えたっていう話に私はぐっと来ました。だからこそ、かっこよくあるべきなんですよね。
鶏
朝を来させるための踊り
− しげやんは、自分が「歴史の中で生きている」という実感はありますか。
しげ:
以前はなかったんですけど、最近そういうことを考えはじめたんです。大人になったのかなって思いますね。子どもを授かったっていうことが大きいかも。
近未来のことで言うと、息子が二十歳になったときに「うちの母ちゃんこういうことやっててん」って自慢してもらえるような仕事をひとつぐらいはしときたいなあと思う。今は母ちゃんが踊ってることはひたかくしにしてるんですよね、ややこしいから(笑)。あんな格好で踊って、家にいないってなると、「お母さんの仕事はいったい何?」みたいな感じになるからね。
でも、大人になったときに、例えば北九州の小倉の酒場でお客様を巻き込んで踊るダンスを、「これ僕の母ちゃんがつくったんやで」って堂々と言ってもらえるものになればいいなと思う。舞台で踊るものも含めて。作品だけじゃなくて「ダンスを残したい」という感覚があって…
− 「作品」と「ダンス」の違いは何ですか?
しげ:
ええとね、「作品」とは再演が可能であるということ。さらに「ダンスを残す」っていうのは、北村成美のダンスとはこのようにつくられて、こういう美意識があって、それに則って新しいものを何かつくれる、ぐらいのことですかね。
− システムみたいなこと?
しげ:
システムと言うか様式と言うか、目指したいのは『白鳥の湖』のような残り方です。そのままやる人もいるし、それを使ってちょっとアレンジする人もいる、志村けん氏も含めてね。『白鳥の湖』ひとつ取ってもいろんなバージョンがあるわけで。そのぐらいの力を持ったダンスというか…『白鳥の湖』って言うと作品っぽい話にもなるんですけど、でもなんか「これを踊るならこうだ!」みたいなものまで残したい、と思うんです。「昔こういう人がいました」「フーン、懐かしい映像ですね」っていう記録や思い出にとどまるのではなく、誰かが「それをもう一回踊ってみたい」って思えて、しかも再現して踊れる、みたいな…伝わってますかね?
− うーん、だいたい。
しげ:
数年前まではね、「私の表現とは何か」とか「私がどう生きていくか」みたいなことやったと思うんですよ、作品づくりの出発点は。けど今は、「わたくしごと」を超えてダンスそのものをつくりたい。50年後の村を考える話には及びませんが、たとえば、100年後の人が私のつくったダンスを踊って、「コレしんどいけど、踊り終わったらすごい気分良くなるよねえ」みたいな、今日リハーサルしてたダンサーたちと同じような感覚を100年後の人にも味わってもらいたいと思うんです。そうすると、ダンスというのはダンスとして残っていくのではないかと――言葉で言うのは難しいですけど、やりたいのはそこですね。そうなると、何度も再演を重ねられる強い作品を作りたいし、1回で終わってしまう作品ではやっぱりちょっと弱いのかなっていう気がしています。
小岩:
そういえば、鶏は民俗芸能では「長鳴鳥(ながなきどり)」といって、その踊りは朝を来させるための踊りなんです。光がないと作物は育たないから、村の人たちのしあわせと五穀豊穣を願って朝を来させる、朝を呼びこむんです。
しげ:
ああ…朝を来させる…『黒鶏』もそんな作品にしたい!新しい朝を連れてくるような…
(了)