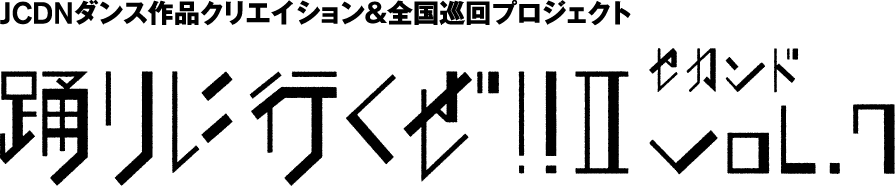2017年01月12日
聞き手・テキスト:みずのりつこ
編集:中山佐代
テープ起こし:黒田瑞仁 インタビュー 2016年11月30日 森下スタジオにて
そのキャリアのある黒田さんが、全国公募プログラムの「踊2」Aプログラムに応募してきたことに、驚きの声が聞こえてきたのは少なくなかった。順風満帆にみえるBATIKでさえ、公募してでも作品制作と上演のチャンスを得る必要があるということなのか?いま実質的に日本でダンスカンパニーを継続して活動していくことは、どのような状況なのかまずそこからお聞きし、BATIKの15年の足跡と、3年ぶりのカンパニー新作となる本作品について伺った。
chapter one
カンパニー作品は文化財そのもの。
―― 「え、黒田さんが応募してきたの?」って聞かれることが多かったですよ。まあ確かに、育世さんほどのキャリアを積んでいる振付家が、「踊2」に応募してくることが意外って思われるんでしょうね。作品をつくることは絶対にやめられないことですか?
やめられないことですね。
―― これまで、作品をつくりたい!という想いはどのように、カンパニーとして実現してきたのですか?今回、「踊2」に応募したことも含めてお聞きしたいと思います。
まずは、短い作品をつくりたいということが目的としてありました。「踊2」の応募がA ②プログラムが、7名まで45分程度の作品を募集していたので、私は縛りがないとわがままになって言いたいことを全部入れてしまう、結果、いつも2時間以上の作品になってしまうので。 それから、皆さんが不思議に思っているのは、公募形式のものに私が応募した、ということですよね。怪訝に思われるかもしれませんが、応募をしてでもBATIKで活動したかったということがあります。私個人を呼んでいただいて踊ったり振付したりということはありますが、BATIKのメンバーたちとまとまって活動している時間が長ければ長い方がいい。その時間の分だけ文化が立ち上がっていくので。
―― BATIKとしての“文化”ですね。
そうです。でも、どのようにすればやっていけるかが本当に問題です。カンパニーを継続するということが非常に困難な状況になっています。最近、新たにカンパニーを立ち上げようという人がいないことをみても明らか。プロジェクトで集まったり、作品に合っている人を募ったり、もちろん、そのことの魅力もあると思いますが、両方ないとよくないと思うんですよね。 “カンパニーというものが独自の文化を立ち上げるのだ”ということがすごく重要で、言わば文化財なんですよね。舞踊作品であろうともいろんな方の協力を得て、公的な助成金をいただいて、お客さんのお金と時間をいただいて、上演を見ていただく。これはれっきとした公の文化財なわけですよね。その文化財を守っていくということは、カンパニーという機能がない限り相当難しいと思うんですよ。
プロジェクトで立ち上がった作品を維持できるのかというと、大分難易度が上がると思います。私の一番古い作品は2001年の終わりにつくった『SIDE B』という作品ですが、今でも維持しています。舞台作品は、瞬間芸術だからなくなってもいいんだという考え方と、もう一方で作品というものが非常に長いスパンで考えられるものでもある、ということも、いろんな人にわかって欲しいし、それをBATIKの作品は願っていると思います。
―― 私は1980年創立、1994年解散まで白虎社という舞踏のカンパニーで活動していてこの頃の時代までは、舞踏集団の多くは集団生活をして衣食住も一緒で朝から寝る時まで、カンパニーの活動しかやらないっていうスタイルだったんですね。今では考えられないけど“公私混同滅私奉公”というの標語が堂々と掲げられ、(笑)メンバーは疑いを持たずまかり通っていた時代。そして、舞踏の先人が考えた経済的にも思想的にも成り立つ仕組みがあったので、今の時代を思うと、活動も生活も心配せずやりたいことだけに集中していられた最後の世代だったと思います。そういうことが成立しない今、カンパニーをどうやって維持し活動していくのか、本当にシビアですね。 育世さんの身体言語がダンサーに染み付いて行くための時間が必要だし、そのダンサーたちをキープしていかないとそれもつくれないし。そのためには運営経費も必要になりますね。カンパニーの活動の継続・文化財として作品を再演できる体制をつくるためには、具体的にはどうやって成立させているんですか?
そうですね、今までギリギリやってこられたのはセゾン文化財団のる森下スタジオのおかげです。森下スタジオは、財団の助成を受けている人が使用できるスタジオで、私が助成をいただいていた2015年度までは森下スタジオのCスタジオをショーイングの場所として使わせていただいていました。基本的には助成を受けている人が使用する場所なので、助成期間が終了してしまった今、本当にカンパニーの危機的状況を迎えています。
―― 今までは森下スタジオで公演が可能だったということですか?
再演ですね。“レパートリーズ”というシリーズで、すでに発表した作品を完全なかたちで再演するのは照明や音響の問題などで不可能なので、抜粋や簡易バージョンにして上演していました。それができなくなった今、劇場を借りてやらなくてはいけなくなった。予算が必要、でも予算なんてない。経済的に破綻状態です。ですので「踊2」で応募をしてでも発表する現場が必要だったのです。森下スタジオはありがたくて、拠点みたいな形で使わせていただいていました。まだ稽古場としては使わせてもらえていて、それだけでも本当にありがたいんですが、それも優先順位ががくんと落ちるので、どうやってサバイバルしていくかが課題です。
―― BATIKというカンパニーの拠点を提供してくれるスポンサー、パトロネージはこれまで出現してこなかった?
もしもできることならば、レジデンス・カンパニーとして地方自治体が持っていらっしゃる劇場に、専属のカンパニーとして迎えていただけるとこれ以上嬉しいことはないです。
―― それが実現するとカンパニーメンバーが東京から移住することになりますよね。
はい、皆、移住する気でいます。
―― そうですか。私が知っている例としては、東京を拠点にしていた劇団が、鳥取に移住して小学校の体育館を本格的な劇場として運営している中島諒人さん主宰の鳥の劇場。彼らは自分たちの作品を上演すること以外に、演劇祭や地域での演劇のプログラムなどさまざまな形で地域と劇場を繋ぐ役割もつくり出してきていますね。
私たちの場合、あがいてきたからこそ得た方法論を持っています。本当はBATIKとしての公演を頻繁に継続したかったけど、それが実現しづらい経緯があって「じゃあしょうがないワークショップでもいいからやってみよう」と始めたのが、これまでBATIKで創って来た作品の“レパートリーワークショップ”でした。これが、すごくいい経験になりました。作品にとっても受講生の方々から新しい血液をもらうことができましたし。作品という文化財の持っている側面というのがいっぱいあって、そのひとつの側面が“BATIKダンサーでない方々にBATIK作品を提供すること”でした。だから、たとえ劇場専属のカンパニーにして頂けたとしても、自分たちの現場をつくるためだけの現場とは捉えていません。望んで頂けたらBATIKが持っている作品をいくらでも全国各地にお渡しできる。ダンスを志す学生にもレパートリーワークショップで渡したいですし、いろんな人に踊ってもらいたいです。プロが踊らないとだめなんだという固定概念は全然ないので。
しかし、これは、プロフェッショナルによる作品の上演がなくなってしまったら出来ないことです。ダンスは本当に誰しも踊ることが出来ます。だけれども、それを職業にすることとは非常に厳しく分けて考える必要もあります。踊りで生きていくことは大変なことです。大変なことをやってのけた時に尊さが滲むし、尊さが信頼を生むのだと思うので、地域との信頼関係、お客さまとの信頼関係を築く姿勢としても、踊りで生きていくというプロフェッショナルなダンサーの作品は必ず必要だと感じています。
―― そうですか。ひと昔前のBATIKから変化していますね。カンパニーの持つ力が個だけではなく、外に対して開かれているんですね。この“レパートリーワークショップ”は、要項に経験不問と書かれてますが、ダンス・テクニックがない人でも踊れますか?
はい。びっくりしますよ。たった10日間でも受講生の方々が、初日とは見違えるようになるんです。
―― 初めて踊りと出会った人が体を投げ出した時、立ったとき感動します。
そうですね、でもそれも“頑丈な作品”があってのことです。投げ出せばいいってものでもないですし、すっぽ抜けて倒れていく様っていうのは面白くない。頑丈な作品に当たってこそ、投げ出した体は面白い。頑丈な作品をつくってきたことは自負してます。これだけ長持ちしているわけだから。
chapter two
BATIK の15年
「メンバーがBATIKの本質なんです。私も含め。」
―― BATIKのこれまでの作品について伺います。2002年設立当時の作品から、最近では原作がある作品を舞踊化する制作方法まで、カンパニーとして15年間を振り返ると、やはり時代により作品の傾向などが出てきていますか?
そうですね、もう4期まできました。第1期は『SIDE B』『SHOKU』『花は流れて時は固まる』。子供の時からの謎をやり続けた3作品です。
第2期は『モニカモニカ』『ラストパイ』『ペンダントイヴ』。これは、そもそも踊りをやりたくてやっているのに、作品のメッセージや具体化しなくてはいけないものに縛られて、自由に踊れなくなることにうんざりしちゃった時期です。だから「私はもう踊りが好きなんだ、ダンスになりたい!」って爆発したのがこの3つ。ダンスになりたいを貫いた時期です。それを経て、私の中にダンスの確信が持てたから、私はダンスから離れないってわかりました。
第3期は『矢印と鎖』『あかりのともるかがみのくず』『おたる鳥をよぶ準備』です。これは、作品の構成要員であり、一番の原材料でもあるダンサーのドキュメンタリーというか、生い立ちに迫っていきました。私がこの人たちのことを知る必要があると思ったんです。具体的に生い立ちを言葉で語っているのは『矢印と鎖』だけですが、彼女たちがなぜ踊っているのか、どうやって生きているのかということから作品をつくったのがこの3つです。
『おたる鳥を呼ぶ準備』 2012年 photo:塚田洋一
本から舞踊化するシリーズです。
それと番外編で、『きちんと立ってまっすぐ歩きたいと思っている』。これは例外的な作品で、10歳の友人と踊った作品です。
―― 1期から4期まで、きちんと統計だっているのですね。素晴らしい。『落ち合っている』は黒田さんとBATIKダンサーのデュエット作品、ダンサーは日替わり出演だったんですよね。ダンサーが変わることで、作品がどう変わりましたか?
みんな全然違うんです。もちろん段取りも振りも全部決まっていますが、ニュアンスはやっぱり違ってきますね。
―― 各ダンサーによって振付を変える、というよりも、普遍的に踊れるものとして振付していくのですか?
普遍性というのはありますが、彼女たちと1対1で踊る時だろうと思ったんです。なんというか、私とカンパニー全員、ではなくて。ダンサーたちはBATIKを愛してくれて活動してくれて、BATIKが求める技能を彼女たちが掴んでくれた。これだけは譲ってはいけないんだっていうものを培ってくれたという気がするんですよね。そうしたら10人、5人ではなくて、一人ひとりと丁寧に踊りたいと思いました。
―― そういう風に育世さんが、ダンサーと、人として向き合うからメンバーもついてくるんですね。
向き合うのは基盤ですよね。メンバーがBATIKの本質なんです。私も含め。だから
皆、責任を感じてくれているんじゃないですかね。そこにいるという。
―― やり甲斐がなかったら辞めていくからね。
ある程度実現すべき使命というか、責任があると頑張りやすいということではないですかね。私がどうっていうよりも作品じゃないですか。作品が彼女たちに使命を与えているんじゃないですか。私が作品をつくってる気がしない、降りてきてつくっているだけだから。(笑)
―― 実際にそれをやれているカンパニーは少ないですよね。パートナーがいて定番形式ができてしまうか、プリマとその他大勢になってしまうか。
本来は群舞でも“その他大勢”じゃなく、ヒエラルキーだけが目につくのではなく、踊れるはずなんです。“今、此処”を踊っているということを使命と感じて、端っこのほうでやっていたとしても、使命を果たすことに幸せを感じるという。センターで踊っていることが、大事なんだということではなくて。
―― 4期の本からダンス作品にするというアプローチは、今回の新作が3作品目なんですね。私が知る初期の育世さんからは、このような制作方法をするということは、予想できなかったです。
『落ち合っている』は自分で原作を書いています。2作品目の『波と暮らして』はオクタビオ・パス。『THE RELIGION OF BIRDS』は中沢新一さん著の『鳥の仏教』。
実は、3期をやりはじめた8年前から言葉が出始めました。4期は言葉が奥にあって、3期に比べると言葉を舞台上で発することは激減しています。
―― 1期から3期まで全て3作品になっていますね。
そうですね、振り返ってみればなんです。どうして毎回3作品なんだろうと不思議に思います。おそらく今回の作品が4期の最後になると思います。
―― 育世さんは舞台芸術のシャーマンじゃないか、とよく言われていますよね。
本当ですか!?降りてくるというか、「この作品をつくれ」って引っ張られる感じはします。だけど私の場合は有刺鉄線でできた梯子が降りてきて、血まみれの傷だらけになりながら作品によじ上がる感じなんですよ。寝ないで作ります、最後の1ヶ月半くらい。だから、シャーマンじゃないですよね。
―― 初期の段階からだそうですね。
『SIDE B』なんかある日突然全部見えたんです。バラララララって。これつくらなきゃ、つくらなきゃ駄目だって。そもそも見えないとつくらないです。これまで何年も見えない、ってことがないんですよ。絶対にある日突然、ウッ、きたって感じなんですよね。
chapter three
そして、3年ぶりのカンパニー新作について

『THE RELIGION OF BIRDS』 2016年12月 途中経過発表 @城崎国際アートセンター (c)igaki photo studio
―― 今回の新作が降りてきたのはいつですか?
これは1年くらい前なんじゃないかな。他の作品をつくってる時で、今ちょっと呼ばないで。次やるから!次ちゃんとやるから待ってー、みたいな。たまたま「踊2」の企画を見て、ああ、これでできるって思いました。
―― 育世さんの作品には鳥がよく出てきますね。前世が鳥なの?
ホントに、鳥なんじゃないかな。今回の作中の鳥の中でも特別なのは雲雀。雲雀って可哀そうなんですよ。何度も生まれ変わりを体験して、すっかり疲れ果てている。
―― 今度の原作では、多くの種類の鳥が出てきますが、ダンサーに役を当ててつくっている?
あまり固定していないです。原作の最後では何も語られないままトビとワタリガラスが置き去りにされるんですが、彼らを見捨てたくなくて、固定したくなかったんです。宗教というものはすごく大切なものだと思いますが、この宗教を信じていなければ救われない、ということに疑問があります。ダメとか、いいとかじゃなくて疑問がある。トビとワタリガラスが私の作品の中で救われない存在ではなくて、一緒にお辞儀をする。そのあとどうなるかはわからないけど、この人たちとも一緒にお辞儀がしたいと。だからカーテンコールのときに出してるんですけどね。
―― なるほど。原作にない育世さんの想いもあるんですね。
このダンス作品が、『鳥の仏教』です、とお客さんに解ってもらうためではなく、この本が生み出されたことの根幹部分が導き出せればいいと思っています。
―― 先日、稽古を拝見した時、印象に残ったシーンなんですが、原作では鳥たちが次々と仏典ダルマの教えを説くところが、3名のダンサーが日常会話の短いセリフと鳥の鳴き声で構成された振付になっていましたね。これまでの育世さんの振付作品にはみられないダンスのように思えました。
まず、この経典を自分が培ってきた踊りに言い換えるならどういうことか?ダンサーたちに何十っていう言葉を宿題で出して、彼女たちが自分の言葉に置き換えました。知的になりたくないから。もっと言うと踊りを通して、自分の体で培ってきたことに落とし込んだ。つまり、仏典を翻訳したんですね。
―― なるほど。仏典の教えは正しすぎて、時として遠い言葉としてしか伝わらないこともありますからね。
私は説教できるような人間じゃない。本は経典だから当たり前なんだけど、作品は説教くさくなりたくない。すごい労力をかけましたが、最終的には5羽分しか残りませんでした。
―― 仏典を自分の言葉に置き換えたんですね。これまでも原作のテキストを渡して自分のイメージをつくってもらうという作業はしてきたのですか?
今までもずっとやってきています。振りは基本的に私がつくりますが、彼女たちにつくってもらったものをコラージュしたりすることはあります。
―― この段階(11月末)でもう通し稽古をしているんですね。
まだ公演まで変わり続けます。だけど、3期までは、直前で積み上げてきたものを変えてしまうガラガラガッシャーンの連続でした。4期に入ってからはそういうことがなくなりましたね。このほんの少しのダンスが全てを変えるようなこと、大切なささやかな一つを探しながらやってますね。
―― 自分がこれをやる意味っていうのがメッセージとして見えるのは、必ず2週間前でしたか?
そうなんです。これもある日突然降ってくるんですが、何故か2週間前なんですよ。
だから仙台公演の前、1月の中旬くらいですね。早く教えて欲しいんですけどね。というか作品の使用人なんですよ、私は。
―― テキストとして啓示がある?
テキストではない・・・けど。
―― 思想としてかな。
っていうのかな。なんですかね。
―― 本当にシャーマンですね。
いやいや。使用人、シャーマン、なんか響きが似てますね。
―― 降りてくる元はなんでしょうね。神様?
神様とかそんな崇高なものではないと思います。ご先祖様とか?わからないですね。でもクロッシング・ポイントじゃないですか、意思とか意識とか。
―― 原作の「鳥の仏教」に収録されているいくつかの章のなかで、中沢新一さんが書かれている「今日のアニミズム」にシンパシーを受けるとお聞きしました。「神話の時間」「夢の時間」と呼ばれ人間の心が自然や動物の心と共感したり、コミュニケートできること。実はアニミズムと「鳥の仏教」の思想は、先駆的に通じるものがあると。
舞台作品の中で、鳥だけではなくほかの動物も登場し、舞台上が森羅万象になりつつ、曼荼羅絵図もみれるような広がりを受け取りました。
そうですね。仏典の中でシンパシーを感じるところはここです。これは大好き。
(中沢新一『鳥の仏教』平成23年 新潮文庫「鳥のダルマのすばらしい花環」内 p.65 カッコーの言葉)
「輪廻する生も輪廻を脱出した生も、すべては自分の心に起こることです。この心ははじめから完全なものとして完成しているすべての土台であり、本質が空であるので、生まれることもなく、滅びることもなく、とどまることもなく、行くことなく、やって来ることもありません。心をどこかに求めても見いだすことはできず、探しても得ることはできません。心ははじめから完全な完成をとげていますから、それを知的に分析したりすると、単一の本質を多くの要素に分解してしまい、はじめから完全な完成をとげている心というものを、理解することなどできません。」
この一節の「それを知的に分析したりすると」これなんですよ!
私は非常に感覚的な人間で、知的に分析したりするのがあまり好きじゃないんです。まるまる受け止めるだけというか。知的に分析しても見つかるものじゃないんだよ、っていう。手放す勇気ってすごく好きなんです。
―― そこが、黒田育世BATIKのダンスを観客が、好きなところでもあると思います。
ピナ・バウシュの「ダンスには、どうしてもダンスでしか伝えられないところがある。」という言葉は、育世さんのダンス思想にも通じることですね。
心と意識というものがあると思っています。意識は心の副産物。心っていうものがあって、それが吐いた二酸化炭素だったり必要な酸素だったり。意識不明の人に心がないのかって言われたら、私はあるような気がします。ただ、こちらが意識的に意識を見ようとしたら、意識はない。だけど心は多分あると思う。物の本によると、踊りは意識的な運動であると書いてあるらしいんです。そういう側面も事実あると思います。だけど、心の成したことを考えたとき、踊りは「知的に分析しようとしたりすると」逃げていっちゃうもの、そっちの側のことが好きなんです。
―― 今回の新作の試みがおもしろいのは、仏典という原作から知的な作品制作過程を通りながら、それを敢えて遠ざけて心のダンスを掘り起こすというところでしょうね。私の心がどう揺れるのか、客席で楽しみにしています。
これで4期が終了するとして、次の5期はどなるか予感はあるんですか?