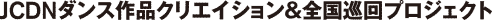2016年04月10日
文・黒田瑞仁
地下鉄の浅草駅から地上に出て吾妻橋で隅田川を渡ると、巨大な金色のオブジェをのせた建物が見えてくる。このビルの側面に回り込み、エレベータで4階に上がるとそこはドーム天井をしたロビーになっている。受付を済ませ動物の角のような金色の取っ手がついたドアを開けれると、横長の少し変わった形の劇場が姿をあらわす。大きな二本の柱と、エアダクトが空間にアクセントを与えており、正面の客席をハの字が挟むように三面の客席が舞台を取り囲んでいた。
photo:飯名尚人踊りに行くぜ!!セカンドvol.6(以下 踊2)は、例年通り全国各都市を巡ったのち、最後は東京で2016年3月26・27日に全3回の公演が行われた。この締めくくりの公演が行われた会場は、踊2が閉館前最後の公演となった浅草のアサヒアートスクエアだ。同会場での開催時期が決まってから、2016年3月末の運営終了が決定したので踊2が「大トリ」公演になったのは偶然だったが、三回目の公演の後には出演者とその日の観客によるセレモニーが行われた。
上演されたのはAプログラムの3作品。
平井優子『Ghosting-軌跡の庭』
梅田宏明『Movement Research - Phase』
山崎広太『暗黒計画1~足の甲を乾いている光にさらす~』
Aプロの3作品は前年の春に公募し選出されたもので、ダンス・イン・レジデンスと称した城崎での滞在製作にはじまり、札幌、松山、八戸、仙台、神戸、福岡で公演することで多くの観客の目に触れてきた。立て続けに都市を巡るのではなく、それぞれの公演の間に数週間の時間を取り、作品をブラッシュアップする形式がとられている。作品を稽古場で前に進めては、各開催地の協力を得ることでどの作品もその都度、形を変えながら半年ほど作品作りが続けられてきたわけだ。
作品提供をする三組のアーティストにとっても、一ヶ月ほど稽古場に篭って集中的に作品を作り上げるのが普通のやり方だろう。アーティストにいつもと違う環境と時間をかけて作品作りをしてもらうのも踊2の目的の一つになっているのだ。またどの会場でも複数作品が上演されるので、1作品はどれも約30分と短めなのも特徴的だ。
東京以外の会場ではAプロ以外にも、演出家が地元出演者と作品を作り上げるBプログラム、地元アーティストの作品であるCプログラムが上演される。なので客席には、地元出演者や会場となった劇場の常連や、もちろん各地域のダンスファンがつめかけ、客席同士で顔見知りを見つけては開演前の話に花を咲かせているのが当たり前だった。そこへいくと東京会場は「地元」枠が無いせいもあってか、会場の雰囲気は他のどことも大きく異なっている。それはきっと、一般の観客に混ざっている評論家やダンサーの比率が多く、また各地方の主催者がアートスクエアでの最終公演と、自分達のところへ踊りにきていたAプロ作品の最終形を見たくて駆けつけて、結果的に勢揃いとなっていた。彼らの間では松山の時に比べたらこの作品はこう、神戸ではこうと、作品たちがどう変化したかの感想が飛び交う。また札幌会場のコンカリーニョに満席になった公演の時のみ姿を表すというマスコットキャラクター、満席さん(なぜか四国のお遍路さんの格好をしている)も登場し、開演前にお客さんを誘導し活躍した。
過去に踊2で作品作りをした出演者や演出家の姿もあった。もちろんこの公演を毎年楽しみにしている常連ファンもいるのだろう。東京はある作家が作りこんだ1時間2時間の公演を沢山観れる場所だ。対して踊2は30分という長さでも各地方で「踊ってきた」作品が、多くの観客と関係者の手と目が入ることで洗われてきた作品が「どうなったのか?」を見る収穫祭のような楽しさがある。心なしか観客席も、派手な髪の色をした人、一色に身を包んだ人、着物の人らを筆頭に華やかだった。全3回公演の客席はどれも満員となった。
一人の女性が、光りを放つ筒を覗き込むところからはじまる。スモーク、映像、仮面などさまざまな仕掛けや、カタコトの言葉、音楽に乗って幾つものシーンが連綿と展開していく。二人のダンサーがいつの間にか現れては消え入ってゆく空間が、あたかもパフォーマーかのように姿を変化させて行った。
この作品を観たときにまず感じざるを得ないのは「時間」というものについてだった。上演されているのは、おそらく現在のことではない。「現代ではない」と言い換えてもいいが、舞台上に流れる時間は終始ゆっくりと心地よく感じられ、会場にたどり着くまでに感じられた2016年の東京の忙しさとは全く無縁だ。タイトルを信じればその場所とはどこかの「庭」なのだろう。シーンの境い目は曖昧で誰かの記憶を漂流して辿るように進んでゆく。
二人のダンサーの衣装はいずれもスカートだ。お互いに寄り添うように触れ合ったり、まったく別個の存在のように音楽にあわせて同じ動きをしたり、ついては離れるように展開する。光と影や、ドッペルゲンガー、あるいは全く別個の存在のようにも見える。特に平井優子の華奢な姿を見て、私には彼女が一人の少女の心のように思えた。自分の身体、もしくは感情を引っ張ったり、丸めたりすることで、どうなるかを試して遊んだりすること。誰にも迷惑をかけずに、その瞬間に感じている寂しさを友達にして楽しんでいるような感覚。学校で友達や家族と接している生身の女の子ではなく、ひとり頭の中でいつまでも空想しているような少女だ。舞台上で行なわれている事柄は彼女の心象風景そのもので、相手役の女性は彼女を導く仮面をつけた妖精の女王さまのようにも見えた。
男女問わず、そうやって心だか身体だかよくわからないものとしての己で遊んだ記憶はあると思う。そういう意味ではもしかすると平井作品が描いているのは最初に知らないうちにダンスをしていた頃の記憶なのかもしれない。「幽霊する」と読めるGhostingとは「幽霊ごっこ」のことなのかもしれない。上演を重ねることで継ぎ目なく組み合わされていった沢山の要素が、見る者の想像の幅を大らかに広げていた。
梅田宏明『Movement Research - Phase』
photo:前澤秀登
この作品からは感情が読み取れない。というのがどうやら定説で、おそらく実際にそう割り切って作られている。見方がわからない、これはダンスとは言えないのではないか、そんな評判も耳にした。一方で印象に残るのは、理系的な視点を持てばこの作品はとても面白いのだ。という報告するぜ!!チームの飯名尚人さんの意見。ただいずれにしても非常な意欲作であることに疑いの余地はない。
四人のダンサーはすべて同性の女性で、背格好も近く、衣装は共通。音楽や、誰か一人の動作が発端となって、円弧を描くような質感の似た動きが派生し伝わっていくことで群としてのうねりを形成する。舞台装置は使われていない。主だった展開は音楽と、照明の微妙な変化と、それに伴うダンサーによる動きの変化でなされた。
多くのダンス作品というのは誰かの心情のクローズアップや、どこかに注目して強調された表現なのだとしたら、梅田作品はシステムや社会のようなもっと広いものに着目しているはずだ。観ていると、言葉も通じない海外に出かけ、街の人々を眺めるときに働くような好奇心がそそられてきた。人々の行為には何か意味や目的があるのだろうが、自分にはそれがわからない。ましてや目の前の4人はアイコンタクトを含む我々が普段使っている言語的なコミュニケーションを全く使わずにいるのだから、海外というよりは、別の星で宇宙人を観察しているようにすら思えてくる。
ここで気づくのは、舞台上には規範に沿って動く群しかおらず、強い主体がいない(演出家が唯一出演していない作品でもある)。しかし、それを眺めている観察者である観客個々人は主体だ。梅田作品が作品として成立させていた最後のピースは、異文化に分け入って行こうとする観客自身だったのだ。
山崎広太『暗黒計画1~足の甲を乾いている光にさらす~』
photo:前澤秀登たとえば暗黒舞踏の「暗黒」についての検証であるこの作品。製作の最初期の城崎では、演出によって書き下ろされた舞踏譜に基づいた出演者3人の踊りだけで作品は構成されていたそうだ。3人には互いに関わりを持たずに踊る瞬間がしばしばある。自分の行為に専念している人物らの間の相対的な距離感は無限のように思え、彼らは闇に天地の別もなく浮いているようにも見えてくるのだ。だが、このころには現れてこなかったが、全国を巡るうちに付け加えられていった要素は数多い。
まず、作品の終盤まで休まず踊り続ける3人を背に、演出家が突如舞台上に登場し、そこで行なわれている踊りの解説をする。彼を入れた4人は老若男女としてそれぞれまったく違った文脈を持つように見える。そんな中で、演出家は自身の「暗黒」に関するイメージを脈絡なく語る。歌ったり、出鱈目な物語を話したり、「すみません、この作品は成立していません。」と宣言すると思わず客席からは笑いが起こる。ダンサーらも、奇声を発したり、前後関係なしには意味をなさないことを急に喋る。しかし段々と、このメチャクチャさと、矛盾を内包するものこそが「暗黒」なのだと説明する演出家山崎広太の言葉と行為が、動き続けるダンサーらが迫力を傾けて表現しようとするものそのものなのだと気付いていくのだ。
後半に差し掛かったところで、世界的な人気歌手Siaのポップで力強い曲が爆音でかかる。その音の中で「暗黒はどんなダンスでもいいんです!」と山崎が叫びながら舞踏とは違ったダンスのステップを踏みまくって踊るシーンに客席は釘付けだ。終演後に「感動して泣いた」という声を幾つか聞いたのもここ。モヤモヤとした状態としてしか存在しえない矛盾に「暗黒」という名前を与えて、それを足でステップを踏みまくることで処理していく爽快感は彼の存在感と共に会場をぶっちぎっていて、関係者や観客から「天才」という言葉が衒いなく出るだけあって圧巻だった。
私がそうだったが、各作品の間に10分ほどの休憩が挟まるとはいえ2時間あまりの間にこの3作品を観るのだから、当然見終わった後は頭も心も整理がついていない。休憩時間には席を立ったり話す人が少ないが、かわりに終演後の騒がしさが際立つ。大きな舞台に対して、人が溜まっていた客席裏の通路とロビーは小さめで、誰かと意見を交わしたい人達によって渋滞が起こるのだ。私も知り合いが来ていた回には、捕まえて感想を聞こうと思うのだが、思わず自分の感想も次々に出て、会話がかみ合わない。終演後に観客が「ほーっ」と息を漏らした後に素直に帰路についていく各地方会場の雰囲気とはやはり違った様子だった。

最終回の後には、水野立子、飯名尚人のダブル司会でのアフタートークで、各作品に関するコメントと平井、山崎の両演出家による作品の初期イメージの解説などが行われた(梅田宏明は海外のため欠席)。用意された一問一答というよりも、それぞれがユルユルと感想を述べていく形で、先の2時間がじっくりと半年かけての製作期間の落ち着いた雰囲気が伺える。もちろん、たまに作家と関係者の間で激論が交わされたという話も聞いていた。
それが終わるとJCDN佐東範一の音頭で、関係者、制作、出演者、各地方公演の主催・協力者、裏方スタッフ、劇場スタッフが舞台上に集合し、観客立ち会った含めた三本締めでアサヒアートスクエア最終公演としてのセレモニーがおこなわれた。音響さんや舞台監督まで舞台上に出てきて、それぞれ紹介されてニコニコとしているなんてことは、そうそう見られる光景ではない。お客さんも残って是非参加をということではあったが、トークが終わった時点で観客もそれなりに減っていたので関係者のほうが多くなってしまったのではと思わせるほど。最後はお客さん含めた全員で記念撮影し踊2vol.6と共にアサヒアートスクエアの歴史が締めくくられた。
終演後に観客にもアナウンスされたが、半年に渡る製作期間とアサヒアートスクエアとの長い付き合いが終わった踊2だが、すぐ次年度の参加アーティストの公募が始まる。毎年の公演が一年かけて運営されているのだ。そして最終公演の打ち上げが終わればみなバラバラに本拠地に戻っていく。JCDNの本拠地は京都にあるのだし、各アーティストも国内外に散らばった。ひと月程度で作品を形にしては、チームがその都度解散する形が一般的な公演だとしたら毎年必ず開催されるダンスのお祭りは、都市における突発的な祝祭として乱立するダンス公演とは別の意味で、大きなコミュニティに季節をもたらしているようだった。