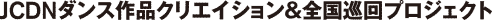2016年03月10日
「報告するぜ!」鼎談
2015年12月13日
未生文庫(東京)にて
飯名尚人
佐々木治己
隅田 有
<立ち会い>
中野三希子(制作者/SPAC-静岡県舞台芸術センター所属)
黒田瑞仁(報告するぜ!!)
今年の「報告するぜ!」は、色々な人とダンスの話をしようという、単純なコンセプトで進めています。振付家、ダンサーとだけでなく、「報告するぜ!」ではむしろ作品の当事者ではなくダンスのいわば「外野」にいる人たちと、ダンスにまつわる話をしていくということを目指しています。つまりこれは「雑談」なんですが、、、日々の雑談はその場で過ぎてゆくけれど、改めてこうして文字にして読み返すと色々な主題が隠れており、またそれぞれの視点の相違と一致が交差していき感慨深いものがあります。自分の考えていることや価値観が他人に伝わるだろうか、みたいな感覚もあります。この鼎談のお題は特になくて、「なんでもいいからダンスに関して話しましょうか」という程度のものです。批評とはまた違う、日々の会話の中にあるダンスについて。
今回は、詩人であり、ダンス評も手掛けている 隅田 有さんを招き、開催されました。立ち会い人として、制作者の中野三希子さん、報告するぜ!メンバーの黒田瑞仁が参加。
2時間ほどの鼎談。長いけれど、あまり編集を加えずに、ほぼそのままをテキストにして掲載することにします。
飯名:隅田さんは舞踊評を書かれていますね。
隅田:もともと、私はバレエを習っていて、舞台も良く見に行っていました。だか
ら最初に書き始めたのはバレエ評です。バレエというのはまず作品があって、それを演じ手がどう解釈するのかを見るのが面白い。それから役に求められる高い技術があり、そこに表現が盛り込まれていく。舞踊評を書いているので、コンテンポラリーダンスの公演も見なきゃと思っているのですが、かなりサボっています。コンテンポラリーダンスの公演、特に日本のコンテは、大概作品を一から作りますよね。バレエは作品が先にあり、踊る側と観る側に共通認識がありますが、コンテは踊り手と作品が極めて近い。それが面白いこともありますが、作り手の思い入れが強くて、ちょっと受け止められないなと感じることもあります。
![]()
佐々木:バレエは元の古典作品があって、解釈、アプローチ、取り組みが、舞台によって露わになるということなんですか?
隅田:そうですね。だから客観的な判断基準が多いんじゃないかと思います。コンテンポラリーダンスの舞台評は、作り手を追っていないと書きづらいんです。特に、既に何度も作品を発表している作り手の場合、一回舞台を見ただけでは、感想は書けても、批評を書くのは難しい。
飯名:詩って自分の中にあることを言葉にするとか、自分が見たこと感じたこと、そういった自分の身体の中にあることを言葉にする作業ですよね。詩というジャンルをやっている方がダンスを観るときに、みんなが共有できるファンタジーの部分に興味があるというのは面白いですね。
隅田:共有できるものの中に、それぞれの個性が出てくる。型があるからこそ、そこから漏れて来るものが面白いと思うんですね。ところで詩は紙とペンがあれば書けますが、ダンス作品は色々なものを必要としますよね。
飯名:ダンス作品も一人で作れる時代になってきましたけども、その一方で、どんどん周辺のメディアで作業や演出で作品が重たくなっている気もします。照明、映像、サウンドであったり、演劇的とも言える演出効果であったり。詩のような極めてシンプルなダンス作品が少ないかもしれません。ダンスが散文化、演劇化しているとも言えますが、ダンス作品の主題が私小説化している、セルフドキュメンタリー的であるとも言えます。詩って注意深く読まないと見逃しますよね。この人は何を言っているのか、この人はどこにいて、どこに向けて語っているのか、そもそもこの語り手は誰なのか。
佐々木:こういう話をしていると、詩と散文って分けて考えがちだけれども、あんまり分けては考えられない。散文詩というものありますし。そうなると何が大きな違いかというのは、詩と散文というよりも、散文は説明的、描写も描き、映画の景色を描くように、見ているものを描写していくんですよね。逆にいえば、その人が何を思っていなくたって、その人が見えている世界をだだ漏れに描いてしまえば、その人が見えている世界なんだから、それでいいというようなことがあります。
しかし、詩の場合は、もうちょっと違いますね。もちろん、そこには形式の問題もありますよね。現代詩になっても、詩形式を意識したり、七五調で全て書くなんて人もいますし、そうした形式で行おうという運動はいつでも起こりますよね。しかし、形式が自由になったところで、詩が何をやっているかというと、私の物語というよりも、私と共同の何か、共有されている何かとの応答とでもいいますか、私が持つイデアと共同体が持つイデアとのぶつかり合いというイメージが強く出てくるんですね。
コンテンポラリーダンスの場合は、イデアなきダンス、イデアなきイメージという、現状の中で、現状を見ること、今のこの世界が当然視されすぎているようなこと、その中で苦しんでいる私、その中で悩んでいる私、その中で違和感を感じる私みたいなものばかりが出てしまうから、まずは、そのような自分を取り囲む世界や環境、状況を当然視しているところから始めるからつまらなくなっているんじゃないかと思うんですね。当然視しているから、散文的に説明するということがあるんじゃないかと思うんですね。
隅田さんがバレエや古典作品の方に興味があるというのは、それらはすでに美学的な感性が、ある時代、ある国において行われ、そことの対峙が行われるから、興味を感じるのではないでしょうか?
隅田:はい、そうだと思います。もっと単純に言うと、いろんな人が同じ作品を踊っているのは大きい。何度も再演され、異なる個性の踊り手が踊ることで、作品が育っていくということがあるのではないかと思うんです。一つの作品をいろんな人が複数のアプローチでやっていて、そこが古典の見所の一つですが、コンテンポラリーダンスは同じキャストということが多いですよね。
飯名:一世一代の表現ですよね。
隅田:再演があったとしても、例えば賞を取って再演みたいな感じですよね。だから古典と比較すると、作品を作る際に加わる視点が少ないんじゃないかと。
佐々木:ですから、何やってもその人の良さ、というものになるんですよね。みんなちがってみんないい、という相田みつを的なものになっていってしまいますけどね。
飯名:そうなると、批評、批判は難しいですよね。何を言っても成立してしまいますし。
佐々木:そうなんですよね。そうなると、良いか悪いかしか言えないんですよね。
隅田:だから同じダンサーを見続けないと書けない。以前の公演と比べることが重要になっていくんですよね。一本だけ見て感動しても、実はこのダンサーは同じことを20年間、手を替え品を替えやってましたとなると、それはそれで違ってきますからね。
即興と振付
一回性というのは寧ろ、型のあるものに出て来るんじゃないでしょうか。(隅田)
佐々木:飯名さんが川口隆夫さんとやっている『大野一雄について』という試みは、こういうことに対する応答なのかな、と思っているんですけどね。それは大野一雄という一世一代のものを完全コピーするといった、これまた変わってますよね。
飯名:『大野一雄について』は、過去のビデオを見て、動きだけを完全コピーする作品です。大野一雄は70歳を過ぎて『ラ・アルヘンチーナ頌』という作品で世界的に有名になっていくんですが、土方巽が演出しているんです。その後の『わたしのお母さん』『死海』という三作品までは土方巽が演出なんです。この三作品の抜粋を完全コピーするという作品です。即興だと思われていた大野一雄の舞踏に、実は再現性があることが分かってきます。皆さんの多くは「大野先生の踊りは即興だから」と言います。そして土方巽は即興ではなくフォルム・型であると言います。ところがその二つが合体したわけですね。即興と振付が拮抗するわけです。先ほど隅田さんが仰っていた一世一代のものが、世界各国で再演・再現されていく。そうすると、踊りの全てが即興というわけはないはずなんですが、「大野一雄は即興である」というところが神話化されているとも考えられます。「大野一雄は、いつも同じことやってますよ」なんて言うと、すごい怒られると思いますけど、でも動きのフレーズは沢山ストックされていて、即興的に動きのストックを引っ張り出して並べていく、ということのようです。
佐々木:すでにプログラムがあって、それをどうオペレーションしていくかで即興というものになるというのが、即興と言われているものだと思います。
飯名:『ラ・アルヘンチーナ頌』という初期の作品では、後半モダンダンスを踊りまくるんです。タンゴやショパンで、軽やかなモダンダンスを踊るんです。一般的な舞踏のイメージや、大野一雄の踊りが、その場で思いついたムーブメントであるということでも無くなってきます。
佐々木:一回性の伝説のようなものはありますよね。また、その伝説を一生懸命作っていたというのも、興行や運動性の中ではあったと思いますし、そこに立ち会った人へのサービス精神だとも思うんですよね。来てくれた人に、これは一回性ですよ、特別ですよ、とね。
隅田:一回性というのは寧ろ、型のあるものに出て来るんじゃないでしょうか。能の一回性とか。即興って同じ引き出しから表現を取り出しているように見えて、意外と”即興性”がないことが多い。
飯名:どれだけ動きの引き出しを持っておくのかということでしょうね。本番でその引き出しを開けまくるという作業があるわけですよね。そのことと徹底的に振付した動きというのは、何が違くて何が同じなのでしょうね。能は、同じ演目でも毎回違う感じがしますし、メンバーも違う。再現性のある芸術なのに即興性があるというのは不思議だなっていつも思うんですよね。
佐々木:一回性や即興の神話のようなものが作られていった感は否めなくないと思うんです。そして、その人ならではのようなものが出てきて、隅田さんが仰ったように、その人を追っていかないと、わからないというような感じになります。しかし、おかしいことに、その人ならではのものを見に行っているはずなのに、既視感があるんですね。その人が既にやったことの繰り返しという既視感ではなく、その人ではないもので感じた既視感と言いますか。
隅田:よく見ている方でもそうなんですね。
佐々木:最近あまり見ていませんが、たまに見に行ったときに、既知感がある。はじめてのダンサーを見ても既視感を感じるんです。
隅田:ダンス好きとしては、とりあえず踊りまくってくれれば文句はないんです。でも、踊り始めて何かが立ち上がってくる瞬間に、踊りが終わってしまって内面に戻ってしまうことが多い。
佐々木:もっと踊れと。
隅田:もっと踊って下さい(笑)。
佇まいだけで観客を納得させるダンサーもいます。
幕が開いた瞬間に「なんじゃこりゃ?!」て、こっちがびっくりするような人。(隅田)
飯名:ダンスをずっとやってきている人たちは、どこかダンスなるものに飽きてしまうこともある。自分が踊るということに関して、これまでの自分のダンスとは違う新しいダンス的なものを探っていくわけですよね。でも、観客からすると、踊っていないじゃん?!ってなったりする。でもアーティスト側からすれば、それが今の自分のダンスなわけです。それはどっちの味方をしていいのか、僕もよくわからなくなってくるんですが、大抵は踊らなくなってくる。そして演劇的にもなっていく。
佐々木:ある意味、踊らないで許されてしまっている部分があるんだと思います。規範に則った身体性を批判するために踊らない、ということはあると思うんですが、そういうことでもなく許されたんだと思いますよ。踊らないで突っ立って内面と格闘したりして、照明を変えて、陰影が出て、佇まいですね。それこそ、その人でしかありませんから、良いか悪いしかない。そして、ダンサーが踊らないというのは、それだけで意味を持ちますから、踊らないことが許されたんだと思います。でも、それってダンスなのか?という疑問が生まれますよね。
飯名:ダンスというジャンルの定義が崩れてしまって、コンテンポラリーダンスの次の区分けは何になってくのでしょうね。
佐々木:「いる」とか「ある」とかになってしまうじゃないですか、「ダンス」じゃなくて。
隅田:プレゼンスみたいな。
佐々木:「佇まい」とかですかね。
飯名:作り手たちはそういう身体性に移行しているかもしれない。
佐々木:「佇まいの芸術」ですかね。
飯名:「佇まいの芸術」というのはひとつの風潮としてあったのではないでしょうか。ダムタイプの高谷史郎さんがやっているパフォーマンスについて、川口隆夫さんから聞いたんだけど、「ヴィジュアルシアター」という構造があるそうなんです。時間軸を持ったインスタレーション、とも言えるかも。そういうコンセプトを持ち込んだとき、これまでのコンテンポラリーダンスとは全く別な身体が舞台上に居ることになりますよね。そういった舞台作品を、批評する側はどう見ていくのか、どう批判していくのか。
隅田:作り手側は何か新しいことを模索しているのかな。
佐々木:ダンサーではないですが、同じ作り手として思うのは、観客や批評家から「新しいことをやろうと思っているの?」と聞かれることがあるんですが、私には、「新しいことをやろう」って思われることが一番よくわからないですね。新しいことをやろうとしていると思われているんだ、と驚きます。新しいとか古いとか思って作ったことはほとんどないんですよね。それがある種の市場なりにさらされたときに、新しいということに価値を持っている人には、新しいことをしようとしている、新しくない、というように見られているのはわかります。新しいとかオリジナリティって何かの価値のように語られますが、そんなことを思ってやっていたら10年くらいで疲れるといいますか、その後は、新しいというよりも、なんで俺はこんなことをやってきちゃったんだろうか、という反省になっていってしまって、反省作業と言いますか、自分がそこに何を見出そうとしていたのか、という探求の作業に入っていってしまいまして、その中で、新しいと言われなくても言われてもいいしというのがありますよね。その探求の中で、「踊らず」に「佇まい」というのが出てきているんだと思いますが、しかし、それも探求においては、「佇まい」というのは、もういいんじゃないか、もう分かったろう、と思っちゃうんですよね。新しい以前に、「佇まい」という探求はもうだいたい分かったんじゃない?と思っちゃうんですよね。
隅田:とはいえ佇まいだけで観客を納得させるダンサーもいます。幕が開いた瞬間に「なんじゃこりゃ?!」て、こっちがびっくりするような人。
佐々木:舞踏の場合は、私は舞踏を知らないときに見て面白いなと思ったのはまさにそれですね。この人なんだろう?っていう人を見に行ったというのがありますね。
飯名:動物園的な「うわっ!ライオンだ!スゲー」みたいな。
隅田:だけどそれは演じ手側が、最初から狙ってよいのかは疑問ですね。いろいろな複合的なものあって、結果的に佇まいだけで圧倒できるようになるんだと思う。
飯名:演じ手がそれを意図的に狙っちゃだめなんでしょうね。
演出家がイメージを受胎する(佐々木)
ベジャールは、”散文”と”詩”の両面を持っていますね。(隅田)
佐々木:演出家がそういうことをきちんとやるというのが一つですよね。劇団解体社はそういうものの一つだと思いますが、見るものは完成された美学に対する欲望のようなものを持っているわけですよね。それに寄り添うと見ているものは楽しく、満足しますよね。劇団解体社の演出家の清水信臣さんは、切断、と言ったりするんですよね。見ているものの欲望も途中で切断される。それは見るものにとってはストレスだし、不安になりますし、そういうことを行うということは一つの探求的な舞台のあり方だと思うんですよね。劇団解体社は舞踏の系譜ですので、舞踏はそれまであった美的な完成を破壊するというか、切断するというようなことがあったと思うんですね。
飯名:それは演出家の意図として?
佐々木:ええ、意図として。
飯名:そこに出てくるパフォーマーやダンサーというのは、どういう位置付けになるんですか?例えば、解体社などでは取り扱われているんですか?
佐々木:清水さんのお話では、まず、パフォーマー、ダンサーが変な動きをすると、それは拒絶反応であったり様々ですが、ある種の遂行行為が出来ないような状態などが露出したときなどに、切断などが浮かび上がるというようなことをおっしゃっていました。
飯名:先にイメージがあるというよりは、何かをやっているときに、こうなっちゃったというものがあるわけですね。
佐々木:それは何か?と思って、演出家がイメージを受胎するだと思います。例えば、手を伸ばそうとしたときに伸びない、伸びないとは何か。綺麗に手を伸ばそうとしたときに、伸びない人に起こった抵抗、反抗はいったい何か。というようなことに感じるんですよね。しかし、見ている方からすれば、手が伸びるべきときに手がスッと綺麗に伸びてくれた方が気持ちがいいわけですよね。見るものの欲望は。しかし、そこで伸びない、伸びないだけでなく、その手が予期しない方向に行く、こういったことは舞踏の作り方として、とてもわかりやすいと思うんですよね。見ているものの美学が挑発されるというんですかね。
飯名:そこはバレエとかモダンダンスとは一線を画すんですかね。
佐々木:意識的にバレエ的な美学に分かりやすく反発しましたよね、土方さんは。白塗りではなく黒塗りにしたり、上に行くのではなく、下に行くんだとか。
隅田:バレエのトレーニングを土方巽は受けてますよね?
佐々木:土方はノイエタンツとかやってませんでしたっけ?
飯名:土方巽は、ジャズダンスのテレビ番組とかに出てました。当時、安藤三子ユニークバレエ団に所属していたり、石井みどりさんのところにも行っていたようです。男のバレエダンサーが少なかったから、相手役に呼ばれていたそうです。
佐々木:コンテンポラリーダンスの踊れない、踊らない問題で大きいのは、ウィリアム・フォーサイスとかを見てて、踊るのをやめるとかは、緊張感があって、しかもダンサーとして出来上がった体が踊らないというのと、その辺の人に近い人が踊らない、というのはまったく違うという特権性がありました。たぶん、コンテンポラリーダンスは、その辺にいそうな人が踊らない、ということをやってしまったから、見ている人からすれば、それはなあ、というのがあるんだと思うんですよね。
隅田:私は恥ずかしながら、「コドモ身体」を自分では観ていないのですが、新聞とかダンス以外のメディアにも取り上げられているのを良く見ました。なので想像ですが、言葉にしやすかったんじゃないですか?「コドモ身体」を元にいろんな思想を語れた。
佐々木:ポストモダンっぽい思想に相性が良かったんじゃないですかね。並列化やスーパーフラットみたいなものと。
隅田:フォーサイスは、実際舞台で起きていることを言葉で書くのは大変ですよね。
佐々木:フォーサイスを書くのは大変だけれども、コンテンポラリーダンスの新しい人のは参照となる過去の公演が少ないし、見ている人も少ないから、比較的簡単に書けちゃえるというのがあったんじゃないですか。
飯名:散文的ダンス作品というのは、解説しやすい。内容を書きやすいはずです。でも、ダンスっていうのは詩的なものだと思うんですよ。隅田さんの『クロッシング』という詩集を読んで、「どうでした?」って感想を聞かれても、瞬時に言葉が浮かばない。詩を読んだときに感じたその空気感って、言葉にしにくい。ダンスもそうなんじゃないかと思うんですよね。ピナ・バウシュのタンツテアターが登場してきて、ダンス作品に散文的情景が描かれるようになったかもしれない。
隅田:ピナ・バウシュは、ダンス以外の分野の人にも好かれますね。
飯名:散文的なところが接しやすいからかもしれない。マース・カニングハムのダンス作品観て、これが何の話なのかなんて分からないですけども、ピナ・バウシュの作品はどこか物語的な印象を持ちます。
隅田:ベジャールは、”散文”と”詩”の両面を持っていますね。
詩はネタバレもないですからね。(佐々木)
詩のあらすじ書けっていわれてもね。(飯名)
飯名:隅田さんをお招きしてますから、是非「詩的なもの」ということを話せればと思ってるんです。
隅田:詩は極端な話、行間を読めって言われることもありまして。書かれていないものを読め、と。
飯名:書かれていないものを読むって、改めて面白いなと思います。僕は映像の仕事もやっているんですが、映画監督のアンドレイ・タルコフスキーは「詩」について『映像のポエジア・刻印された時間』に書いています。詩的な映像って何かなというと、ただ長回しするとか、そういうことじゃない。抽象化してデザイン的なイメージではいうのではなくて、もっと詩的な行為、感覚がある。『サクリファイス』というタルコフスキーの映画があって、DVDで買ったら、立派な冊子に日野啓三の解説が入っていて「タルコフスキーはイラついているんだ」って書いてあった。「かつて詩というのは世界を表現できるメディアであった」と。叙事詩、叙情詩であったり、詩があれば世界はすべて表現できた。しかし今は、詩なんて書いてもしょうがないじゃない、詩なんて読んだってしょうがないじゃないってなってきた。誰も詩を読まなくなった。つまり詩が古いのではなくて、詩を読める人がいなくなったから、問題なんだと。そのことにタルコフスキーはイラついているんだ。って、解説で書いてあった。こういう時代背景から、詩のような感覚的なところから立ち上げたダンスって、どう感想を言えばいいのか難しい行為なんだなと思いました。タスコフスキーの映画って、核戦争の話だったり、人間が持ってる希望だったり、トルストイじゃないけど、人間への教訓的な事柄や、宗教とはまだ別な信仰心なども入っているんだけど、そのことについて論じる人は少ないようです。映像的な手法について語られていることが多い。
佐々木:詩もあるときに詩の終わりがきたと思うんですよね。それは荒川洋治さんや、ねじめ正一さんは意識的にそうしたように思うんですよね。詩は霊感か技術かという議論が荒川洋治さんと入澤康夫さんとでありましたが、荒川さんは技術だというんですね。で、荒川さんの書くものは読みやすかったし、とっつきやすかったいうのがありました。それは詩を読んだことがない人でも、荒川さんやねじめさんの詩はニヤニヤしながら読めてしまうと思うんですよね。
でも、読んでいるときは楽しいんですけど、二度三度と読み返す気がしないんです。一回読んで終わるというんですかね。一回性でいい、ということなのかわかりませんが、一回読めば満足するような詩なんですよね。
飯名:もう一回読みたくなる詩って、例えばどんな詩人?
佐々木:私はちょっと趣味が偏っていて、頭のおかしい人かと思われてしまうかもしれませんが、マラルメから始まり、日本の詩人で言うと、吉田一穂や北園克衛が好きでしたね。
飯名:もう一回読みたいっていうのは、なんでなの?
佐々木:一言だけとかが印象に残っているんですよね。で、その一言が映像のように残ってしまっていて、それがなんだったんだろうか、ともう一度読みたくなるんですよね。読んでおきながら、説明ができないんですよ、自分に。
隅田:観客は、分からないままにしておくことが苦手になってきているのではないでしょうか。例えば、難しい映画を見て分からないと、Wikipediaや、誰かのブログのネタバレとかを読んで答えを探す。分からないまま一旦寝かせておくというのを、観客の側もしなくなっている。
佐々木:まあ、詩はネタバレもないですからね。
飯名:詩のあらすじ書けっていわれてもね。
隅田:無理ですよね。それと同時に、ここまでは書かれているので、ここまでは分かって欲しいというのもありますね。
佐々木:そこは書いてあるから分かって欲しいというのはありますよね。私は20歳くらいのころに入澤康夫さんに詩を見てもらっていたことがあって、そのときに言われたのは、「君の詩の中で分かり易いのは全部ダメだ。分からない詩こそいい」と言われたのを憶えてます。水野さんとの鼎談でも話しましたが、三島由紀夫が『太陽と鉄』で、言葉は基本的にはお互いが理解し合うためのツールであって共有されていくものであるが、芸術というのは個人的なものであるから、共有されるツールとしての言葉を芸術化するということは、ツールとしての言葉を役に立たなくさせていくことになるんだという、これは「ダンスと言葉」を考えるときのキーだと思います。言葉が個人化してしまうと、たった一人の言葉のようになり、言葉の有用性を考えると無用になっていってしまうことが言葉の芸術なんですよね。そして三島は、私はそこまで行けないということで、肉体という最初から個人的なものを鍛えることで、神輿を担ぐ青年たちと仰ぐ青空を共有しようとしたんですね。
隅田:三島が言うならしょうがない。だけど例えば文章を書き始めたばかりの人が「俺の言葉は私的化している」って言っていいのか(笑)。
佐々木:しかしですね、書きはじめの言葉を知らない人の方がもしかしたら、その人が中途半端に覚えてから書くよりも良いかもしれない。
飯名:ビギナーズラックのような。
コンテンポラリーダンスという、
どぶさらい作業の中で砂金を見つけようとしているんだ(佐々木)
佐々木:言葉がうまく繋がっていない方が、その人がどう考えているのかを的確にわかるのは難しいですが、事故のように読み手に誤読させ、何かが起こるかもしれませんよね。コンテンポラリーダンスの最初もそういうところがあったんじゃないですか?誤読させたというような意味で。
飯名:誤読の面白さがあったと思うんですよね。まずは、なんだろうこれっていうのがあり、なんだか分からないから、もう一度そこに行ってみようっていうことだったんだと思うけど。それがジャンル化されてきて、「これがコンテンポラリーダンスです」というのが薄らと出来上がってきちゃう。アヴァンギャルド、ニューウェーヴにしても何年かすると、それがジャンル化されてきて、そこからどうやって逃げるかという作業が始まる。
佐々木:10年くらい前ですかね、コンテンポラリーダンスの企画に関わりはじめたばかりのとき、ふと「なんでコンテンポラリーダンスをやってるの?」って聞いてみたんですよね。すると、「バレエをやっていても、プリンシパルになれないんで」って言われまして、中西レモンに「コンテンポラリーダンスってのはなんだかひどいんじゃないか」って話すと、「どぶさらい作業みたいなものだよ」っていうんですよね。
飯名:言葉が悪い(笑)。
佐々木:まあ、彼はコンテンポラリーダンスというどぶさらい作業の中で砂金を見つけようとしているんだと思いますが。
<続く>