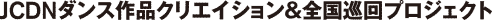2016年03月05日
鼎談「ダンスと言葉」
会場:未生文庫
<ダンスにしか出来ないことがある>
水野:飯名さんも佐々木さんも、身体の人じゃないですよね?
佐々木:お前ら鍛えてもいねーじゃんと?(笑)
水野:そういう意味じゃないですよ(笑)。今まで散々、言葉での意義や説明の必要性を言ってきましたが、それでも、とても抽象的なダンスでの表現の言葉にし難い部分についてというか、感覚的なことかもしれないですが、やはりダンスって説明しようとした時、弱い物だと思うんです。そのためには、ダンス作品を作る時に、詩だったり音楽だったり、美術だったりいろいろなモノの力を借りて、あるいは、引き算して伝えようとする。だからダンスって本来、色んなジャンルと強く結びついているとも云えますよね。同時に、ダンスでしか見ることのできなかった風景というのも、いくつか出会ってきていて、私がこういう“ダンス”っていうものには特別な想いをもっているのも確かだからこそ、「踊2」を“ダンス作品”と言っているのでしょうね。ダンスという表現が、説明できない何かが残っている、それが特徴として魅力になっている、というのはある。
佐々木:それは「あなたは私ではない」ということだと思う。私しかこの場で踊っていないというような、さっきの話だと孤立性。言葉が様々な人に共有できるためにあるとしたならば、ダンスは共有できない。圧倒的に。
水野:存在っていうものが、肉の塊というか身体から出てくる表現というものは必ずあると思っているんですよ。ただそれが盲目的にそれしかないんだと思っているわけじゃなく、全てのものを語りつくした中でこぼれるものが最終的にあって、そこの美学は信じていますね。それに出会った時、ワクワクしたり、想像が膨らむことの楽しさ、快楽を知っているのかもしれない。かといって言葉の否定では無いですけど。
飯名:ダンスでしかできない事があると思うんですね。なので、自分の作品の中にダンスを入れたいわけです。言葉では説明できない、ってことが、ダンスという形式を使えば説明できるかも、と思うからです。例えば映像で、キューバの風景とかアフリカの風景とか、東京の風景とか具体的に見せていくことはできます。でも、作品で見せたいことは、具体的な風景を見せたいわけじゃなくて、観客の想像力によってその風景を生み出したいわけです。
水野:風景が必要になってくるんだね。
飯名:そう。空間に立っただけで、背後の風景が広大になっていくダンサーもいますよね。空間に空気が流れはじめるダンサー。それは、テクニックの上で上手いとか下手とかじゃなくて、説明のつかない存在・肉体の中で、圧倒的な何かです。この感覚は専門家でなくても直感的にわかることです。「何か知らんが、このダンサー凄い!」って直感的に感じますし、そのことは観客も感じます。専門的に色々分析していけばこういう風なテクニックを使っているのだろう、とか、色々あるんだろうけど、素直に観客として観るときはそこまで分析的に見ているわけじゃない。でもそのダンスに触れたときに「風を感じた」とか、「匂いを感じました」とか、お客さんからそういった感覚的な感想が出たりしますよね。それは詩に似てると思うんです。散文じゃなくて詩です。文章としてはスカスカで隙間だらけだけど、何行か読んでいくと、そこには一言も出てない言葉なのに、この詩は春っぽいとか、茶色っぽいとか、このひとは死んだんじゃないかとか、色々感じる。「ダンスと言葉」というテーマで、あえて限定して言うと、ダンスに表現できることって詩に近いのかな、とか思ったりしますね。 詩にかわるものとしてのダンス。でも詩の朗読って難しいですよねー。
佐々木:超絶技巧のダンスみたいなものを見てもなんとも思わないわけですよね。
飯名:超絶技巧プラス何か、というところでしょうかね。基本的な技術はないと、それはそれで表現に至らないこともあります。
佐々木:この人はどんなことを見て考えて、今この人にはどんな景色が見えているんだろうな、映ってるんだろうなって思うダンスに惹かれることはありますね。
飯名:僕は、その人がどうやって生きてきたんだろうかとか、どこから来たんだろうかとか、そのダンサーのミステリアスな部分みたいなものに惹かれるんです。
水野:なるほど。人間臭いというか、ダンスと生きるということは、何故こうも密接に感じ取ってしまうのかな。それがあるから、ダンスを観ると人は熱くなるのかもしれない。毎回それを強く感じてしまうダンスは、私にとっては室伏鴻さんでした。室伏さんの舞台のリノリウムに残す銀粉の足の跡をみていると、なんか人生の足跡のようにみえてくる。あの無茶苦茶な生き方と誠実さが両方存在しているダンス。人間そのもののダンス。「喜怒哀楽」っていうのバカにしていたけど、いや、まさにそういうダンスだったなあと。
飯名:結局それがある程度の時期まで習い事でできてた部分が、自分の作品を作るってなった時に、生きてる人生の部分の充実度とか目的意識みたいなところが、ある人・希薄な人ではおんなじテクニックを持ってても全然違う踊りになっちゃう。それがおそらくモダンダンスとか群舞でダンサーとして雇われてやっているっていうレベルだと、おそらくそこまで考えなくてもできちゃうんだと思う。考えなくてもできるようにシステムが作られてるんだと思う。それをメソッドとして、
佐々木:言葉を廃してる。
<言葉が排斥されてしまったダンス>
水野:土方さんの「病める舞姫」は、読むたびに全然わからなくなります。頭が空白になっていく感じ、アレは何故ですか?佐々木さん。
佐々木:何ていうんですかね、土方さんのテキスト読むと分かる分からないというよりも熱にうかされて読む感じですかね。
水野:土方さんのダンスですね。
佐々木:僕も適当なことばかり言いますが、以前、土方さんの奥さんの元藤さんに「これ何なんですか?」とそうすると「土方はああいうことばかりしょっちゅう言っていたんだ。」と。日常だったんですね。なので、それを本気にして、土方さんの日常に触れるつもりで『病める舞姫』を読んでいました。『慈悲心鳥』も、日常的にヘンな人として僕は楽しいんでいた。理解しようというより、土方を自分がどう思うか、土方がダンスに何を求めているか、自分はそのイメージから何を喚起するのか、という感じですかね。詩を読むにしても、詩の全体よりも一行、一言でも、それこそ誤読でもいいんです。それによって自分の中で何が起こるのか、というのが大事ですよね。
飯名:ダンスもそういう意味で、60分の作品だったら60分間ずーっと良い必要は無い。作品の中のどっかに、自分の中の何かを喚起させてくれる瞬間があればお客さんとして大満足なんじゃないかと思います。そういう瞬間に出会いたいはずです。土方巽の文章ってどんどん夢のように切り替わっていっていきますよね、一見脈略無く。大野一雄もそうかもしれません。
水野:多くの人がやられてしまう、てことですよね。佐々木さんは作品を上演する時に、必ず客席に土方さんが座っていると想定すると聞きましたが、30代でそういう設定をする人も少ないと思うけれど(笑)、今この時代にそういう表現を作りたいし、求めているし、今生きてる私たち世代が見たいですね。
飯名:そのことは単に土方巽のようなことをやるわけじゃなくて、現代のものとした時に土方のエッセンスみたいなものがキチンと引き継がれるか、ということ。単に真似して、今ああいうことやっても「いまどき、なにアングラなことしてんの?!」って言われちゃう。それぞれに、エッセンスを掴むべきなんですね。
水野:少なくとも今のダンスに足りないのは、言葉を排斥してしまったことですよね。
佐々木:僕みたいな実際に会ってない世代に土方さんの影響があるかというと、言葉には巻き込む要素があり、誰にでも入り込める隙がある。もちろん、正確になんて理解できている人はいるのかもしれませんが、土方のテキストは誤読がしやすくできてると思います。さっきの水野さんが言ったダンスのように、なんでもくっつく。それが面白いんだと思いますね。写真家たちが土方を撮っていったように、土方のテキストは読む人が勝手に誤読する。今のダンスの現場での問題は、そういった言葉だけじゃなく、巻き込める状況を作れていないからじゃないかと思う。それはもしかしたら、観客席から「踊りが見たいんだ」「感動したいんだ」という欲望だけしか捉えようとしていないからかもしれない。
飯名:踊りの量として多い少ないじゃなくて、そこに行われてる身体表現の中身ですよね。それが意味が分からなければ、意味が分からないということに観客が揺さぶられたり、興味を持っちゃったり、あるいは腹が立ってきたりする。そういう感情の揺さぶりが生まれます。やる側も責任を持って通じない言葉を徹底的に執拗に表現する、ということも必要です。それに対して「それじゃ通じないよ」ってときに、次の議論に進む。舞踏の面白さというのは、踊ってる時間より議論の時間が長いんじゃないか?!みたいなクリエイションのプロセスでもあります。思考することと踊りが一体化してくるんでしょうかね?踊って伝わらないものを、何とかその後の飲み会で回収しようとしたり、言葉で攻撃してくる人との対立だったりも生まれます。時代性もあるかもしれませんけども、そういうコミュニケーションが生まれてた現場だったのでしょうね。今でも舞踏ファンはそういうところを大事にしていると感じますね。ダンスを劇場の中、ファンタジーの中だけに留まらせず、会話として外に、日常の世界に出していく感じです。
水野:表現することに賭けているし、生きていることと地続きだから。
飯名:話をまとめる、というための会話ではなく、あくまでも議論というか、言葉を発し合うという作業なわけですけども、それが会話する人たちの表現行為ということですから。
<魅力ある言葉を発する振付家>
水野:一昔前は、作品について語ることは否定肯定ではなく、楽しいことだった。観客もかなり熱く語ったりしてね。私が若かりし頃の舞踏の作品制作の稽古現場では、演出家や振付家が出演者に話していることが、意味不明でもおもしろかったですよ。まあ最初の頃、一体何をいっているのかさっぱりわからなかったですね。だけどその言葉の意味や世界観といういうものを必死でみようとすることに、本来、成り立たないコミュニケーションが成立し始めてきて、それがダンスとし立ち上がってくることに、血が沸くというんでしょうかね。(笑)言葉をダンスで紐解く作業が舞踏の振付けだったのかもしれない。
佐々木:ダンスも言葉も一つ共通点があって、「あんたと私は違うんだ」って宣言ができることなんですよね。そうすると対立が生まれちゃうわけだけれど、それを恐れる、嫌がる空気があります。だからなんとなく違うけれどあるあるというところを探りあうようになるから、舞台の公演とか見ても自分とは決定的に違う、不快というものよりも、なんとなく自分の好きなものを、自分でも受けとめやすいものを探すようになる。そうすると共感する公約数の人たちばっかり集まるようになる。
飯名:演出家とか振付家が、魅力のある言葉を発する人は面白いなと思う。ジャンルは問わず、その人が何かの状況でぽっと言ったことが凄く自分にとってインパクトがあるみたいなことです。そういう言葉を発する人って必ずしも分かりやすい言葉じゃない。結構時間掛けて考えないと、「それってつまりどういうことなんだろうな?」って理解できない。僕が映像作家として舞台作品に関わっているときに、演出家から「この作品はこういう感じにしたいんだ」ってことが、分かりやすく説明されるとあんまりイメージが伸びない。僕の中で。だけど「え?それってどういうこと??」っていう言葉が飛んで来るとき、それはイメージに近い言葉だったりします。その言葉のチョイスのセンスみたいなものに惹かれて、「なるほどねー、たぶん、こういう感じなんだろうなー」ってなる。そういうことが結構あって、単にこういう風にしてくださいねーって分かりやすくディレクションする人が必ずしもやりやすいわけじゃなくて、逆に僕なんかは「それだったら、若い映像作家に頼んだほうがいいんじゃないですか?」ってなる。演出家が稽古場で面白い事言うなーってとき、すごい惹かれるんですよ。
佐々木:理解というより受肉なんて言いますよね。受胎ってのも近いかもしれません。その場では自分が何をするのかは出てと来ないんだけど、その言葉や動きから作られていく。劇団解体社の演出家清水信臣さんは、受肉、受胎させるような言葉やイメージ、思考を出したあとに、意識的に一生懸命説明するんですが、説明が詩的といいますか、説明の中にまたバンバン出てくるんですよね、すぐに理解できなそうなことや、直覚的にピンとくるものが。それが数ヶ月経って、ああ、あの事はこういうことだったのかって自分なりにわかるときがあります。
飯名:受肉って、まさにそれかもしれませんね。そういう言葉を発する人って、恐らく「今回の作品はこういう事なんだ」ってずっと孤独に考えてるんですよね。それ以上でもそれ以下でもない、言葉にするならこういう風に言うしかない、みたいなところでクリエイションしている。だから毎回同じこと言うわけでなく、言葉上、矛盾したことも言い出します。でも、その言葉にたどり着くには、参加しているクリエーターが、演出家のイメージにどうやってたどり着くか、というかなりの努力も必要です。演出家の脳ミソ開けても見えてきませんしね。共通言語としての「言葉」によって通じてくることを想像するしかない。そこに言葉の奥深さというのを感じます。