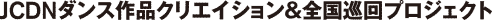2016年02月20日
文・黒田瑞仁
「踊りに行くぜ!!」2の日本各所をめぐるツアーは、1月に始まる。その一箇所目はどうやら決まって北海道の札幌市であるらしい。1月の北海道は寒いだろうになあと思ったが、とにかく私はその取材をするべく東京から現地に向かった。前情報として知っていたのは、「踊りに行くぜ!!」2のプログラム・ディレクターの水野さん曰く「会場であるコンカリーニョとは付き合いが長く、作品制作に何かと融通してくれるので一箇所目の会場としてやりやすい。」ということ。その時はそういうこともあるんだろうなと思っていたが、実際に現地に行くと「踊2」のようなイベントにとっての劇場との連携が持ってくる意味と、そしてコンカリーニョの特異さが際立った。
さて、会場となるコンカリーニョは劇場と称してはおらず、生活支援型文化施設コンカリーニョというのがフルネームだ。札幌駅からJR舞鶴線で二駅の琴似駅直結といって中心地からのアクセスが良い。駅直結と聞いていたので、駅の目の前に一味違った建物がドーンと建っているものと思っていた。しかしいざ着いてみると劇場然としたヘンテコな建物は見当たらず、行き方がわからない。商業施設の充実した駅前に、雪が積もっていた。そしてさすが北国というべきか、外気に触れず行き来できるように駅前の大きな建物はほとんど数珠繋ぎにつながっているのだった。
その数珠繋ぎを辿っては戻り、私は10分ほど完全な無駄足を踏んだあと、コンカリーニョの方向を示す看板を見つけた。看板の矢印を信じ、階段を上がったり下がったりするとたどり着いたのは医療クリニックと薬局の入った建物で、伸びている廊下は病院のそれのように白く清潔で装飾気がない。同時に頼りの矢印がそこで途絶えたので、私はまたその建物のなかを困り果ててウロウロするはめになった。そうしてまたしばらく時間を浪費した後、私は行き止まりのような場所に出た。そしてその先に何もないだろう廊下としか思えなかった先に、やっと、カラフルなConCarinoの文字をたたえた小さなパネルが掛かっているのを見つけたのだった。その傍らにあったドアの取っ手を開けると、劇場が姿を現した。


病院のように清潔でプレーンな、私が散々ウロウロしてしまった廊下とはまったく違う世界が広がっていた。まず、埃の匂いがする。正面口である二枚組のドアを入ると、工事現場の足場を組むパイプで段状に組まれた客席の背後に立つことになる。パイプの上には使い古されて風合いの出た板が敷かれていて、その上に椅子が並べられる。劇場は内部にロビーも何もない一つの大きな箱の形をした空間の中に、200人弱は座れるであろう観客席があり、のこりの空間が舞台になっている。客席脇の通路には所狭しと金属ラックに公演の宣伝チラシが並べられ、そしてこれが何より印象的だったのだが、大きな円柱型の石油ストーブがオレンジ色の光を放っていた。ちなみにこのストーブは私がコンカリーニョに入った夜に行われた最終リハーサルの暗転中も、本来は真っ暗なはずの舞台空間に煌々と熱と光を発し続けていて、いかにも北海道の劇場に来たのだと私に思わせた。
コンカリーニョは、自身が入っている施設建築そのものよりも内部のその空間だけが古くからそこにあるような、何もかも使い込まれた場所だった。むしろどんな小綺麗な最新型の劇場よりも芝居小屋の雰囲気すら漂う、劇場としか言いようのない空間だった。
私が潜り込んだその時はちょうど公演の前日、最終リハーサルを控えた時間帯で、舞台上には複数のチームがウォーミングアップや、振り付けの確認をしている。ダンサーといえば薄着で動きやすい格好をしているものばかりと思っていたが、ここではみんな厚着だ。ダウンジャケットを着込み、裸足ではなくモコモコしたスリッパを履いている。もちろん雪の積もっている外に比べれば、中はだいぶ暖かいのだが、コートを脱がなくても暑すぎない温度ではある。そんな舞台を忙しそうに横切るのは、やはりダウンジャケットを着込み照明機材を抱えた照明家や、舞台監督や、それぞれセッティングら舞台上の掃除をする人たち。客席には、運営の人、関係者の家族、写真家、そのほか(私自身を含め)よくわからない人たち。
まるで夢の中でドアをくぐると全く別の場所に出てしまうように、あまりに突然あらわれたその有機的なこの場所は、それ自体が劇的な体験をもたらす。「踊2」の東京会場であるアサヒ・アートスクエアのような奇抜な外観もなく、世田谷のシアタートラムのような観客の気分を盛り立てる光の廊下もなく、利休がとにかく客の意識を抑圧させて抹茶という劇薬の脳への効果を最大限引き出そうと茶室にこめた理念とは真逆に、落とし穴の中にあるかのように都会の中に突如姿を現わした。観客としてそこに入って、さらに舞台装置が組んであればその驚きは倍増しただろう。自分の生活とは懸け離れた世界感を表現者から直でぶつけられるような場所だった。一つの大空間に客席と舞台が、幕などの仕切りなく近い関係で接し合うこういう場所は、上演の見やすさはもちろん、パフォーマーにとっても観客が近い。まさに「踊2」の一つ目の会場としてアーティストが出来立ての作品をお披露目しその反応を感じられる場所だ。


ほかにもコンカリーニョには変わったところがある。舞台裏の空間も一つであって、細かく区切られていない。倉庫と搬入口と、場合によっては観客に見せる奥舞台が、舞台から壁一枚隔てて、奥に横たわる。客席から舞台裏に到達するには、裏の通路はなく舞台を横切るほかはない。事務所や楽屋はというと、なんとこの奥の空間の中に、小さな二階建ての屋根のない家のように建っているのだ。一階が楽屋とトイレで、二階が事務所と楽屋がもう一つ。事務所の二階から、舞台側の二階回廊に出られるようになっている。
この不思議な入れ子構造がなぜ出来たかは、本番後の打ち上げの席でコンカリーニョの立ち上げに関わった照明スタッフの高橋さんが教えてくれた。どうやら駅前という立地、病院と抱き合わせの施設の条件、当時の予算的にも、普通の設備を揃えた劇場はできそうになかった。だがどうにかして舞台芸術の場をそこに作りたかった人たちは、建物の中に建物を建て、舞台関係者のネットワークを使い方々から劇場を成立させるために必要な機材を集め、とうとう客席まで自分たちでパイプと板を見つけてきて組んでしまったそうだ。シンプルで使いやすい空間を優先してつくったので、客席も舞台もすべて組み替えられるようにしたというのだ。その熱意が、この生活支援型文化施設コンカリーニョという稀に見る舞台空間を作り上げてしまった。
コンカリーニョでどんな人たちが誰と作品を作り上げていたかはこちらを参照されたい。https://flic.kr/s/aHskpCaaRd
もちろんこの熱意は、ここで作品を発表する作り手を大いに助けている。たとえば、今回の「踊2」のCプログラムとして発表した、地元高校生ダンサーの本田大河さんの作品は『人性』というタイトル。

スマートフォンが小道具として登場し、どこか観客の大勢にとって覚えのあるような年頃の葛藤を感じさせながら、彼の手足は何かを掴むべく空を切るように踊りまくる。他の作品は専門家の集合としてチームを組んで公演を実現させる中、本田さんは作・演出・構成・振付・出演を自分でこなしていた。札幌プログラムの唯一のソロ作品であったことと、彼の年齢ゆえの生生しい表現は、演出家の作品という傾向の強い他の3作品を相対化し、そのプリミティブな存在感を強く放っていたと思う。
ただし、若いダンサーが一人だけで練達の作家たちと同じ舞台に立つということは大変だ。Cプロとしての上演が決まった本田さんは、作品の舞台セットをどうするか迷っていたらしい。彼と打ち合わせをする中でコンカリーニョのスタッフさんが一つ提案をした。本田さん曰く、たまたま巨大なトイレットペーパーが劇場にあるので、舞台装置として使ってみないかと言われたという。なぜそんなものがコンカリーニョにたまたまあったのかはわからないが、この案は採用されて、本番では舞台の片側に幅3~4mはあろうかという大きな白いパーパーが舞台の二階通路から垂れ下がり、本田さんがその背後で踊れば彼のシルエットを映し出していたし、作品のクライマックスでは本田さんがこれを突き破ったりと、作品の構成に幅をもたせていた。劇場のスタッフが作品に提案を持ち込むというのは、決して舞台芸術では通例ではない。通常、場所を貸す側の人間であって、作る側ではないからだ。
ちなみに、「踊2」ではプロデューサーも作品に口を出す。たとえばプログラム・ディレクターの水野さんは時にはリハーサルや本番を見て作品にコメントを出し、時には作り手と意見が食い違ったとしても、作品を育てていくというスタンスだ。運営・制作スタッフが堂々と作品にコメントをするのは、相当珍しいのではないかと思う。私が到着した日に本田さんの作品は二度リハーサルが行われたが、実際水野さんは「一回目より二回目のほうがよかった!でも最後がまだ弱いね!」と遠慮なく伝えていて、具体的なアドバイスもしていた。もちろん他の作家に対しても水野さんは積極的にコメントをして、それを作り手は作品に取り入れたり、無視したりしている。
このまま他の上演作品についても紹介したい。観客が入った実際の上演では本田さんの作品が1作品目、Aプロの2作品が続き、最後にBプロの作品がしめる。Bプロは作品そのものが地元から持ち込まれるCプロとは異なり、広く活躍する作家が、地域に出演者を募り、一ヶ月程度で作品を作り上げるという形式だ。


これを担当した東野祥子さんの『現代版 −7つの大罪− 第一章』は、7人の札幌を拠点に活動する出演者と作られた。7人はそれぞれバレエダンサー、コンテンポラリーダンサー、舞台俳優などで、それぞれ普段は別々の世界で活躍している。観客もBプロの出演者の知り合いが多いようだった。特に2人の出演者はバレエ教室の先生をしており、本番の客席には小学生くらいの髪をアップにお団子にした女の子とその保護者が何組も来ていた。きっとコンテンポラリーダンスや舞踏なんて初めて観たであろう彼女らは、7つの大罪になってしまった先生や、他の作家の作品をどう見たのだろうか。この出会いはAプロだけを上演する東京公演ではありえない。
普段は劇場以外にも、野外や学校建築、お化け屋敷公演といった変わった場所で作品作りをするという活動を続けている東野さんの作品は、広い劇場をフルに使った仕掛けが目白押しだった。札幌以降も各地を転々とするAプロ作品とは違って、BプロCプロは開催地ごとの限定公演。その劇場機構に特化した作品作りが可能だ。冒頭から高い天井高を利用して3mはあろうかという巨大な人物が現れ、かと思えば舞台奥の壁に絵を描きなぐり(勿論そんなことができる劇場ばかりではない)、枯葉がバサバサと二階通路から落ちてきて、最後は舞台奥が大きく開き劇場の裏側が露見する。音も自前の機材から、即興で繰り出される。バレエからセリフと専門の違う出演者が入れ替わりで、踊り、演技をして、集団で舞い、罪を犯しながら陰気な後ろめたさを感じないカラッとしてダークな世界観が展開された。視覚と聴覚をストレートに使った楽しませ方は、客席に多く押しかけていた出演者の友人たちを釘付けにしたし、プログラムの最後の作品として観客の拍手もひときわ大きく響いた。
その一方で、Aプログラムはわかりやすいというわけにはいかない。むしろ、率先して観客の正常な判断力を奪おうとしてくる作品たちだ。


平井優子さんの『Ghosting ー 軌跡の庭』は、作品制作中のインタビューで地のない庭を作ることを目的の一つとして掲げていた作品だ。真っ白いスモークに包まれた曖昧な空間の中で、二人のダンサーの人影が踊る。この二人の出演者のうち片方は平井さん自身で、明るい色のワンピースを着た彼女が舞台上に立つと、少女のようにも見える。そんな彼女が現れたり消えたりしながら、共演者の中尾さんと出会うと二人があるいは互いの影、ポジとネガや、ドッペルゲンガーのように見えてくる。そして二人以外にも、別の存在が作品空間に現れる。それは舞台上を動き回る映像なのだが、その何者かの動き回る映像は、その動く軌跡は毎回変化するのだという。あらかじめ組まれた映像プログラムの数値を上演中にいじり、ダンサーは物理的に存在しないはずの映像と即興を演じることができるのだ。
ところで演劇では一度舞台を暗くして暗転すると、場所や時間を別のところに移動させてもいいという了解があるが、平井作品の白いスモークとどこまでも輪郭をぼかす人物の縮尺も、年齢や、存在、空間をも曖昧に感じさせる。壁がどこかもわからないような世界観が私の認識を侵しはじめ、客席を離れても舞台の扉を出て市街に戻ることができないのではないかとすら思えてくる。舞台空間全体を直接的に表現に巻き込む作品なので、「踊2」で上演場所を変え舞台空間が変わるごとに別の見え方がするだろう。
『足の甲を乾いている光にさらす』は普段はニューヨークで活躍する山崎広太さんの作品。こちらは暗黒舞踏の表現せんとする「暗黒」に注目して取り上げた作品だ。ダンサーたちは全く独立しており、連動することなく舞踏の動きをしている。あまりに無関係に動いているのでこれもだんだん3人の物理的な距離感までよくわからなくなってきて、宇宙空間に点在する近いように見えて実は何光年も離れた星のように思えてくる。目立った舞台装置も、照明効果もないにも関わらず、だ。そして出演者は3人のほかに、演出の山崎さんも四人目として時たま山崎広太さん自身として出てきては、踊らず、喋る。「暗黒」というものについて、彼の思い出や、解釈を語るのだが、とても「なるほど」と思えるようなものではなく、私たち観客はポカンとするしかない。次第にどうやらそんな分からなさや、複雑さに山崎さんは「暗黒」を感じるらしいとわかってくるのだが。
全体が空間としてもやがかっている平井作品とは対照的に、確かにそこに存在するヒトやモノが、一体どういう意味をもっているのかさっぱりわからなくなってくるというタイプの曖昧さでガンガン殴られているような感じがした。とても衝撃的な作品なのだが、一つ、この作品のおかしさが伝わるかもしれないと思った私の勘違いを書いておく。実は本番前日の最終リハーサルで山崎さんはやはり折につけ舞台上に出てきて客席に向かって喋っていたのだが、同時にしょっちゅう「違います!そこは、こうです!こう!」とダンサーの振りをその場で「こう!こう!」と指示語を連発しながら自分が実演し、いわゆるダメだしを大声でしていた。あんまり堂々としているので、私はてっきりそれも「出てくるはずのない演出家が出てきてしまう」という演出なのだと思っていたら、翌日の本番ではダメだしはやっていなくて、逆に驚いた。
以上4作品が、札幌のコンカリーニョで上演された。(舞台写真はこちらでもっとご覧になれます。 https://flic.kr/s/aHsksRUSMk )
ダンスがフィジカルなばかりの表現でなく、身体や音はもちろん、言葉や空間、さらに言えば場所の力を取り込む、観客の意識をあらゆる手を融合させて揺さぶる呪術的な行いだと思い知らされるラインナップだ。二度あった公演はどちらも満席で、客席は開演前は明るい雰囲気に包まれていたが、休憩中と終演後は別の興奮状態が感じられた。「踊2」は力のあるコンテンポラリーダンサーの作品の作成期間を、そのまま連続する公演群として立ち上げているということと、各都市でのダンサーや観客との交流が特徴なのだと思う。ツアーの一箇所目として、観客にも劇場にも特別の熱意がある札幌のコンカリーニョで開催されることは、観客や劇場が持つパワーを、作り手に直に感じてもらうための直球なのだ。
ところでこのコンカリーニョに始まり、全国を巡って作品に磨きをかけ続けた「踊2」Aプログラムは、最後に東京で公演を行う。実は東京会場となるアサヒ・アートスクエアは、この2016年3月で26年間の運営期間を終えて閉館することが決まっている劇場だ。観客として作家の作品を期待することは当然だけれど、場所が作品に与える影響も小さくない。私はアサヒ・アートスクエアがその存在を示す、ほとんど最後の公演として私は、3月26・27日の東京公演を目の当たりにするつもりだ。