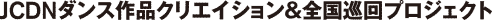2016年01月20日
鼎談「ダンスと言葉」
会場:未生文庫
<喋るのもダンス 、というアプローチ>
み:去年の作品の例で言うと、目黑大路さんの作品「ナレノハテ」は、「言葉とダンス」でしたが、あれはどういう経緯だったんですか?
さ:結局、僕は踊れないわけですよね。踊れないっていうのは何ていうんでしょうかね、ダンスが持つような踊り方って言うんですかね、ダンスのルールにのっとって僕は身体を動かさないですよね。そもそも、体操でも構いませんが、キチンした動きの発表会なんかしたくない。そんなことをやってたら意識的でも無意識的でも、後の世に戦犯扱いされるかもしれませんよ(笑)
み:ダンス的な訓練を受けていないから?
さ:そう、ダンスの訓練を受けていないので。例えば拍をとって手を動かしたりとか、いきなりステップを踏むとかできないし、やりたくないし、照れくさいしっていうようなことがあるから、舞台にかかわったとき、何を頑張るかって、立ってるとか座ってるとしかできないんですよ。その中の一つとして、しゃべったんです。
み:喋るのもダンス。
さ:そのダンスのルールに則ってないだけという意味では。ダンスをどこからみるかというのがあると思いますし、立ってたり座ってたりするのもダンスだということも可能でしょう。そこにいるだけでいい、舞台芸術として見ちゃえば別に立ってたり座ってたり、またそこでのたうちまわったりしてても、「ナレノハテ」では、しゃべる以外では、拘束されてのたうちまわってました。のたうちまわっているのは目黑さんも私も中西くんも同じですよね。拘束を解いた後は、目黑さんは<踊る>ダンスの領域で踊るわけですよね。中西くんに関してはちょっと何て言っていいか分からない。そこはおいといたとしてもそれぞれが別になったとき、僕がダンス批判、しゃべる内容も舞台では、ああしなきゃいけないこうしなきゃいけない、見せ方などの舞台のお約束の批判をします。舞台で当然だと思っていることをとにかく僕にあった足枷と同じだということで、のたうちまわるように批判する、暴露をしていくようなことをやっていました。ダンスの中で言葉を使うと、距離感がありますから、簡単に批判的になれるんですね。それはそれで面白くないので、冷静な批判というよりも、感情的にやりました。で、あとはサービス精神で、いつもよりも早口にしてみました。ここがいつもね、劇場でやるときの最終的な枷だなと思ってるんですけど、やはり劇場でやるからには観てもらわなければならない、例えば、伝えたくないってことの意思は伝えるべきだと。面白くないんだってのを伝えるためには、面白く面白くないことを伝えなきゃいけないんだと。
み:「ナレノハテ」に関して言うと、観客の反応として、言葉が饒舌すぎてつまらん、と、あの言葉があるから良かった、という正反対に二分されたのが驚きでしたね。私は喋っている言葉自体がダンス的な表現だなと思ったわけですが、ダンスに対する定義が狭くなっているのかなと感じました。
い:<NPO法人ジャパン・コンテンポラリーダンス・ネットワーク>が主催の「踊りに行くぜ!!」という企画なわけですから、一般的なイメージだったら「がんがんダンスするぜ!」って思いますよね。でもこの企画で目指したいのは、ダンスの定義を拡張していくことなんでしょうね。しかし、実際はお客さんから「ダンスのシーンが少ない」「全然踊ってない」と言われることもしばしばあります。もっとダンスが見たい、って。純粋な意味での「ダンス」です。ダンスの定義というのが、作り手と観客でズレたまま作品が発表されてしまうことになります。
さ:欲望を抱えて人々は来るわけじゃないですか。観たいものが観たいという欲望を。それが、自分が観たことない人のものでも、これだ!ってことじゃなくても、なんとなくでも観たいと思っている何かがあって、そういうものが観たいんですよ。
み:「ダンスが見たい」という欲望が、ダンス”だけ”を見たい、ということに繋がるわけではないはずだけど、観客にはダンス公演に対する想定があるのかな?60年代頃の舞踏を観に行った観客は、当時の“ダンス公演”という想定をはるかに超えたものがでてきて、ドッヒャーとなったわけですよね。
さ:ダンスだけのことじゃないですが、感動したい、美しいものが見たいという欲望がありますよね。商品としてのダンスを求めているわけですよね。そこにお金を払っているわけだからそういうのを消費物としてみたいわけですよね。僕の場合だと、食べ物に関しては、あんまりグルメでもないので、ただ安くて美味しいものが食べられれば満足ですけど、子どもの頃から美食でならされていたら、変わったもの、自分の味覚を超えるようなものを食べたくなるのかもしれませんね。僕は食べ物に関しては保守的というか貧しいので、美味しいものしか今のところ食べたくない。実験的な料理やおしゃべりな料理なんて求めませんよ。
ジャンルに対する疑問があるかどうかというのは大きいと思います。綺麗なものばかり見ているとなんだか不思議な気持ちになるものです。それを綺麗だと思いつづけるのは何故だという疑問もおきます。ある時代、ある国になぜ流行りのデザインがあるのか、そのデザインを綺麗だと思う国はどんな国であるのか、と考えたときに、整然としたものを綺麗と思う場合は、整然としていないものを排除しようという思想がありますね。そうなると、整然としたものを綺麗だと思うことに、綺麗だと思う自分に疑問が起こる。自己言及が始まるんですね。そうなると、破調の美にうたれる。まあ、これも、半可通の人なんかが陥る罠みたいなものですけれども、僕はもう、なんだか分からないんですよ。予期しないことに会えばそれだけで楽しくなっている節がある。
城崎で桑折くんが「自分の舞台はキレイなだけって言われるんです。」って言うんですね。僕も映像をみて確かにそうだなあと思いました。舞台効果として綺麗な世界を築くことが目的化されていると思う箇所もありました。しかし、いろいろと話してみると、その綺麗なものを作るということに、桑折くんの業みたいなものがあって、桑折くんは舞台で綺麗なだけって、批判されたとしても、桑折くん自身が綺麗なものが見たいんだと強く願っている。僕は桑折くんの舞台に感銘は受けなかったけれども、それが悪いっていうのじゃない。桑折くんの業として色々分かると、破調だーっとか、ぐちゃぐちゃにならねばならないとか、僕が抱えているものは桑折くんとは別の業があるかもしれないが、桑折くんのように綺麗なものを作ることが目的にもなるってのは形式や形骸化というのとも違うと思う。僕にはあんまりものを見る目がないから見るだけじゃ気がつかないこともあるけど、話していたときに感銘を受けました。いつもなんとなく綺麗にしちゃうっていう演出家とは違うわけですよね。
なんとなく綺麗に作ったものを良いと思うってことがダメだというつもりはありますが、ただコンテンポラリーダンスの目的は、美しいものやダンスって言いながら、規律訓練に従った綺麗な体の動きを見せるようなことはしないかもしれない、踊りはないかもしれない舞台表現だって認知があまりないんでしょうね。芸術って言葉を照れもなく使うと、近代以降の芸術はすでにある既存の価値観との戦いというか、批判というか、そういうものじゃないかと思うんですよね。
い:そうするとダンス公演で、「踊りは無いかもしれませんけども、ダンスなんです」というようなことを、どう成立させられるかという挑戦になるわけですね。
<宣言が足りない>
さ:モダンダンスやジャズダンスにしても、それはある規律訓練により培われた中のダンスなわけですよね。それぞれの美学の中にいるわけだけど、大げさにいえば、そういった身体の規律訓練に敢然と立ち向かっているのがコンテンポラリーダンスだと思っています。その意図すらもあまり浸透していない。ただ風変わりなものをやるダンス、コンテンポラリーダンスってヘンなの見せられるからやだなって人は多いと思う。
コンテンポラリーダンスが浸透しないのは、やはり説明というか宣言が足りないんじゃないでしょうかね。舞台上でというより、それ以外での。
み:そうかもしれないですね。その宣言をしようとするとき、全体像を捉えて公的なものを見つけるのは難しいなと感じています。コンテンポラリーダンスはジャンルではないので、それこそ評論家も振付家も目指すところや、掲げるとことが異なってくるのも当然なので、カンパニーや個人、組織がそれぞれの宣言、表明をするしかないというか、それをはっきり出していけば逆におもしろくなるし、明確になるように思います。
今回のテーマ「言葉と体」は、ダンスの今を考える上で、キーワード的なものだと感じています。舞踏が創立された1960年でさえ、言葉と体は、裏腹にあったはずで、そうでないと表現できない領域、社会に対してアンチであること、それまでのダンスそのものにアンチであること、舞台で美学の概念をつくり出してやろうという心意気があったんじゃないかな。だからアートをやる意味がそこにあったわけで。そこからもう50年以上経っている今、ダンスというものがこのあたりの意識から切り離されてしまっていることに、私はもどかしさやジレンマを感じてしまいます。孤立的な個人的な表現を極めていくと、それが強ければ強いほどそれに共感できるものに繋がるのかなと。そこには、ダンスと言葉が対になる必要があったはず。
さ:僕はそういう意味でダンスに出会うのが遅くて、2001年からなんですね。たまたま土方巽記念アスベスト館で自分の劇団の旗揚げ公演をしたんですよ。その前から土方さんの本とか言葉、『慈悲心鳥がバサバサと骨の羽を拡げてくる』が学生時代にCDで出て、聴いてたとかそのくらいであんまり舞踏とか率先して見に行こうと思わなかったんですね。ダンスには興味ありませんでしたし、裏方の仕事でダンスの発表会や公演をやると、やっぱりダンスに興味ないな、と思って距離があったんですけど、アスベスト館で旗揚げ公演した後に、アスベスト館の舞踏を演出することになったりして、そしたらいろんな人に会うようになって、ダンスについて書かれた本なんかも読むわけですよね。そうすると、なぜ、そういう動きがあったのか、なぜこういう舞台だったのかという問い掛け、問題提起みたいのがバーッと出てきてしまって、それまで手にも取らなかった現代思想なんかも読みながら考えるんですが、ダンスと言葉について、思想について考えていくと何時まで考えても追いつかない、ダンスを観に行っても混乱しながらずっと舞台見ているような状態でした。そこで気付いたのが今度はどんなものにも意味があるように思えて来てしまう。ダンスをしている本人がそんなに考えてなくても僕の中で勝手に考えるようになっちゃって、どんな舞台でも同じようになるようなことが起こった。急に詰め込んだので、麻痺したんだと思います。多分やる人たちは気付いたと思う、考えなくてもやってれば、専門家たちが勝手に語ってくれると。
み:そういう意味の言葉の位置づけもありますね。ダンスを観る楽しみとして、観る側が好き勝手に想像を膨らませて観れる、という良さ。
さ:自分たちで語らなくてもいいやってなったんだと思います。無力な体と一緒で、無力な言葉になっていって雰囲気だけをやればいいってなったんじゃないですかね。個人的、孤立的なものも、自分の今の生きている様、戦いとしての日常性、わたしは圧倒的に個人的で孤立だというような日常性ではなくて、もうちょっとなんとなくボンヤリでいいんじゃないかっていう日常性に焦点が当てられ、共感できる日常性っていうのが重要視されたと思います。共感できない日常性っていうのは、水野さんのようないろんな人から共感されない日常性は求められてなくて、みんなが共感できる、「あるある」っていう共感できる日常のほうをみんな見たくなっちゃった。
み:あるある。それはもうねえ。
さ:それまでは舞踏家の居方って独特で、そういう人たちの視点に怯えたもんなんだけど、そういう人たちが普通の人たちになったっていうか、相田みつをみたいになったんで、なんか安心ですよね。何やっても一歩だけ踏み込んだ「あるある」です。表現者たちは厳しい視点がなくなったから楽になって喜ぶし、ダンサーたちの集めるお客さんたちもそういうのを喜ぶようになり、見に来る人たちもそういう人たちばかりになり、みんな「あるある」のなかにちょっと綺麗なところがあればいいっていうか、ちょっとスパイスの効いた暮らしが良いみたいな感じの舞台作品が増えたような感じがしてならないんですよね。そうなると水野さんが言っていたような個人的孤立的な存在自体がもう必要とされなくなった。
み:あ、やばいじゃん。
い:全否定。
さ:三島由紀夫が『太陽と鉄』の中で面白いことを書いてて、言葉っていうのは本来みんなに通じるという公共性が言葉の道具としての重要な役割であるが、言葉を芸術にするというのは、その全く逆になり、言葉を個人的にしていくからどんどん人に通じない言葉になっていくんだ、と。言葉の芸術化がいやになって、神輿を担いでいる青年たちに憧れ、あの青年たちはどんな風景を見ているんだろうって自分もそうなろうと思って身体を鍛え、神輿を担ぐ青年に自分がなってみると、そこには何もなかった。
み:そこには何も無かった、という結論?
さ:なかったみたいですよ。だけど三島は身体を鍛えれば鍛えるほど身体というものはやがて崩壊していくもなんだと見つめるようになる。「死」というものが一つの大きなものになっていく。死の平等性、死の舞踏ですね。言葉が持つ永遠性と孤立性みたいなものから死にゆく肉体を持つ全ての人を持つ「死」になったんですかね。「詩」と「死」なんて言ってませんでしたけど(笑)
み:三島が最後に逆三角形の鍛えた体につくりあげて、最終的には自分の身体のナルシズムに傾倒していたことは確かなんですよね?
さ:三島が何をしたかったか僕にも分からないけれど、肉体を鍛えたときに窓辺に座って風が吹いたら身体が冷えてくじゃない。そういうときに寂しい想いをするなんてことも書いてましたね。その話を目黒さんにしたら「すげーよくわかる。」って喜んでました。