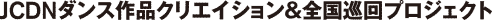2016.03.22
平井優子作品紹介『Ghosting~軌跡の庭』
作品紹介/インタビュー記事
仙台公演 photo:Echigoya Izuru
関西圏を拠点に活動している平井優子さん。意外なことに平井さんとは、今回が初顔合わせとなる。平井さんの活動歴は、バレエを出発点にコンテンポラリーダンスに進み、フランスで研鑚。その後、ダムタイプ・藤本隆行・高谷史郎など国内外で活躍する主たるメディア・アーティストの作品に、振付・ダンスとして共同制作で関わってきている。近年では、果敢に自身の作・演出品制作に取り組み始めている。
平井さんは、囁くように話す。その話を聞き洩らさないように、1歩平井さんの方に近づき距離を縮める。以来、今日まで数回同じ動作を繰り返す度、デジャ・ヴュ的感覚に陥っていた。1月初演の札幌から、松山・仙台公演を終え福岡公演前日のリハーサル後、「報告するぜ!!」の佐々木冶己さんにも聞き手に加わってもらい、楽屋でインタビューを行った。
*****************
空間が息づいているということがあれば、例えば、人が出ていなくてもいいと思ったんです。
平井さんには、2つの異なる身体性がある。
岡山県北部の山間地域の民話や口承文化をリサーチして制作したという作品「猿婿」での平井さんのダンスは、土着的な節回しの唄と呼応する日本の芸能のような体の使い方を見せてくれる。
一方で、メディアの中での体が必要とされる作品では、計算された西洋的な機能を持った体となる。どのようにダンスであれば、世界を変えてみせられるのか、を知っている体。
バレエ出身の平井さんが、メディアとの制作に興味を持ち、ダムタイプのようなマルチメディアのアーティスト集団の中に入り振付・ダンスをやりたいと思うようになったのは、どういうきっかけがあったのだろうか。
「自分は空間のことを考えながら、そこにいるというのが好きなんだとおもいます。
幼い頃バレエの初舞台のとき、演目は『シンデレラ』だったんですが、仕込みのあいだ舞台スタッフさんが装置を組み立てているのをずっと見てました。動きの練習をするバレリーナの隣で虚構の世界を作っていくんです。とってもわくわくしました。虚構ばりばりの本編よりも魅力的でした。今でもよく思い出します。そういうリアルな身体とあらゆる要素が時にちぐはぐで、時に素晴らしく融合するようなものに興味があります。
あらゆる要素がひとつの世界感を同時にあらゆる方向から構築していくということが好きなんだと思います。」
今回の新作「Ghosting」でのチームメンバーは、平井さんとは馴染みのメディア・プログラマーの古舘健さん、以前からファンだったという詩人で音楽家のAGFさん、そして、舞台の世界とは少し縁遠い庭師の山内朋樹さん、岡山のダンサー中尾舞衣さん。言わば、デジタル系との混合メンバーとなっている。この面子での平井作品の制作は、もしかしたら新境地かもしれない。とは言え、ダンス以外の要素、映像・音・照明というものが重要な要素としてあるこの作品、今回このチームで取り組もうとした意図はどのあたりにあったのか。
「近年、自分のパフォーマンスでサイトスペシフィック空間でパフォーマンスを構成するということを意欲的にやっていたんですけど、そこでは光や音が流動性を持っていてそれらを活かす、それらに活かされることが面白かった。
そして今回そういう外光や遠くに聞こえる騒音などがもたらす効果がない劇場だからできる空間づくり、を一緒に考えてくれそうな人とやりたかったんです。
AGFにも最初のキーワードとして’Enormous creature’といったのですが、大きな息づく器官のような空間にしたいと思いました。空間が息づいていているということがあれば、例えば人が出ていなくてもいいと思ったんです。そのくらい空間自体が有機的に動いていて、それを振付けることもおもしろいかな、と。光と音のうねりのようなものを。これは今後の課題として残っています。
舞台上で人に振付けるウエイトの大きさと変わることなく、私にとっては興味があります。」
*********
言葉を並べて時間、空間をつくり出したい。
言葉の意味をできるだけ排除した“声”で想起させる世界
今回の作品は、音楽というよりも詩・ボイス・フィールドワークから集めたかのような音・自然の中のノイズ、と言った方が伝わるだろうか。メロディやリズムが刻まれる楽曲ではない。確かに平井さんの思惑のように、言葉を音として捉えたり、風景が見えてくるような音の存在が、作品を際立たせているようだ。新作のアイデアの段階のコンセプトシートに、「音」の役割が明確に記されていた。
音や輝きは触知的に我々の記憶を換気する。そしてそれは言語が違ってさえ起こる。つまり意味を排しても声そのものに生命を感じるからだ。ドイツ人の詩人であり音楽家でもあるAGFは、音声による詩とフィールドレコーディングによる風景描写を融合した音楽を作り出すアーティストでもある。彼女とのコラボレーションから、ある音声空間をつくりあげた多声ポリフォニーの響きの中にあるナラティブなものを換起するためのサインを丁寧につなぎ、ひとつの新たなストーリーを紡ぐ。
平井さんは、以前からAGFの音が好きでよく聞いていたそうだ。今回、映像の古舘さんの知り合いで声をかけ、城崎国際アートセンターでのクリエイションに参加することが実現した。AGFさんは既に日本で数回、作品制作したこともあり、日本の俳句を題材にした作品もある。今はフィンランドの大自然の島を拠点に活動しているそうだ。これまでの作品を拝聴すると、とても詩的な音づくりをしていることがわかる。ちょうどAGFが日本に来たころは、難民が欧州に押し寄せている社会問題がニュースで報道されていたり、パリのテロ事件が起きた頃だった。城崎ではAGFと平井チームメンバーで、作品を巡る様々なテーマを掘り下げるよい機会となったはずだ。
(城崎国際アートセンターのロビーでAGFと英語の会話もできるロボット「ペッパー」君と)
実際に客席で聞くAGFの詩は、たどたどしい日本語として発音される。意味が分かるようで分からない、かといって何も意味が通じないわけではなく、ワードとして断片的に言葉が耳に残ることで、舞台上で行われている事柄のイメージを増幅させてくれるという不思議な作用が成されていた。普通、言葉の意味というものは直接的なディレクションを与えるので、時として観る側が制約させられてしまうこともあるが、AGFのボイスはそこをフワリとかわして、私たちに謎を投げかけてくれるのだ。
「そうですね。あれは言葉の意味を脱臼させていくといいますか、意味をなくしていく。お互いに何度か往復のやり取りをして、ある文章を、最初はとても意味のある言葉だったんですがお互いに翻訳し、意図的に意訳を介して意味をなくしていき、最終的には彼女は私がローマ字で書いたものを読んでいるので、彼女が自分で意味を込めて喋っているわけではないんですよね。言葉としての死んだもの、誰かが発したんだけど、生きていない言葉であり、単なる声といて扱いたかった。もちろん単語や音として意味が見えてくることもありますし、あえて意味として使っているところもあります。
声を音としてどう扱うか、声という登場人物がどうやって一緒にいられるのかなどを考えながら色々と試してみました。言葉を並べて時間、空間を作りだしたい。意味をできるだけ排除して、声によって人に想起させる、そんなことができないかとか。そして人格でも、声でもなくなって、歌になる、音になるとか考えてます。AGFさんの声は本当に素敵なんです。とっても好きです。」
*******************
生と死を同等に扱う。影に寄りそう。
同席した佐々木さんは、「不気味」に感じたらしい。何故かと言うと、単に生きている者と死んだ者、存在しないものと存在しているもの、という対比であれば解りやすいが、平井作品をみると単純にそうなってはいない。それが、不安になって不気味に感じてしまうそうだ。確かに作品中に生と死が同居している。どちらかというと、暗闇・死のイメージが強い。そして平井さんは、死を当然のように易々と受け入れ、それどころか楽しそうに死者=影と戯れてさえいるように見える。これがまた佐々木さんに不気味さを感じさせる!平井さんの死生観と、この作品に気配を感じるが姿が見えないもう一人の存在・不在者の存在・気配とは何なのだろう。佐々木流にいうと「誰かいる!」。
「不気味なもの、理解しえないものが自分たちの世界には意外と多く存在するとおもいます。そしてその暗闇のなかで一生懸命目を見開いて見ようとすると、自分の存在が脅かされてとてつもなく怖いと感じて、光があるとつい無条件に信じてそれを頼りたくなる。
一方、目を閉じることで身を守りながら身体を任せると、意外と心地よく勝手に動いていく、そんな感じがあります。
対象を「見ること」と「見ないこと」でおこる主体のポジションの変化というのがひとつ始めにあったんですけど、それを死生観でいうとするなら在、不在というものが角度を変えることによって同等になったりして、でもそこには背景があって、それぞれの目線できっと見え方が違うんだろうな、と。」
「お能の幽玄というものにとても興味を持っています。お話形式、つまり死者が普通に登場人物して出てくるようなものは昔から多いですよね。そういう扱い方は面白いと思っています。
何かで読んだんですが、資本主義になってからの建築様式では日常社会のなかで、死というものを生活からなるたけ排除している。死を特別視している。きっと死を怖いと思うのは近代人なんですね。けれどもそれ以前では、死は身近なもので、もっと日常に混在していたそうです。そういう意味でいうと、”気配”というものに対して、私の指向的にも中間的なものが好きなものですから、白か黒かではない間の部分、それは言葉とかかたちを割り当てられない部分のことなのですが、そういったものに出会うとはっとします。
下には人がたくさんいる。「庭」そして、土地が待つ“土地の記憶”
福岡公演 photo:富永亜紀子
水銀灯や電球、スモーク、映像、デジタルな計算された舞台効果の演出が楽しめる作品なのだが、そうすればするほど逆に「闇」や「影」から死・死者の存在が際立ってくる。今回、フランスの哲学者・庭師であるジル・クレマンの「動いている庭」からインスピレーションを得て、舞台機構を庭にみたて平井さんが現出させたかったものの正体とは?
「”庭”そしてその“土地が待つ記憶”とも言えます。土の下には幾重にも堆積する人々の記憶が眠っている、というイメージは皆さん持っていると思うんですね。時代を経て、たくさんいるんですよね、きっと。土の下や池の下にはたくさんの人が泳いでいるんですね。上からの光は饒舌で我々を誘導してしまうのです、下からの影というがどこに連れて行ってくれるのかはわかりませんがそれらを意識して、そういういう構造をつくろうと思いました。
非日常感というか、普通じゃないものをわりと求めているんですよね。日常的なものを描いていても、最終的には非日常だな、と観ている人たちに持って帰って欲しいと意識しています。」
ドキッとすることをさらっと話してくれる平井さんは、最後にこう締めくくってくれた。
そうなのだ。この作品にはいくつものマジックのようなものが隠されていて、いつの間にか日常ではに何処かに連れられていくことが心地よい。信じて疑わなかったものが、ふと、なんだ違ったのかと思えたり、見えなかったはずの存在に気がついたり、価値観を揺すぶられることを楽しみに、そして、地中からの声が聴こえるといいなあ。